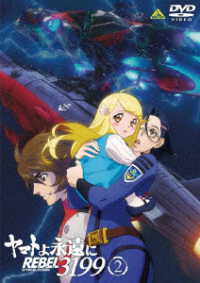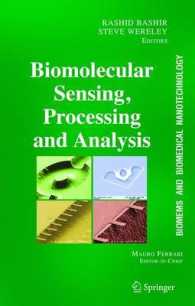出版社内容情報
1950年代の粛清の嵐で生き残った共産党改革派は,スロヴァキア派と組んで68年に政権を獲得,民衆の動きが呼応しプラハの春が訪れる.だが,ソ連の介入にスロヴァキア派は――.新しい視点から見直す.
内容説明
50年代の粛清の嵐を生き残った民主改革派は、チェコ主導の政治に反感を持つスロヴァキア派と組んで68年に政権を獲得、民衆の下からの動きが呼応しプラハの春が訪れる。だが、ソ連の介入にスロヴァキア派は―。新しい視点からプラハの春を見直す。
目次
戦後改革と連立政権
スターリン化と粛清
改革の序曲
1968年改革と軍事干渉
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイ
136
スラブ関連歴史に触れてみたくて、薄いこの本から始めることにする。旧帝国の名残か、東欧内では知識人を多く有し、生活水準も高かった。チェコとスロバキアの対立なしには語れない。大戦中もそれを独ソ両国に利用される。プラハの春は、チェコのもの。スロバキア人にとってはプラハの春という呼称自体がおかしい。共産主義思想は旧ブルジョワに冷たかった。例えばハヴェルは、ブルジョワだったために教育を受ける機会を奪われ、工場で働きながら夜間に通う。プラハの春が起こる前、チャウシェスクやチトーが歩み寄ろうとしていたとあるのが意外。2017/05/26
扉のこちら側
66
2016年1121冊め。プラハは国家の首都だがスロヴァキア人からみるとそれは「チェコ人のもの」。スロヴァキア人にとって「1968年の春」はまず、民族として対等と自立を獲得することであり、そもそも「プラハの春」という言葉自体に問題が含まれているらしい。これまで考えたことのない新たな視点だった。2016/12/20
ジュンジュン
11
戦後のチェコスロヴァキアの歩みは、一見他の東欧諸国と同じように見える。表層に表れる政治現象を追いかけてみると、社会主義の導入→粛清→反発(プラハの春)→弾圧→’89東欧革命と大体同じコースを辿る。しかし、かの国を他と分かつ特徴がある。それはイデオロギーで覆われていたため、目立たなかったが、ずっと底流し続けた根源的な問題。それは建国以来ずっと克服できずに持ち越されていた課題。それはチェコ人とスロヴァキア人の民族問題。最終的には分離独立という形になるこの問題から、同国の戦後を考える。2023/02/11
Fumitaka
3
戦後チェコスロヴァキア史の簡単な概説。出版はまさに動乱期の1991年で、結論部分でも今後の展開について「今の時点では判断がつきません」(p. 61)と書かれている。冒頭の地図にある、ごく一時期に採用されていた国名「チェコ・スロヴァキア」も時代を感じさせる。チェコの東欧革命がペレストロイカという不可欠の要素(pp. 3-4)に影響されながら、プラハの春など土着の要素も意識していた(p. 59)ことが指摘され、奇しくも「ソ連」「地元の要素」という二つの絡み合いを、スロヴァキア人問題に言及しつつ論述している。2023/02/07
しろのやま
2
1989年の東欧の政治変動を考える上で、特にチェコスロヴァキアに絞り1968年のいわゆる「プラハの春」を通して概観されている。ノヴォトニーやドゥプチェク、フサークら国内政治家の動きとソ連を中心としたWTO諸国との関係が分かりやすい。ページ数的に充実した内容だが党と内閣と軍と民衆との関係をもう少し踏み込んで欲しかった。しかし参考文献一覧もしっかりしておりありがたい。なお記述されているようなスロヴァキア人の不満が国家分裂という形で現代にも影を落としていることは感慨深いものがある。2014/11/24
-
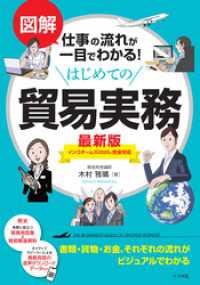
- 電子書籍
- 図解 仕事の流れが一目でわかる! はじ…