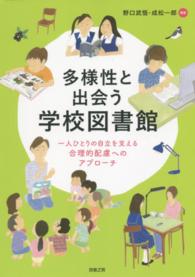出版社内容情報
近代的主体の構造を攪乱し,人間の尊厳の多様な在り方を肯定する社会秩序は可能なのか.ニーチェ=フーコーを大胆に導入し,90年代の政治理論に大きな衝撃を与えた本書は,差異の政治化による新たな政治空間の創出を試みる.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
てれまこし
7
米国でもポスト近代思想が闊歩していたのは文学部くらいで、政治学部では肩身が狭い。コノリー先生はその政治学におけるポスト思想の擁護者として広く尊敬されてる。だが、個人及び集団のアイデンティティを守るために多様な生のあり方が犠牲にされることに対して、先生がもち出したのはなんとニーチェのルサンチマン批判である。日本でこれに対応するものを考えると保守派知識人の左翼批判である。下手するとリバタリアンにもなるニーチェから左翼ニーチェ主義を分けるのは、後期近代では「超人」と「畜群」がもはや別個の集団ではないという点。2025/07/15
有智 麻耶
3
差異を他者性に転化し、それに悪の責任を負わせることで自己のアイデンティティを真正なものとして確立する。そのような形での他者の排除は、アウグスティヌス以降の伝統であり、後期近代においてはより一般化した病理となっている。コノリーは、生におけるアイデンティティの必要性を認めながらも、その偶然性を強調し、「アゴーン的敬意」の倫理を涵養することを訴える。20年以上前の著作でありながら、現代の社会を分析する上で有益な視点を提供してくれていると思う。しかし、他者との「距離」を政治的手段によってどうにかできるのかは疑問。2018/07/08
砂糖 翠
0
精読のために再読。本書における主張とは一貫しており、コノリーの言葉を借りれば、超越論的エゴイズムにいかに立ち向かうかということであろう。後半になされるニーチェの解釈によって、死から生を意識させるというのは、プルーラリズムにおいて概念化されている存在の政治、生成の政治につながっていくことがよくわかる。 本書において物足りないのは、アイデンティティは一連の差異から構築されるのはいいとして、この差異を持つ他者あるいは、悪を押し付ける他者性そのものがあまり多くは語られていなかったような気がする事。2015/12/19