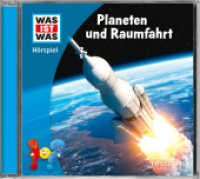- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 図書館・博物館
- > 図書館・博物館学一般
目次
1 一人ひとりの特性や思いを生かス学校図書館(「多様性と出会う学校図書館」を考えるための3つのキーワード;一人ひとりの特性とニーズを知るために)
2 読書と学びをサポートする場所づくり(「生きる力」や「自立」につながるさまざまな資料やサービスを;個々の学びのスタイルで取り組む探究型学習;読むことが苦手な子どもたちも図書館は大好き;ロービジョン当事者が語る「子どもと読書」「図書館利用術」;全盲徒徒のiPad活用から見えてくるデジタル時代の授業の可能性 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
sazen
6
📌病弱、貧困、障がい、海外にルーツのある子供、LGBTなど、マイノリティとして扱われやすい立場の子どもたちへの図書館的アプローチ本。単に珍しい活動を展開している図書室、の紹介ではない点が良い。神奈川の施設が多く紹介されていて、個人的にはとても身近に感じる。海外の学校図書館との比較から日本の学校図書館司書の立場が曖昧模糊すぎる現実がより明確化されていて、なんだかな…と思う。フランスの場合は、教育者として扱われるんだね、びっくり。クリエイティブスクールの存在も初耳で、興味が湧く。2023/09/03
ぴょんす
2
LGBTの生徒についての例で出ていた「先生の机にLGBT関連の書籍が並んでいて『勉強してくれてるのかな』と思えたから自分のことも告白した」という文章が印象的だった。本は読むものとしてだけでなく、意思表示としても機能するのか、と感じた。 2018/09/04
ティパリン
2
つい‟大多数”に合わせがちだが、その子が何を本当に必要としているのか、どう支援するか、一人ひとりとしっかり向き合わねばと思った。2018/05/20
caliculus
2
『一人ひとりの読書を支える学校図書館』の待望の続編。2016年4月施行予定の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を前に、障害のある生徒への合理的配慮について考えます。参考となる事例として、ありとあらゆる場所で実施されている読書教育について知ることができ、驚きと自身の至らなさの実感の連続です。多様な人それぞれに合った支援を探るということ。どこまでも人という存在の奥深さを教えてくれる本でもあります。2015/11/17
NakaTaka
0
ずっと前に買って読んでいたのに記入漏れ。障害者差別解消法施行の今こそ。2016/09/25
-

- 電子書籍
- 世話やきキツネの仙狐さん(11) 角川…