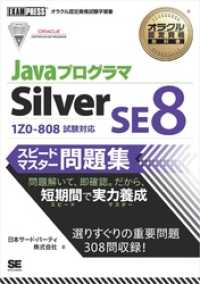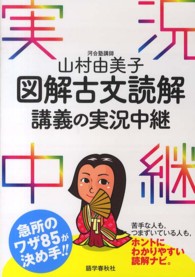出版社内容情報
大惨事はなぜ常に”想定外”であり,不幸の予言は聞く耳を持たれないのか――.現代フランスを代表する哲学者が,18世紀リスボン大地震からアウシュヴィッツ,ヒロシマ・ナガサキ,9.11,スマトラ沖地震という歴史的経験の考察を通して,「破局の未来」にどう向き合うかとい
内容説明
大惨事はなぜ、常に“想定外”なのか―リスボン、アウシュヴィッツ、ヒロシマ、ニューヨーク、スマトラと破局をめぐる哲学的考察。東日本大震災を受け日本語版への序文を付す。
目次
始まりの時(未来を悼む;破局と悪)
リスボンからスマトラへ―悪について私たちは何も学んでいない(ライプニッツ;ルソー;ヴォルテール)
悪を自然のもとに返す(ニューヨーク;アウシュヴィッツ;ヒロシマ)
未来の破局という問題(犠牲者の混同;未来を聖なるものにする)
著者等紹介
デュピュイ,ジャン‐ピエール[デュピュイ,ジャンピエール][Dupuy,Jean‐Pierre]
1941年生まれ。科学哲学者。理工科学校社会・政治哲学名誉教授、スタンフォード大学教授。フランス放射線防護原子力安全研究所(IRSN)倫理委員会委員長
嶋崎正樹[シマザキマサキ]
1963年生まれ。翻訳家・放送通訳。東京外国語大学卒業、同大学院外国語学研究科修了(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おっとー
9
地震、大量虐殺、原爆、テロ、そして原発…自然的・人為的を問わずこうした大量死の事件は全て事後的に分析され、「これが原因だ、こうすればよかった」と結論付けられる。しかし、統計や科学技術が発達した現在もこうした結論は全く生かされることなく、人類は常に大惨事にさらされる。となると、大惨事を回避可能なものとして捉えること自体が無意味であり、必死に研究しても分析しても、それを超える現象は常に起きてしまう。人類は大惨事を受け入れるとともに、あまりになんの脈絡もなく生じる悪の分析不可能な面を考えることしかできない。2020/12/06
左手爆弾
4
本書で語られる悪は、実に根深い。問題が大きすぎて、悪意を理由に特定の誰かを責めることができない。責任を問うにしても、それは事後的に「あの時ああしていれば」に止まる。それにしても「リスク」という言葉に集約される。「1000年に一度のツナミにたまたま遭遇しただけ」という開き直りで乗り切れてしまうのだ。リスクの判断は自己責任で、というわけだ。現代における破局や悲劇は、概ね悪意よりも善意から起こる。経済成長という善を求めて原発事故や環境破壊が起こる。私たちは悪に対する新たな向き合い方を問われているのだろう。2013/12/05
なさぎ
3
再読(輪読にて)。過去の自分の感想を見ると、やや読み違えていたかな、とも思う。本書の記述や引用は、一つ一つが「作者の意見の補強」「批判のための当て馬」のどちらなのかを、丁寧に見極めていかなければならない。話の流れ自体も飛んだり戻ったりする訳で、決して読みやすい訳ではない。ただ、慣れてきた今は、内容自体についてはさほど異論はない。——ところで、今更気付いたけれど4章の引用にカルロス・ゴーンのル・モンド紙記事があって、タイトルがずばり「国境を越えよう!」、爆笑した。2020/05/10
tamaph
3
本書は911直前に脱稿状態だったものから手を加えられ、スマトラ沖地震を機に2005年に発刊された。日本では2011年の東日本大震災の4ヶ月半後に翻訳版が刊行された。ツナミとは、もちろん津波のことだが、それを象徴として歴史上の自然的災害および倫理的災禍をも並列して俯瞰し、そのカタストロフィーに私たちはどう対峙できうるかを検証する。最後の西谷修氏の解説「「大洪水」の翌日を生きる」は、現代日本に生きる私たちの視点をさらに補完するものでとても腑に落ちる。最近の不穏な政治的動きに悶々とする中、命綱的に読んでいた。2015/10/07
ぶちたろう
2
様々な事例から人間の「悪」に対する認識を考察し、人類世界の破局・終末を避けるにはどのような思考の転換が必要なのかについての本。終末や自然災害などを悪と認識するなど所々にキリスト教的、西洋的な考え方が現れていて興味深かった。著者は人類の終末をもたらすとしたらそれは「システムとしての悪」だと語っている。文明社会が創造した様々なシステムが破局を演出する装置として働き、我々はそのことを承知していてもその歩みを止めようとはしない。それができるとしたらそれこそ著者の言うような奇跡でしかないのだろうか。2014/02/24