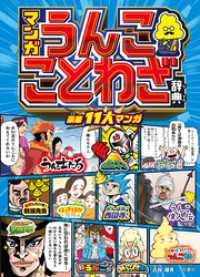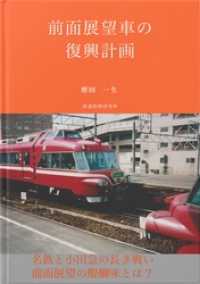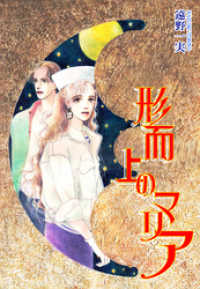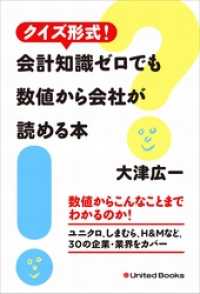内容説明
日本文明の大半は中世の寺院にその源を持つ。最先端の枝術、軍事力、経済力など、中世寺社勢力の強大さは幕府や朝廷を凌駕するものだ。しかも、この寺社世界は、国家の論理、有縁の絆を断ち切る「無縁の場」であった。ここに流れ込む移民たちは、自由を享受したかもしれないが、そこは弱肉強食のジャングルでもあったのだ。リアルタイムの史料だけを使って、中世日本を生々しく再現する。
目次
序章 無縁所―駆込寺と難民
1章 叡山門前としての京
2章 境内都市の時代
3章 無縁所とは何か
4章 無縁VS.有縁
終章 中世の終わり
著者等紹介
伊藤正敏[イトウマサトシ]
1955年東京都生まれ。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。思想家・中世史研究家。一乗谷朝倉氏遺跡調査研究所文化財調査員、文化庁記念物課技官、長岡造形大学教授などを歴任。現在は研究・執筆活動に専念している。文献史学、考古学、文化財保護行政などをフィールドとしている。研究対象は日本村落史と中世寺社勢力論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
クラムボン
18
最近は日本史の中世が、呉座さんの本で人気上昇中ですね。…とは言え鎌倉~室町・南北朝などは鵺のごとき世界。著者は中世の寺社勢力の存在は強大だと唱える。まずは中世の開幕を、祇園社が政治権力の及ばない《不入地》と認められた1070年だと、学会の通説への挑戦らしい。祇園社の境内は東山~鴨川西岸、三条~五条までと広大だ。そして延暦寺の本体は山上でも近江坂本でも無く祇園社だという。ここは山徒の居住地・青蓮院などの三門跡も有る。そして中世の京都は叡山末寺祇園社の門前に広がる町だと、大胆な物言いの数々はとても刺激的です。2021/12/22
かんがく
18
幕府、朝廷と並ぶ中世日本の第三勢力でありながら、教科書における記述は少ない。網野善彦でお馴染みの「無縁」をキーワードに、境内都市の動きを論じる。祇園社と叡山の関係や、僧兵、金融業者としての役割、民間信仰との繋がりなど極めて面白かった。中世の史料はほぼ寺社のものであるとのこと。2020/01/25
鯖
17
中世で唯一「自由即死」ではない寺社という空間について論じた本。よっつねが山伏に身を窶したのは公権力の検断が及ばない無縁の人だから。中世の僧は発心し出家した個人の集合ではなく、僧の家という世襲の職業集団。不邪淫京の僧侶は判例や法律に明るかったことから関東の御家人に代わり弁護士のように訴訟を代行していた。叡山は園城寺を50回以上焼き討ちしたが、写経して懺悔で済ませた。平重衡や爆弾正さんがかわいそう。自力救済中世ヒャッハーって現代人はバカにするけど、いじめパワハラ炎上と所詮は同類だよはその通りですよねとしか。2021/06/05
MUNEKAZ
12
現代日本において無縁社会は都市にある。そして、それは中世でも同じ。不特定多数の国内移民が暮らす匿名性の高い空間が中世のメガシティ・京都であり、そこを大寺社の神人や行人が経済的に牛耳っていた。ということで、中世社会の隠れた主役・寺社勢力の影響力を明快に論じる一冊。「武士と朝廷の相克=中世」ではなく、寺社勢力の存在こそ中世だと言い切る著者の言葉は力強い。祈りや教義ではなく、寺社勢力の経済的、軍事的な影響力に重点を置いた見方は面白く、中世史の捉え方を再考させてくれる。2024/05/05
イツシノコヲリ
8
中世寺院の見方が変わる書籍である。重版されているだけ面白い。境内都市についても書かれていて、高野山が先進的であったことを理解した。2023/01/10