出版社内容情報
シリーズ解説:
「彼を知りえたことは私の生涯の中で最も刺激的な知的冒険の一つであった」という B・ラッセルの証言を引くまでもなく、ウィトゲンシュタインの哲学的思索の軌跡は、二十世紀の知的世界が遭遇した一つの事件であった。比類のない分析力のおもむくところは、論理的に完璧な言語の構想から、具体的な語の使われ方に文法を見出そうとするところにまで及び、考察の照準は、一貫して言語の批判に向けられていた。
内容説明:
「言語ゲーム」理論の総決算
「わたくしは、自分の手稿によって他の人が考える労を省くようになるのを望まない。できることなら、誰かが自分自身で考えるための励ましになりたいと思っている。」(序)このつつましい挨拶とともに公刊された『哲学探究』は、20世紀後半の哲学的運動において不断のエネルギー源であり続けてきた、いわゆる後期ウィトゲンシュタインの代表作である。「言語ゲーム」「家族的類似」「生活様式」「私的言語」等、現代哲学の主題をめぐって展開される透徹した分析は、読者の脳髄を刺激してやまないであろう。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
白義
15
本書は、哲学の終わりと、哲学の始まり、その二つが極めて近いところにある地平へと読者を駆り立てる著作だ。言語ゲーム、という、言葉の使用と行為、それらを常に成り立たせる規則の生起というイメージから、人間の行為、文、言葉、つまり「生きること」がそのままで全て独自の秩序がある、と肯定され、独我の迷宮は逆に、他者と世界の確信という新たな奇跡へと解消され、問いの地平自体が更新される。狭い意味での哲学はもはやその謎自体が消し去られるが、それは新たな問いと謎へ導く、広い意味での哲学の始まりとなる2013/08/21
てれまこし
8
ラクラウ、ムフでまた名を見たんで、とうとう観念して読んでみた。それでもわからないから二度読みしてる。だが、ひとが自分で作ったことを忘れてそれに作られるようになる最たるものは言語。ラカン精神分析における原体験も、それ自体というよりは言語学習の過程として理解しうる。普遍的言語の「論理」(単数)ではなく言語ゲームの「文法」(複数)。この違いが分かりにくいのは、本書の批判対象になるのが哲学言語(ゲーム)であるのに、ぼくらはこれを真面目に考えたことがない。だから当り前のことをわざわざ難しく言ってるだけに聞こえる。2025/08/07
飛燕
3
「ピンボケ」の比喩をはじめとす言語の考察は刺激的(形式に追従して事態を見る、など)。あと個人的に面白かったのは私的体験の話。私的な体験の本質とは、わたしと他者とが「異なる」ことではなく、同じなのか、違うのか、そもそもわたしがもっているものを他者はもっているのか、もっていないのか、全くわからないことにある、ということ。他者を「わたしと異なるひと」とは言えない。同じように、「わたしと同様、心をもっているひと」とも言えない、わたしがもっていると信じているものを他者にまで押し広げることこそ独我論になるのだろう2013/10/21
urza358
2
ウィトゲシュタインが日々何を考えていたのか、彼の頭の中の言葉の残響。全体としてまとまりがない告白であり、全体としてすべてを内包する啓示の書でもある。2010/04/25
tomad
1
まだまだ読み足りない2008/09/19
-
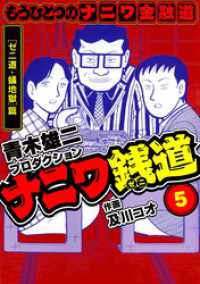
- 電子書籍
- ナニワ銭道─もうひとつのナニワ金融道5…
-
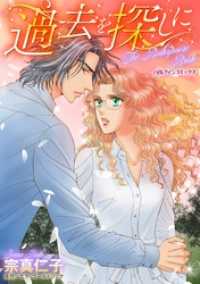
- 電子書籍
- 過去を探しに【分冊】 6巻 ハーレクイ…
-
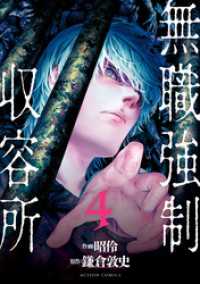
- 電子書籍
- 無職強制収容所 4 アクションコミックス
-

- 電子書籍
- C★NOVELS Mini クリザの平…
-
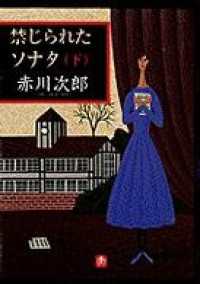
- 電子書籍
- 禁じられたソナタ(下) 小学館文庫




