出版社内容情報
楠船を操り黒潮の流れに乗ってやって来た海人族.白鳥伝説とともに移り住んだ夷たち.山深い中央構造線に沿ってたどる鍛冶神の足跡.各地に残された地名こそ弥生の時代から近世まで,名もなき人々の暮らしの記憶を伝えてきたものであった.これら小さな神々のあとを丹念にたどりながら,文書に記されないもう1つの日本の歴史を読み解く.
内容説明
楠船を操り黒潮の流れに乗ってやって来た海人族。白鳥伝説とともに移り住んだ夷たち。山深い中央構造線に沿ってたどる鍛冶神の足跡。各地に残された地名こそ弥生の時代から近世まで、名もなき人々の暮らしの記憶を伝えてきたものであった。これら小さな神々のあとを丹念にたどりながら、文書に記されないもう一つの日本の歴史を読み解く。
目次
第1章 地名の旅―黒潮のながれに沿って(日和山とアイの風;楠船と楠神 ほか)
第2章 地名と風土―中央構造線に沿って(難渋する谷のムラ;姥にちなむ地名 ほか)
第3章 地名を推理する―白鳥伝説の足跡をたずねて(こふの原;物言わぬ皇子 ほか)
第4章 固有地名と外来地名―「波照間」論争をめぐって(「波照間」の地名の由来;隼人の説話)
結語(アイヌ語の地名;「いと小さき」地名 ほか)
著者等紹介
谷川健一[タニガワケンイチ]
1921年熊本県に生まれる。東京大学文学部卒業。専攻は民俗学。現在、日本地名研究所所長
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
52
四半世紀ほど前に本書を読んだ。地名には興味津々。日本書紀などには地名説話があるが、ヤマトが古くからの呼び方を勝手に(権力で)上書きした感が強く違和感がある。昨日から読み出した児島恭子著「アイヌ語地名の歴史」に絡み日本の地名にも改めて関心を呼び起こされた。
壱萬参仟縁
28
沖縄では島のまわりをとりまく暗礁をヒシ(干瀬)と呼んでいる。ヒシの外は深い海だが、ヒシと海岸までの間は浅い海でイノウと呼ばれる(81頁)。上田市の生島足島神社は安宗郷に鎮座する式内社(103頁)。 この神社が大八洲の霊を祀る(104頁)。青崩峠の謎も面白そうだ(124頁)。 また、塩尻市の善知鳥峠の谷間、洞穴、窪地につけられる地名で、ウソ、オソ、ウツ、ウト、ウトウ。 考えるだけで、鬱になる?? 大歩危・小歩危のホケはホキ、フキと同じく、けわしい崖(137頁)。 2015/08/05
はちめ
13
言語学者にとって地名などの固有名詞は意味を持たないが、民俗学者にとって地名は宝でありその土地を生きた人々の生活の息吹を感じることができるものだ。本書においてたくさんの地名が紹介されているが、大切なのは日本列島の海岸沿いを黒潮に乗って移動した人々や中央構造線を移動経路とした人々の生活の息吹を感じることだ。とてつもなく長い年月の間、人々は獲物を獲得するためや物を運び交換するために移動を続け、それが共通する地名として定着した。そんなロマンを感じることができる。ただ、福岡市を博多市と誤認しているには問題。☆☆☆☆2021/05/09
よしじ乃輔
12
人々の暮らしと神話を民俗学と小説家の視線で考察した地名論。地名改変による由来ある地名の消滅を寂しく感じてきた自分には、各地に足を運び聞き取りし風土記や神話を基にした考察に引き込まれました。古代から近世、そして今現在。これから地名はどのように変化してゆくのでしょうか。2025/04/05
シンショ
8
地名の由来には確固たる正解はないため、それぞれが想像を働かせて自分なりの正解を探ろうとできるロマンがある。反面、自分の論調の主張が強く根拠が薄く感じられる地名本も多い。本書は黒潮や中央構造線に沿った人々の移動した経緯を一つ一つ細かく解明しながら、その地名が成立した根拠を解説している。書かれていることにどこまで信憑性があるかわからないが、そこに至るプロセスは非常に興味深かった。最後にでてきた「明宝村」は特産のハムをブランド化するため、村名が変更になった理由の一つ。2021/12/18
-
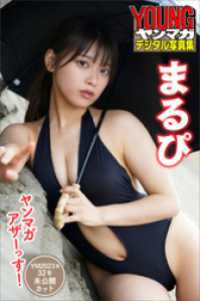
- 電子書籍
- まるぴ ヤンマガアザーっす!<YM20…
-
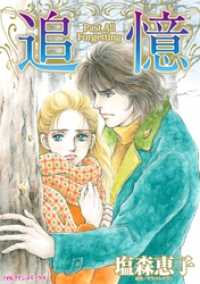
- 電子書籍
- 追憶【分冊】 10巻 ハーレクインコミ…
-

- 電子書籍
- 電波青年 26巻 Comicベガス
-
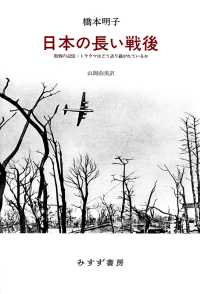
- 電子書籍
- 日本の長い戦後――敗戦の記憶・トラウマ…
-
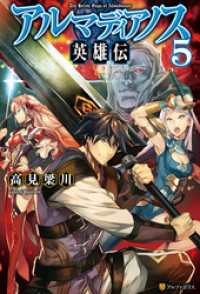
- 電子書籍
- アルマディアノス英雄伝5 アルファポリス




