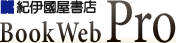 |
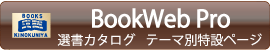 |

 出版部 図書目録
出版部 図書目録
| 新刊 | 思想・社会 | 文化・人類学 | 歴史 | 哲学 | 文学(小説・詩・伝記・エッセイ) |
| 文学(研究・批評) | 芸術 | 絵本・ビジュアル・図鑑 | 言語学・語学 | 心理学・ 精神医学 |
経済 |
| 生活・健康 | 秘書・ 実務教育 |
科学一般・ 科学哲学 |
数学 | 物理学・化学 | 生物学・医学 |
| 脳 |
| 脳 |
| 【1】 | 脳のなかの水分子―意識が創られるとき | |
|---|---|---|
 | 中田力(著)2006 46判 176頁 本体1,600円+税 | |
| 「意識は脳のなかの水から生まれる!」
全身麻酔薬はなぜ意識を抑えるのか。定説は「脂肪に溶けやすいから脳に入りやすい」。本当にそうか。1973年、著者はポーリング博士の仮説を発見。「水の結晶をつくらせるから」。「意識と水分子」の関係をひとり探究して25年。複雑系から「脳の渦理論」誕生までのドラマを活写する。
|
| 【2】 | いち・たす・いち―脳の方程式 | |
|---|---|---|
 | 中田力(著)2001 46判 154頁/口絵4頁、他図版多数 本体1,800円+税 | |
| 脳科学が久しく待っていた新しいパラダイムがここに登場。
心の物理法則、それが本書の主題。デジタルの世界では1+1が0である話から説き起こし、古典力学から複雑系の物理学まで、そのエッセンスを解説、脳の謎に迫る。最終章「統一脳理論」は圧巻、脳の中心から外へ向かう熱の流れで脳は作られ、意識も生ずるという仮説を提示する。知的興奮の書。
|
| 【3】 | 脳の方程式―ぷらす・あるふぁ | |
|---|---|---|
 | 中田力(著)2002 46判 146頁 本体1,800円+税 | |
| 脳はいかにして心を創るのか。心と意識の謎を解くには、ニューロン一辺倒では限界がある。
ニューロンの「きょうだい」であるグリア細胞がつくる脳内の新しい構造に注目、ここに「複雑系としての脳」から渦理論を樹立する。脳科学のニュー・フロンティアを拓く気迫に満ちた、刺激に満ちた意欲作。『いち・たす・いち』の姉妹篇。
|
| 【4】 | 脳 小宇宙への旅〈科学選書 11〉 | |
|---|---|---|
 | 信濃毎日新聞社(編)1991 46判 296頁 本体1,942円+税 | |
| 千数百グラムの脳という名の小宇宙の中に、人間が透けてみえてくる――私たちの精神や行動のすべてを支配する脳の謎は、いまどこまでわかったのか? 脳の正体を求めて、探検の旅に出る。コーヒーやアルコールなどの身近な話題から、脳内麻薬物質、記憶や学習、ぼけの話まで、脳に急接近する。好評を博した新聞連載を一冊に収録。
|
| 【5】 | 視覚の文法―脳が物を見る法則 | |
|---|---|---|
 | ドナルド・D.ホフマン(著) 原淳子,望月弘子(訳)2003 カラー図版多数・A5判 328頁 本体3,200円+税 | |
| 人はいかにものを見ているのか。実は、私たちは外界にあるものをそのまま視ているわけではない。脳が創造性を働かせながら、視覚世界を意味あるものとして構築するのだ。
対象物が何であるかわかる、奥行きと動きがわかる、さまざまな色を判別する、といった日常的な行為の裏側に隠されていた多数の〈法則〉を探りだし、豊かな視覚世界の謎に迫る。
|
| 【6】 | 脳のなかの倫理―脳倫理学序説 | |
|---|---|---|
 | マイケル・S.ガザニガ(著) 梶山あゆみ(訳)2006 46判 264頁 本体1,800円+税 | |
| 記憶を良くし、「賢い」脳をつくり、脳の中の思想や信条を読み取ることが現実のものとなった。脳科学の新時代における倫理と道徳をめぐる問題を、世界を代表する神経科学者が考察。
2001年より米国大統領「生命倫理評議会」のメンバーとなった著者ならではの迫真の内容で、新しい分野、「脳(神経)倫理学」、ついに日本上陸。
|
| 【7】 | 心は脳を超える―人間存在の不思議 | |
|---|---|---|
 | J.エックルス,D.ロビンソン(著) 大村裕,山河宏,雨宮一郎(訳)1989 46判 272頁 本体2,330円+税 | |
| 今世紀を代表する脳生理学者が心理学者と協力して、「脳と心」の科学の最新の成果をもとに、記憶、自我意識や霊魂といった心の本質に鋭く切りこみ、その到達点を平易に説く。「脳と心」の根本問題をめぐる到達点から、現代社会をおおう様々な哲学的、宗教的、イデオロギー的迷信を徹底的に批判して、人間の本質をめぐる新しい地平を提案する。
|
| 【8】 | 手と脳〈増補新装版〉 | |
|---|---|---|
 | 久保田競(著)2010 46判 264頁 本体2,000円+税 | |
| 手をうまく使えない子どもが増えている。はたして手の器用さは、どのように発達するのだろうか? 本書では、感覚器官・運動器官としての手の機能や、手の進化、利き手の研究などを脳とのつながりで詳しく解説した。手を創造的に使うことが脳の働きを高めることを示した1982年刊行の著者代表作に、脳科学の最新知見をアップデートした増補新装版。
|
| 【9】 | 言語と脳〈叢書・脳を考える〉 | |
|---|---|---|
 | 杉下守弘(著)1985 46判 192頁 本体1,700円+税 | |
| 人間は言葉を自由自在に使いこなすことで豊かな文化を創造してきた。しかし言葉と一口に言っても、その中には話す、聞いて理解する、読み書きなど様々な複雑な働きがある。一体脳はいかなる仕組でこうした言語活動を操っているのだろうか。本書は、言語と脳をめぐる様々な興味深い知見を一般の人にもわかるようにやさしく解説した本である。
|
| 【10】 | 脳の老化とぼけ〈叢書・脳を考える〉 | |
|---|---|---|
 | 朝長正徳(著)1988 46判 276頁 本体2,000円+税 | |
| 年をとると、脳の中で何が変わるか。ぼけは、脳の中のいかなる現象と対応しているか。ぼけはなぜ起るのか。本書は、脳の老化とそれと表裏の関係にあるぼけの二つに焦点をしぼり、幅広い視野からかつ深く掘り下げて解説する。脳の老化をめぐる知見からぼけの正体にどこまで迫れたかをよく分かるように解説し、その予防と治療の将来的展望を見通す。
|
| 【11】 | ミラーニューロン | |
|---|---|---|
 | ジャコモ・リゾラッティ,コラド・シニガリア(著) 柴田裕之(訳)茂木健一郎(監修)2009 46判 256頁 本体2,300円+税 | |
| 1990年代初頭、自分がある行為をしているときも他者の行為を見ているときも、同様に活性化する脳の神経細胞が見つかった。鏡のように他者の行為を映すことから“ミラーニューロン”と命名されたこの発見は、近年の脳科学最大のトピックとなり、学習や模倣、情動の伝播・共有などを説明する鍵として注目を集める。その秘める可能性を発見者自らが科学的に解き明かす。
|
| 【12】 | ユーザーイリュージョン―意識という幻想 | |
|---|---|---|
 | トール・ノーレットランダーシュ(著) 柴田裕之(訳)2002 46判 568頁 本体4,200円+税 | |
| 意識は0.5秒遅れてやってくる。デカルトの「我思う、ゆえに我あり」という意識の黄金律は幻想に過ぎなかった。
本書は、数学、物理学、情報科学、実験心理学の成果から、たとえばベイトソン、マトゥーラーナとヴァレーラの思想に至るまでの〈知〉を総動員して、意識という存在の欺瞞性を暴いた力作。原書は母国デンマークのベストセラー。
|