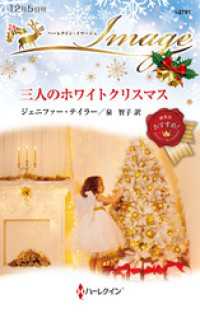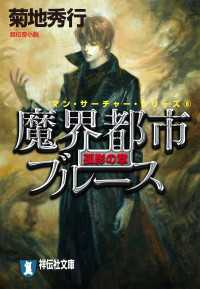内容説明
戦争体験を取り上げた作家・詩人は数多い.石原吉郎は,シベリアのラーゲリで不信と連帯,密告と報復,死者と生者の交錯する極限を生きた.その体験を自己への凝視,告発と断念,絶望と祈り,沈黙と発語の拮抗する内面における,硬質にして静謐なる言葉で表現した.石原吉郎の散文を精選して,その文業の核心をテーマごとにまとめる.
目次
Ⅰ シベリヤ──フランクルに導かれて
確認されない死のなかで──強制収容所における一人の死
オギーダ
強制された日常から
体刑と自己否定
無感動の現場から
失語と沈黙のあいだ
「耳鳴りのうた」について・1
〈体験〉そのものの体験
Ⅱ 詩の発想
沈黙と失語
望郷と海
海を流れる河
俳句と〈ものがたり〉について
私の部屋には机がない──第一行をどう書くか
辞書をひるがえす風
私と古典──北條民雄との出会い
自作自解
断念と詩
「フェルナンデス」について
「全盲」について
Ⅲ 聖書と信仰
『邂逅』について
半刻のあいだの静けさ──わたしの聖句
信仰とことば
聖書とことば
詩と信仰と断念と
絶望への自由とその断念──「伝道の書」の詩的詠嘆
十字路
終末をまちのぞむ姿勢
虜囚の日
Ⅳ ユーモア
私の酒
日記1(一九七二年)
日記2(一九七四年)
偉大なユーモア
遺書は書かない
略年譜
解説……柴崎聰
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
102
戦争を思う8月、何十年振りかで石原さんの文章に触れた。私はこの人の硬く理知的な文体が好きだ。石原氏のシベリア抑留体験のエッセイは、フランクル氏の「夜と霧」とよく比較される。告発の姿勢や被害者意識を排した深い内省的考察は共通だが、希望の光を求める「夜と霧」に対し、石原氏の体験には極限状態の闇が露わになる。「失語」という、この詩人の最も重要な言葉である。信仰が救いになったかと問われて「信仰が、危機に即応するような形で人間を救うものでないと痛切に教えられた場所こそシベリアであった」というキリスト者の言葉も重い。2023/08/30
ふるい
16
ジェノサイド。人、が一人ひとり峻別されぬ死。この不条理が強制的に日常とされる地獄と、抜け出した先に待っていた失語。生きるための断念と信仰、試作について、非常に真に迫るものがあった。石原吉郎の詩を読んでみよう、とおもった。2019/07/08
踊る猫
14
V・E・フランクル『夜と霧』と同じくらい、死が身近にあったシベリア抑留体験という過酷な体験をなんの自己憐憫もなく冷徹に自己を見つめて描き切ったエッセイが集成されている一冊。苦しみはしかし抑留中ももちろんだが、解放されたあとにも残るという(今の言葉で言えば PTSD だろう)指摘が興味深い。来年は図らずも没後四十年となるわけだが、フランクルの書物と同じくこの書物は戦争を忘れないための書物として読み継がれるべきではないかと思う。だがこれ以上深いことは書けそうにない。いずれ読み返す日が来るのだろうと考えてしまう2016/12/10
Bartleby
11
詩人・石原吉郎が壮絶なシベリアの収容所体験、そして失語体験を経て紡ぎ出す言葉のむこうには、言われなかった膨大な言葉がある。一方、じっさいに書かれた言葉は、どれほどの労力と苦痛と記憶との軋みから搾り出されたものか。詩が混乱状態に適した形式だという指摘は石原吉郎という人にしかできないものだ。なまじっかには読めない。読者に一個の人間としての応答責任を強いずにはいない。2022/09/07
芋煮うどん
3
名前についての考察が胸に迫った。どこの収容所の壁にも名前が刻まれている。最後に残したいもの(残せるもの)は名前なのだ、と。すると無名兵士の墓と呼ばれるものの残酷さ、よ。2025/02/19


![しょせん他人事ですから ~とある弁護士の本音の仕事~[ばら売り]第51話[黒蜜] 黒蜜](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-2318740.jpg)