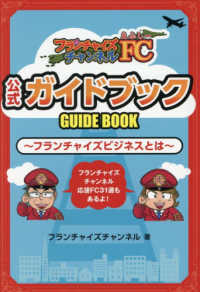内容説明
東京・下落合、戦火を逃れた邸宅に集められた4人の女性。
GHQの一声で、彼女たちの人生を変えるハチャメチャな同居生活が始まった。
1946年11月、日本民主化政策の成果を焦るGHQがはじめた “民主主義のレッスン”。いやいや教師役を引き受けた日系2世のリュウ、地位と邸宅を守るためこの実験に協力した仁藤子爵夫人、生徒として選ばれた個性豊かな4人の女性――それぞれの思惑が交錯する中、風変わりな授業が幕を開ける。希望と不安、そして企み……。波乱の展開が感情を揺さぶる、今年一番の超大作!
【電子版おまけ】
手書きメッセージ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
starbro
233
森 絵都は、新作をコンスタントに読んでいる作家です。本書は、著者6年ぶりの長編小説、戦後民主主義レッスン譚でした。GHQが日本に民主主義を定着させるにあたって、本書の様なエピソードがあったのでしょうか❓ 興味深く、面白く読みましたが、少し冗長な気がしました。 https://kadobun.jp/special/mori-eto/democracy-no-iroha/2025/11/05
旅するランナー
208
敗戦国日本へのGHQによる民主化政策。日系通訳官サクラギは4人の日本人女性への民主主義教育役に任命される。6カ月に渡るドタバタと最後にまさかのどんでん返し。強烈なキャラたちに大笑いしながら、民主主義の真髄も見えてくる傑作です。2025/11/12
しんたろー
148
戦後間もなく、GHQにより民主主義を啓蒙する実験で集められた若い女性生徒たちと先生の日系二世・サクラギが半年間を過ごす物語。「小難しい話?」と思っていたが、著者らしい巧いキャラクター描き分け&豊かな心情描写と目に浮かぶような情景描写で惹き込まれた。サクラギと一緒に喜んだり悩んだりしつつ、読む手が止まらなかった。途中の一章では視点が代わり、ある裏側が解き明かされるのも面白かった。人生や民主主義などを考えさせられながら、爽やかな感動に包まれた。NHKで実写化して欲しいし、今年のマイベスト10入り決定の佳作👍2025/12/16
katsukatsu
118
GHQの命により日本人女性4人をモデルにして、民主主義教育の実験が半年間にわたって行われました。元華族、優等生の真島美央子、静岡の農家の娘、近藤孝子、おしゃれに余念のない沼田吉乃、ベールに包まれた宮下ヤエ。4人の先生、日系人のリュウサクラギは授業を始めますが、4人からは何の反応もなく……。そこに家を提供する仁藤夫人が傍若無人にかき回し、メイドのクニにも何かありそう……。飽きることもなく話が展開し読者の心を離しません。民主主義を単なる机の上の飾り物にせず、一人一人の人生の中に落とし込んだこの一冊に拍手です。2025/11/02
buchipanda3
113
戦後、間もない頃が舞台。デモクラシーという堅めのお題となっているが、当時の女性たちの人間味溢れる群像劇として面白く読めた。GHQ主導の民主主義のレッスンを受ける彼女らは同じ年頃でも、みな違う戦争体験をしていて想いも違う。それだけに教師役のサクラギも四苦八苦。でも徐々に、というよくある展開かと思ったがそればかりではなかった。答えは教えて貰うばかりではなく、自分の物語を紡ぐ中で見つけていくものなのだなと。オホホおばさんにマネカッサー、何より和太鼓の師匠と脇役もドラマ向き。あとヤエ太鼓には二度愉しませて貰った。2025/11/12
-
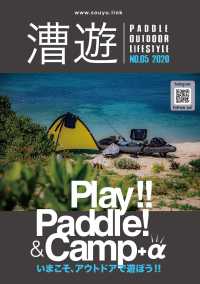
- 電子書籍
- 漕遊 -SOUYU- #05 MIX …
-
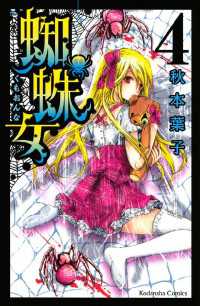
- 電子書籍
- 蜘蛛女(4)