内容説明
同時代の朝鮮半島や中国東北部の考古資料を詳細に比較し、日本史最大の仮説の一つ「騎馬民族征服王朝説」の再考に挑む。
もし仮に、朝鮮半島に「騎馬民族征服王朝」が存在したのであれば、当然、日本列島の「騎馬民族説」の問題にも直接的な影響を与えるにもかかわらず、日本国内においてこの韓国の「騎馬民族説」を真正面から取り扱った研究は、皆無であったといってよい。そこには日本史、朝鮮史(韓国史)、あるいは日本考古学、朝鮮考古学(韓国考古学)というそれぞれの枠組みを越えて議論することに対する躊ちゅう躇ちょや遠慮があったのかもしれない。しかし、あとで詳しくみるように「騎馬文化が来た」という点では、朝鮮半島もまた日本列島と同じであったことをふまえれば、両地域における騎馬文化の出現はそういった既存の一国史の枠組みを越えて、東北アジアを一つの単位とする一連のプロセスとして理解してみる必要があるのではないだろうか。いまからおよそ一六〇〇年前にユーラシア大陸の東端で起こった騎馬文化東とう漸ぜんのメカニズムは、かつて江上氏が「ミッシング・リンク」とした東北アジア各地から、陸続と出土し続けている考古資料をもとに再解釈する必要がある。本書の議論を通じて、「騎馬民族説」に代わる新たな騎馬文化伝播モデルの提示を目指したい。(本文より抜粋)
【著者】
諫早直人
京都大学大学院文学研究科歴史文化学専攻考古学専修博士後期課程修了。博士(文学)。
日本学術振興会特別研究員PD(京都大学人文科学研究所)を経て、現在、独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所都城発掘調査部研究員。
主な論著に「古代東北アジアにおける馬具の製作年代」(『史林』第91巻第4号、2008年)、「東アジアにおける鉄製輪鐙の出現」(『比較考古学の新地平』、同成社、2010年)、「日本列島初期の轡の技術と系譜」(『考古学研究』第56巻第4号、2010年)などがある。(2014年現在)
目次
はじめに――「騎馬民族説」の呪縛
一 騎馬文化の成立・拡散と韓国の「騎馬民族説」
1 「騎馬民族」とは?
2 騎馬遊牧社会の成立と騎馬文化の拡散
3 騎馬文化出現以前の朝鮮半島
4 伝播した「騎馬民族説」――韓国の「騎馬民族説」
5 馬具からみた朝鮮半島における騎馬文化の導入
二 古代東北アジアにおける装飾騎馬文化の成立と拡散
1 慕容鮮卑における装飾騎馬文化の成立
2 高句麗における受容と展開
3 新羅における受容と展開
4 加耶における受容と展開
5 百済における受容と展開
三 日本列島における騎馬文化の受容と展開
1 倭における騎馬文化の受容
2 倭における装飾馬具生産の開始
おわりに――なぜ騎馬文化は海を渡ったのか
注・参考文献
感想・レビュー
-
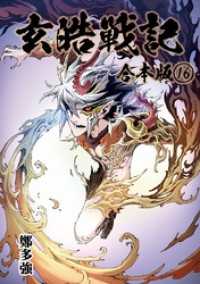
- 電子書籍
- 玄皓戦記 合本版 16 漫画パンゲア
-
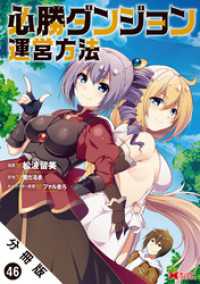
- 電子書籍
- 必勝ダンジョン運営方法(コミック) 分…
-

- 電子書籍
- 盾の勇者の成り上がり【分冊版】 101…
-

- 電子書籍
- お転婆娘と顔無しの男【単話版】(114…





