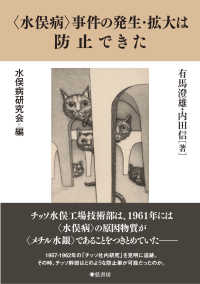内容説明
十九世紀末,ブラジル北東部の最貧地帯に現れたキリストの再来をおもわせるコンセリェイロ(「教えを説く人」)およびその使徒たちと,彼らを殲滅しようとする中央政府軍の死闘を描く,円熟の巨篇.ブラジルで実際に起きた「カヌードスの反乱」をモチーフにした,バルガス=リョサ畢生の超大作.(全二冊)
目次
第一部
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ
第二部
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
第三部
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
〔下巻目次〕
第三部(承前)
Ⅵ/Ⅶ
第四部
Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ/Ⅵ
解説(旦敬介)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
藤月はな(灯れ松明の火)
54
貧しさが人を損ね、弱き者が更に弱き者を虐げる事で一時的な心の安寧を得ている19世紀ブラジル。そんな不毛な世の中にイエス・キリストの再来かと思われるコンセリェイロが現れた。神を信仰しようにもその信仰も場も廃れている事に気づいた彼は行動を開始していくが、それは周囲を感化していく。だが、危険視する中央政府軍は彼らに対抗するための準備を始め・・・。コンセリェイロの信仰者となった人々の人生だけでも面白いが、バークニン支持者の外国人勢力もコンセリェイロに絡み合うのが不安要素か。この戦いは泥沼化するのだろうか。2025/09/01
sayan
26
「終末」は支えの臨界を示す。カヌードスの民が国家の外に共同体を築いたのに対しガザの人々はその外部での生を強制させられる。国家と人間、双方の安全保障が崩れ、唯一、信仰と関係性のなかで生が保たれる。信仰はなお、生を支える力たりうるのか。リヴァイアサンの契約が崩れた後、人間は内なる保障を求め、祈り・記憶・ケアが精神のインフラとして生の秩序を紡ぐ。破壊は国や制度のみならず人そのものに及ぶ。この現実は国家が支える能力を失った世界を可視化する。上巻は、国家が保護しえない時代の内的安全保障を問い、ガザの現実に響きあう。2025/10/12
塩崎ツトム
25
すでに単行本で読んでいるが、再読。「世の中には哲学ではわからぬことがあるのだ、ホレイショ」。しかし賢いもの、富めるものは、説教師コンセイェロと、彼の元に集い、救済を求める人々を理解できない。だから愚者のスタンビートか、あるいは背後にある陰謀しか思いつかない。いや、陰謀論というのは宗教的結束の下にあるカヌードスの民もそうだが、バイーアの天地しか知らぬものの「真実」と、富めるものの事実では重みが違う。狭い天地に閉じ込められ、死と恐怖が迫りくる人々を、無知蒙昧と指さす高邁な奴らに災いあれ。2025/11/08
穀雨
8
同じ作者による『楽園への道』がよかったので。全2巻、計1000ページあまりの大作のようだが、文体が簡潔で非常に読みやすく、かつ視点が転々とするメリハリのついた構成になっているのですらすら読むことができる。たまたま数ヶ月前にブラジル史に関する本を読んでいたこともあり、とても興味深かった。風采の上がらない新聞記者やサーカスの一座など、脇役たちもそれぞれいい味を出している。2025/11/01
Decoy
4
ようやく上巻を読了。終始不穏な空気が漂っており、緊張を強いられながら読む。下巻も楽しみ。 岩波文庫で海外文学を読むと感じることが多いが、どうしてこのような登場人物が多く、場面転換が頻繁な作品で、主要登場人物紹介と、舞台となる場所の地図と、時代や地域ならではの用語解説を、別ページに設けてくれないのだろう…? あれば、よりスムーズに読めて理解が深まるだろうに。とても残念。2025/12/23