内容説明
子ども福祉臨床の目的は子どもの保護と健全育成です。与えられた枠組みや理論にただ縛られるのではなく、対応してもよいのではないだろうか。児童相談所で約30年の勤務経験のある著者が、具体的事柄とともに子ども家庭支援の現場において大切なことを綴る。
目次
はじめに
第1章 子ども家庭への支援業務~福祉臨床現場ならではの視点と協働~
(1)事例のアセスメントが一番
ジェノグラムを描いて考える
視野を広げる(5歳のランちゃんの事例)
仮説を立てる(ランちゃんの事例への視点と仮説例)
仮説を立てるときの留意点(個人的特徴と原因論・人の法則性と非法則性・先入観から自由になる・支援者の生身性への配慮)
(2)子ども福祉臨床ならではのトリートメント
「世話されること」と「保護者のよい顔」
子どものことは決めつけやすい
多様性と「ふつう」
マイナスのストーリーの書き換え
落とし穴や悪循環
(3)コミュニティに向けた業務
児童相談所業務の理にかなっているところ
子ども福祉臨床の特徴と大切にしたいこと
心理職の業務をとおして現場を考える
資格と専門性
この時代背景の中で維持したい専門的意識
第2章 発達相談場面での保護者への対応~その子の一番の専門家は保護者~
(1)来談した保護者の思い
一般的に想像する
発達検査課題を実施する場合
(2)支援をめざした配慮
総論として(来所と日々の子育てへのねぎらい・その子の一番の専門家は保護者・保護者をやっつけたいのではない・よかれと思ってした助言・より丁寧なコミュニケーション・背景への思いやり)
少しだけ各論的に(検査結果をどう伝えるか・子どもとの遊びの具体例・問題意識がなかったり自分を責める保護者・子どもに感情的に接してしまう保護者)
チームアプローチ
第3章 子ども虐待による死亡事例から考える~収束的に拡散的に~
(1)私と子ども虐待死
(2)私の体験
足元での事件の際に考えたこと
間接的にふれた虐待死亡例(加害者の被害者的側面と社会復帰・担当者の「心のケア」・児童虐待重大事件に関する著作を読んで)
(3)虐待死について少しだけ広げて考える
自殺したAくんとBさん
虐待事例と「距離感」
(4)あらためて子ども家庭支援に必要なもの
事例検討の重要さ
検証に関する異なる視点
第4章 要保護児童対策地域協議会の充実のために~「狭く深く」と「広く浅く」~
(1)要対協とは
協議の対象
三層構造
守秘義務
(2)虐待を疑ったときの初期対応
(3)要対協に関して気になる点
個別ケース検討会議と実務者会議との関係
要対協について検討する際のテーマ
第5章 子どもへの対応をめぐる事態にかかわる~後手から先手に~
(1)世の中の動きへの対応
感情労働の危機
虐待防止と健全育成
その行為は適切か不適切か(明らかに不適切な場合・判断がむずかしい事柄・不適切かもしれないけれど)
後手から先手に(適切か不適切かではなく・身近なことは身近なところで)
(2)「対応のバリエーション」という取り組みの例
勉強会の紹介
職場研修後の私からの手紙
第6章 子ども福祉臨床の現場への支援~「仕方がない」ではないかもしれない~
(1)子ども虐待防止関連の事柄
子ども虐待に関して考えたいこと
虐待事例を見聞きして考えたこと(どこまでの「判断」が許されるか・職権による一時保護の謝罪・夫婦喧嘩をしてはだめなのか)
(2)子どものように大人も守る
等身大のすすめ
大切な筋道
自分自身と業務は別か
フリーハンドの力
関連書籍
おわりに
-

- 電子書籍
- あなたのハニーは転生から帰ってきた【タ…
-
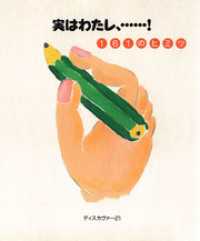
- 電子書籍
- 実は私……!161のヒミツ
-
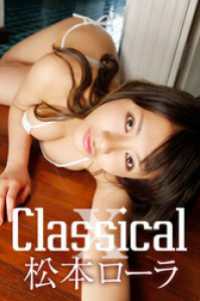
- 電子書籍
- 松本ローラ Classical X ギ…
-
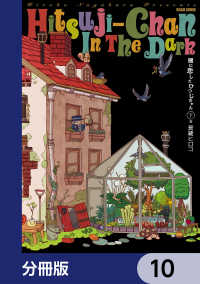
- 電子書籍
- 闇に恋したひつじちゃん【分冊版】 10…
-
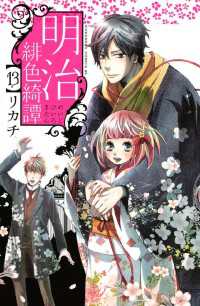
- 電子書籍
- 明治緋色綺譚(13)



