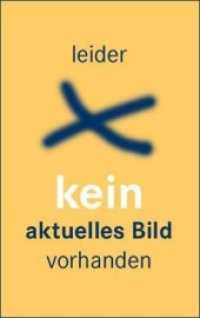内容説明
「モノづくりのための学問」を志す人にとって,無機化学は本質的に重要な分野である。本書は,先人たちが開拓し,まとめあげた元素についての知識を「暗記」ではなく,「理解」することで学ぶことを目的としている。
目次
1. 原子
1.1 原子とは
1.1.1 原子を構成する粒子
1.1.2 元素の存在状態と成因
1.1.3 原子と元素の違い
1.2 元素の電子状態
1.2.1 水素原子とボーアモデル
1.2.2 量子力学(量子化学)入門
1.2.3 原子軌道
1.2.4 多電子原子の構造
1.3 イオン化エネルギーと電子親和力
1.4 有効核電荷
1.5 電気陰性度
まとめ
章末問題
2. 周期表
2.1 周期表とは
2.1.1 現代の周期表,周期と族
2.1.2 周期表とブロック分類
2.2 周期表と元素の性質
2.2.1 原子半径
2.2.2 イオン半径
2.2.3 周期表と原子,イオンの大きさ
2.2.4 ランタニド(ランタノイド)収縮
2.2.5 周期表とイオン化エネルギー,電子親和力,電気陰性度
2.3 周期表と元素の存在状態
まとめ
章末問題
3. 固体の形成
3.1 凝集力
3.2 共有結合と分子性化合物
3.3 金属結合と金属結晶
3.4 最密充填構造
3.5 イオン結合
3.5.1 イオン結晶の構造
3.5.2 イオン半径比と配位数
3.6 格子エンタルピー
3.6.1 ポテンシャルエネルギー
3.6.2 ボルン・ハーバーサイクル
3.7 分子間力
3.8 水素結合
まとめ
章末問題
4. 分子
4.1 共有結合
4.1.1 ルイス構造とローンペア
4.1.2 オクテット則
4.1.3 2中心2電子結合と電子不足結合
4.1.4 形式電荷・共鳴
4.1.5 酸化数
4.2 分子軌道法入門
4.2.1 原子軌道と分子軌道
4.2.2 水素分子とヘリウム分子イオン
4.2.3 結合次数
4.2.4 多電子原子の分子とさまざまな軌道
4.2.5 フロンティア軌道
4.2.6 等核二原子分子1:フッ素分子
4.2.7 等核二原子分子2:酸素分子と三重項状態
4.2.8 等核二原子分子3:窒素分子
4.2.9 異核二原子分子1:フッ化水素
4.2.10 異核二原子分子2:一酸化炭素
4.2.11 混成軌道
4.2.12 不飽和結合
4.2.13 バンド理論
4.2.14 金属(導体)・半導体・絶縁体
4.2.15 量子ドット
まとめ
章末問題
5. 典型元素
5.1 元素の各論
5.2 水素
5.2.1 水素の同位体
5.2.2 水素分子と原子核のスピン
5.2.3 水素原子の電子配置と化学的性質
5.2.4 水素の化合物1:塩類似水素化物
5.2.5 水素の化合物2:分子性水素化物
5.2.6 水素の化合物3:金属類似水素化物
5.3 希ガス(貴ガス)
5.4 アルカリ金属
5.4.1 アルカリ金属単体の性質
5.4.2 アルカリ金属単体の製法
5.4.3 アルカリ金属のイオン化傾向
5.4.4 アルカリ金属のイオンの大きさと水和半径
5.4.5 アルカリ金属のアンモニアへの溶解
5.4.6 アルカリ金属イオンを有機溶媒に溶かす方法
5.4.7 アルカリ金属の酸化物とその他の化合物
5.5 アルカリ土類金属(第2族元素)
5.5.1 アルカリ土類金属(第2族元素)単体の一般的な性質
5.5.2 対角関係:アルカリ金属元素,第2族元素,第13族元素の類似性
5.5.3 第2族元素の化合物
5.6 ホウ素とアルミニウム
5.6.1 ホウ素の同位体
5.6.2 ホウ素の化学的性質
5.6.3 ボランの構造
5.6.4 ホウ素のその他の化合物
5.6.5 アルミニウム
5.6.6 アルミニウム単体の製法
5.6.7 アルミニウムの化合物
5.7 炭素とケイ素
5.7.1 炭素の同位体
5.7.2 炭素の単体と同素体
5.7.3 炭素の化合物
5.7.4 ケイ素の単体と製法
5.7.5 ケイ素の化合物
5.8 窒素とリン
5.8.1 窒素の単体と化合物
5.8.2 リンの単体と化合物
5.8.3 窒素またはリンを含む錯体
5.9 酸素と硫黄
5.9.1 酸素の単体とイオン
5.9.2 活性酸素と過酸化水素の製法
5.9.3 硫黄の単体
5.9.4 硫黄の化合物の例
5.10 ハロゲン
5.10.1 ハロゲンの単体
5.10.2 ハロゲン単体の製法
5.10.3 フッ素の特徴
5.11 オキソ酸
5.11.1 周期表とオキソ酸
5.11.2 おもな典型元素のオキソ酸
5.11.3 ハロゲンのオキソ酸
まとめ
章末問題
6. 遷移元素と錯体化学
6.1 遷移元素とは
6.2 配位化合物
6.2.1 配位結合
6.2.2 錯体の命名法
6.2.3 錯体の構造
6.3 原子価結合理論と錯体の磁性
6.4 結晶場理論
6.5 配位子場理論
6.6 金属錯体の電子状態と分光学
6.6.1 金属錯体の色
6.6.2 分光化学系列
6.7 金属錯体の安定性と反応
6.8 遷移金属元素の各論
6.8.1 スカンジウム・イットリウム
6.8.2 チタン・ジルコニウム・ハフニウム
6.8.3 バナジウム・ニオブ・タンタル
6.8.4 クロム・モリブデン・タングステン
6.8.5 マンガン・テクネチウム・レニウム
6.8.6 鉄・コバルト・ニッケル
6.8.7 白金族元素
6.8.8 銅・銀・金
6.8.9 ランタノイド
まとめ
章末問題
7. 固体化学
7.1 固体化学とは:結晶について
7.2 無機化合物の結晶構造
7.2.1 イオンの最密充填と配位多面体
7.2.2 晶系と単位格子,ブラベ格子
7.2.3 代表的な結晶構造
7.3 結晶によるX線回折
7.3.1 X線回折についての基礎知識
7.3.2 空間群と消滅則
7.4 固体の電気伝導
7.5 固体の熱伝導
7.6 誘電体と関連する物性
7.7 格子欠陥
7.8 ナノ材料
まとめ
章末問題
8. 溶液化学
8.1 溶液化学とは
8.2 理想溶液と非理想溶液
8.3 酸と塩基
8.3.1 酸と塩基の定義
8.3.2 pHとpK_a
8.3.3 HASB
8.3.4 緩衝溶液
8.3.5 水和
8.3.6 加水分解
8.4 酸化還元
8.4.1 酸化剤と還元剤
8.4.2 標準酸化還元電位
まとめ
章末問題
9. 核化学
9.1 核化学とは
9.2 自然界の力と放射性同位体
9.3 放射線と放射能:関係する物理量
9.4 放射性同位体の半減期
9.5 アクチノイド
9.6 原子力発電の概要
9.7 核医学の概要
まとめ
章末問題
10. 生物無機化学
10.1 生物無機化学とは
10.2 酸素
10.2.1 酸素と活性酸素
10.2.2 活性酸素の除去と生体防御
10.2.3 窒素酸化物
10.3 アルカリ金属
10.4 第2族元素(アルカリ土類金属)
10.5 金属錯体
10.5.1 金属錯体と酵素
10.5.2 血液における酸素運搬
10.5.3 金属錯体と光合成
10.6 金属が示す毒性
10.6.1 重金属の毒性
10.6.2 金属発がん
10.7 無機物質の薬理作用の例:抗がん剤
まとめ
章末問題
付録
索引
-
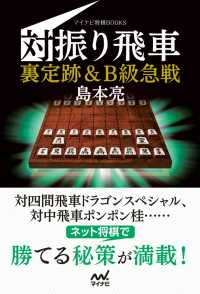
- 電子書籍
- 対振り飛車 裏定跡&B級急戦 マイナビ…