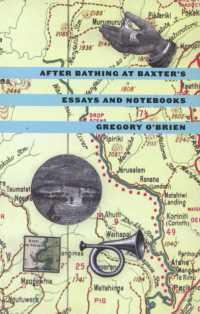- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
昨今混迷化するパレスチナ情勢を受け、パレスチナに暮らしている人々や故郷を追われた人々の現状、イスラエル国内の世論等、一元的な対立構造ではない多様な視点からパレスチナ問題がわかる別冊エリア・スタディーズが誕生。どのようにガザを支援しているのか、パレスチナ国内のカルチャーや商業活動等、現地の日常も活写したパレスチナ理解の決定版。
目次
序章[鈴木啓之]
パレスチナ/イスラエル全景
パレスチナ難民の移動と現在の居住地
Ⅰ ガザ情勢から見るパレスチナ/イスラエル
第1章 ガザの風景――潮風が香る街道の町[鈴木啓之]
第2章 「封鎖」以前のガザ――うち続く反開発と人びとのスムード[藤屋リカ]
第3章 封鎖下の生活――若者の志を打ち砕く現実[手島正之]
第4章 国際社会とガザ――ガザの人びとと国際人道支援[吉田美紀]
第5章 ハマースとガザ――抵抗と統治のはざま[山本健介]
第6章 イスラームと政治――その規範的観点と歴史的文脈[ハディ・ハーニ]
第7章 パレスチナと国際人道法――継続する占領と集団罰[島本奈央]
第8章 イスラエルと虐殺の記憶――過剰防衛の歴史社会的背景[鶴見太郎]
コラム1 レバノンの政治運動とパレスチナ[早川英明]
コラム2 イスラエル南部のキブツ[宇田川彩]
コラム3 イスラエル軍の徴兵制[澤口右樹]
Ⅱ 日常のパレスチナ/イスラエル
第9章 東エルサレムと人びとの日常――支配の侵食に抗うこと[南部真喜子]
第10章 西エルサレムの人びとと生活――弦の橋が映し出す街の姿[屋山久美子]
第11章 イスラエル国籍のパレスチナ人――「1948年のアラブ人」の日常[雨雲]
第12章 ヨルダン川西岸での人びとの生活――入植地、分離壁、検問所の存在とその影響、生活する人たちの思い[福神遥]
第13章 テルアビブ――世俗的首都の「多様性」[宇田川彩]
第14章 終わりのみえない難民生活――レバノン在住のパレスチナ人[児玉恵美]
第15章 日常の中のナクバ/ナクバの中の日常――歴史の抹消にあらがう人びとの暮らし[金城美幸]
第16章 パレスチナをめぐるもうひとつの争点――LGBTQの権利について[保井啓志]
第17章 入植者植民地主義とパレスチナの解放――地中海からヨルダン川まで[今野泰三]
コラム4 教育と日常[飛田麻也香]
コラム5 「非日常」の抵抗――パレスチナと演劇[渡辺真帆]
コラム6 日常という抵抗、文学という抵抗[佐藤まな]
Ⅲ 日本や世界との関わり
第18章 UNRWAの活動と日本――70年続いてきた支援[清田明宏・角幸康]
第19章 国際NGOとパレスチナ社会――人びとの暮らしに寄り添って[大澤みずほ]
第20章 ガザの商品を扱う――フェアトレードの試み[山田しらべ]
第21章 パレスチナ・ガザ地区での医療援助――国境なき医師団の活動を通して見た紛争地医療の課題[白根麻衣子]
第22章 国際協力NGOとアドボカシー活動――日本外交への提言[並木麻衣]
第23章 パレスチナ勤務の経験から――緊急人道支援から大規模産業復興プロジェクトまで[大久保武]
第24章 帝国主義とパレスチナ・ディアスポラ――大英帝国からアメリカ帝国へ[イヤース・サリーム]
コラム7 14歳のパレスチナ難民が日本に伝えたこと[新田朝子・石黒朝香]
コラム8 転換期にあるBDS運動 ICJ暫定措置命令と対イスラエル武器禁輸[役重善洋]
コラム9 『ガザ素顔の日常』上映と映画の力[関根健次]
パレスチナ/イスラエルを知るための参考資料
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
藤月はな(灯れ松明の火)
かおりん
鯖
瀬希瑞 世季子
英
-

- 電子書籍
- 結婚しない娘は用無しですか? 17 マ…
-
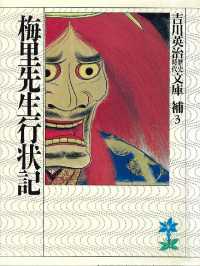
- 電子書籍
- 梅里先生行状記 吉川英治歴史時代文庫