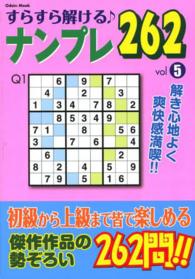内容説明
双六、丁半、花札、富くじ……。賭博は古代より日本社会に存在し、貴族の社交の嗜みとして、武士の陣中の慰みとして、また庶民のエネルギー発散のはけ口として、あらゆる階層の人々を虜にしてきた。本書では、現在もなお残る定番の賭け事から、忘れ去られた昔の流行物、果てはイカサマの技術に至るまでの数々を紙上に再現。権力による禁圧の裏で新たな賭博が次々と生み出されてきた様を、豊富な図版とともに活写する。賭博という人間存在を語るうえで不可欠な現象に着目することで、時代の性格や民衆の感情の新たな側面が見えてくる。類書のないギャンブル日本史。解説 檜垣立哉
目次
第一章 賭博史話/1 賭博の起源/2 古代の賭博/3 乾坤一擲の思想/4 江戸時代の賭博/5 賭博の定義と分類/第二章 近世賭博要覧/1 開帳/2 江戸サイコロ賭博/3 江戸カルタ賭博/4 花合わせ(花札)/5 富突/6 文芸賭博/7 ゼニとクジ/8 弓矢賭博/9 動物賭博/10 雑賭博/11 手目(詐欺)賭博/第三章 明治賭博史/1 変革期の賭博/2 競馬/3 チーハー/4 明治の富くじ/5 花札(弄花)/6 トランプ・骨牌/7 撞球(玉突き)/8 天災・チイッパ/9 明治の詐欺賭博/10 〈社会〉賭博/第四章 現代賭博論/1 大正昭和の賭博/2 競馬・競輪・パチンコ/3 現代の富くじ/あとがき/主要参考文献/解説(檜垣立哉)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nonpono
59
わたしにはギャンブラーな父と弟がいる。後楽園場外で一日を過ごし、大井のナイター競馬に行ったり、帰りの電車代まで賭けて家まで歩いたり、車に乗っていると通行人を見つけ、右に曲がるか、左に曲がるかまで賭ける。レベルが違う。ギャンブルって何だろうと本書を手に取る。文献的には「日本書紀」に685年から登場。厳しく規制すればするほど燃え上がる民衆、新たなギャンブルの登場。まさに、「禁ぜられては逼塞し、また盛り返し」なのである。ギャンブルから見る日本の歴史が面白かった。蛇足だが、弟は副業でネットで競輪の予想をしている。2025/05/30
けっと
3
日本の古代から現代にかけてどのような賭博が存在したのか幅広く紹介しています。興味深いのは万葉集で「一伏三起」の文字列を「コロ」と読む理由は昔の賽の出目のひとつである1枚表・3枚裏の「コロ」に由来しているから、という話です。昭和になって朝鮮語に同じ音の単語があったことがきっかけで判明したらしく、謎の解明には思いもよらない分野の知見が役に立つことの良い例だと思います。他にも江戸時代のカルタやサイコロ、くじ引きについて遊び方を(そして賭け方も)細かく記載しており、中には確率の良い問題になりそうな事例もあります。2025/02/16
gibbelin
2
追悼読書。チョイスは偶々…2025/09/17
Go Extreme
2
賭博の起源:古代祭祀 信仰と遊戯 中国影響 双六 賽 博奕道具 神事占い 中世賭博:武士と賭博 闘犬 闘牛 将棋囲碁 社交要素 情報交換 戦略競技 江戸賭博:花札 丁半 庶民娯楽 商業化 賭博場規制 違法賭博 非公式賭博 明治賭博:競馬導入 近代化 公営賭博 法整備 立身出世手段 社会的交流 現代賭博:公営ギャンブル 競馬 宝くじ オンライン賭博 依存症問題 カジノ 社会影響:社交手段 経済活動 社会問題 倫理観変遷 国家規制 文化的影響2025/03/18
Taichi Ichikawa
1
取材用2025/08/16
-

- 電子書籍
- 漫画パチスロパニック7 2021年02…