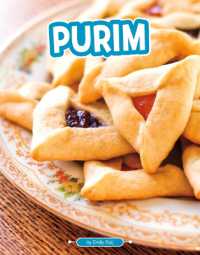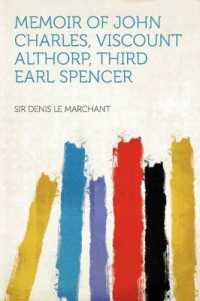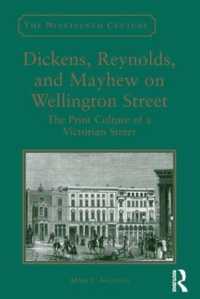- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
中華思想は文明の優劣で人々を区別する発想である。文明のある世界を中華とし、その周辺には野蛮な夷狄がいる。そして夷狄は中華に何も残さなかったものだと長らく考えられてきた。しかし注意深く歴史をみていくと、夷狄であるはずの遊牧民はむしろ中華文明の形成に積極的に関わり、新たに持ち込み、主体的に選別し、継承してきたことがわかる。中華文明拡大の要因は、あらゆるものを内部に取り込んで膨張していく性質にある。逆に言えば、気づけば夷狄も中華になっているのだ。本書は、中国史を遊牧民の視点から捉えなおすことにより、中華の本質に迫る一冊である。
目次
はじめに/第一章 中国史にとっての遊牧民/王朝交替/中華文明の存続/中国の地理/生活スタイル/女性の地位の高さ/遊牧の起源/馬の家畜化/車の発明/インド・ヨーロッパ語族の広がり/騎乗のはじまり/中国と牧畜/モンゴル高原の遊牧/第二章 中華文明の成立と夷狄/1 農牧境界地帯の形成 気候変動と社会の階層化/初期国家の成立/原中国人の祖形/青銅器の伝播/2 王朝の誕生と夷狄 城壁集落と首長/城壁集落から都市へ/殷墟/甲骨文字/二輪スポーク戦車と馬/天体観測と暦/方国/3 周と夷狄 殷周革命/牧野の戦い/天命思想/封建/殷を継承/周と夷狄/中華思想の起源/第三章 中華古典世界と夷狄/1 春秋諸侯と夷狄 歴史書の誕生/春秋時代の夷狄/晋の文公/の国 中山/2 戦国七雄と夷狄 文明世界とそれ以外/燕と東胡/趙の武霊王/3 秦と匈奴 開国伝説と聖人の政治/匈奴の登場/七雄の戦力比較/秦の中華統一/匈奴討伐と万里の長城/始皇帝陵/中国の成立/夷狄に対する四つの対処法/第四章 中華と夷狄の対峙/1 匈奴国家の成立 君主の呼び名/天子と皇帝/冒頓のクーデター/モンゴリア制覇/匈奴の国家体制/スキタイとの類似性/2 前漢と匈奴 白登山の戦い/和親/中行説/前漢の帳簿/国書の往来/匈奴の西域支配/漢と馬/武帝の即位/冊封のはじまり/武帝の挑発/汗血馬を求めて/烏孫/解憂/匈奴の衰退/単于乱立/破格の好待遇/王昭君の降嫁/3 新たな匈奴像 土城/匈奴の農業/第五章 夷狄を内包する中華世界/1 匈奴の臣従 匈奴は別格/王莽の華夷混一/四条の規定/夷狄を従える/王莽の容貌/匈奴の中興/匈奴の大型方形墓/2 後漢と南匈奴 莫大な下賜品/夷を以て夷を制す/逢侯の乱/3 北匈奴の動静 光武帝が和睦を拒否/碑文「燕然山銘」/三絶三通/北匈奴とフン/匈奴の発音はフン/烏桓/鮮卑/南単于権の崩壊/仏教伝来/第六章 夷狄による中華の再生/1 五胡十六国 八王の乱/五胡十六国のはじまり/劉淵の自立/皇帝即位/宗室軍事封建制/劉聡の即位/五徳終始説/前趙は胡漢二重体制/後趙の建国/石勒の統治/石虎の後継者問題/前秦の建国/苻堅の国家安定策/ 水の戦い/前秦の先進性/2 拓跋国家 併合と離散の国家成立/昭成帝の改革/北魏の道武帝/八国と代人/内朝/西郊祭天/季節移動/金人鋳造/子貴母死/真人代歌/太武帝の華北統一/孝文帝の漢化政策/3 柔然と南朝 柔然という称号の意味/仏教の隆盛/第七章 新たな中華の誕生/1 東魏・北斉と西魏・北周 新たな認識の萌芽/『周礼』と後宮/九龍の母/レビレート/恩倖/北周/天元皇帝/2 隋と突厥 侵攻と和平/隋の中華統一/兵士のゆくえ/二つの首都/貶められた皇帝/3 唐の新たな中華 多民族国家・唐/「古代書簡」/中華のソグド人/ソグド人軍団/ソグドの姓/玄武門の変/東突厥の滅亡/和蕃公主/則天武后/安史の乱/反乱の経緯/安史の乱とは何だったのか/唐の文化/騎馬女子/唐の長安/遊牧民視点の「中華」史/あとがき/参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サアベドラ
よっち
kk
ta_chanko
さとうしん