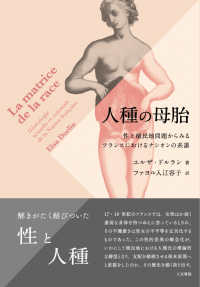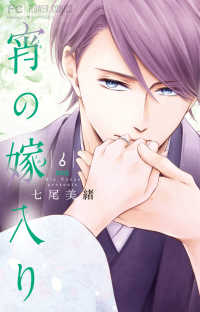内容説明
神との合一に到るための階梯を詳述したカトリック神秘思想を代表する作品。ヨハネは自らの詩に註解を施すかたちで神学的思索を行い、魂の浄化に向かう道を指し示す。「この山にはただ神の誉れと栄光だけが住まう」とされるカルメル山。すべてが闇の内へと沈む「暗夜」を通り抜け、山の頂きへ達するには、この世のあらゆることどもから──自分自身からさえも──逃れなければならない。魂の全き赤裸と神的一致をめぐる教説は、キリスト教徒を超えて人々に多大な影響を与えた。スペイン文学の至宝でもある古典を名訳でおくる。 解説 鶴岡賀雄
目次
序文(御聖体のルチオ神父)/霊魂の能動的暗夜/要旨/詩/まえおき/第I部 感覚の能動的暗夜/第1章 第一の詩句。人間は、劣った部分(体)と、高尚な部分(精神)とからなっているため、霊的な道を歩む人々の通る夜も、二つの異なったものがあること、ならびに次の詩句の説明。/第2章 神との一致に至るまでに、霊魂が通る暗夜とは何であるか。/第3章 この「夜」の第一に挙げられるべき原因、すなわち、すべての事柄に対する欲求をなくすること。および、それがなぜ「夜」と呼ばれるかという理由について述べる。/第4章 神との一致に向かって進むためには、「感覚の暗夜」──すなわち欲望の克服──を真に通りすぎることが、どんなに大切であるかについて述べる。/第5章 (前章の続き)神に向かってゆくには、すべてのものに対する欲望を克服するこの「暗夜」を通ることが、われわれにとって、どんなに大切であるかを、聖書によりながら、また、その比喩を用いて示す。/第6章 欲望が霊魂に及ぼすおもな損傷。一つは喪失性のもの。他の一つは、加害性のもの。/第7章 欲望が、どんなに心を苛むかについて述べる。比喩と、聖書によって証明する。/第8章 欲望が、どんなに霊魂を暗くし、盲目にするかについて。/第9章 欲望が、いかに霊魂を汚すかについて。──聖書の言葉と例による論証。/第10章 欲望が、徳の実行において、どんなに霊魂を冷やし、衰えさせるかについて。/第11章 神との一致に達するためには、たとえ些細なものであっても、欲望のすべてを捨ててかからなければならないことを証明する。/第12章 前に述べたような損傷を、霊魂の中に引き起こすに足る欲望とは、どんなものであるかということに答えて説明する。/第13章 感覚の暗夜に入るために、とらなくてはならない方法と、その形について述べる。/第14章 歌の第二句の説明/第15章 上記の歌の残りの句の説明/第II部 精神の能動的暗夜──理性/第1章 第二の歌/第2章 暗夜の第二部、すなわち信仰という暗夜の第二の原因について論ずる。何故に、この部分の暗夜が、第一または第三の部分よりも暗いかという理由について述べる。/第3章 信仰は霊魂にとって、どのように「暗夜」であるか、聖書の言葉と例による説明と、理論的裏づけ。/第4章 信仰によって最高の観想にまでよく導かれるためには、どのようにして、われわれの魂もまた、暗黒のうちに留まらなくてはならないかについて概略を述べる。/第5章 神との一致とは何であるか──一つの比喩。/第6章 精神の三つの能力を完成させるものが、どういう意味で三つの対神徳なのか。また、この魂がその精神能力のうちに、どのようにして空白と暗黒とをつくり出すかを述べる。/第7章 永遠の生命に導く道がどんなに狭いか、またこの道をゆくものの心は、どんなに赤裸で自由でなくてはならないかについて述べる。まず、知性の赤裸について話し始める。/第8章 一般に、被造物といわれるもの、知性の中に入ってくることのできる概念など、そのいかなるものも、神との一致の直接の手段とはなりえないことを論ずる。/第9章 知性にとって、神との愛の一致に至りつくためには、信仰がそれにふさわしい至近の手段であることを述べる。──聖書の言葉と比喩による説明。/第10章 知性の中に入り得るすべての知覚と知解の種別について。/第11章 五官による外的感覚において、超自然的に現れるものを、知性が把握する場合に生じ得る妨げと弊害について、およびこれらのものに対していかに処すべきかについて。/第12章 想像による自然の知覚について。それはどんなものであるか。また、それがなぜ神との一致のためにふさわしい手段とはなりえないか。そうしたものから逃れる術を知らない場合には、どんな害を蒙るかについて。/第13章 どんな時期に黙想と推理とをやめ、観想の段階に移るのに適当であるかを知るため、霊的な道を行く人が、自分のうちに見いだす徴について。/第14章 前進するために、これらの徴について述べたことの必要性を裏づけ、そのような徴の価値を確かめる。/第15章 もう初歩ではなく、進歩の段階にあるもの、すなわち、この観想の「はっきり枠づけられない知解」をもつにいたったものにとっても、時に頭を使ったり、また、自然の機能を働かせたりすることがどんなに大切であるかの説明。/第16章 何かの映像として、超自然的に表れる想像力による知覚について──こうしたものが神との一致のための至近の媒介となるには、いかに程遠いかということについて。/第17章 神が、感覚を通して霊的な宝をお与えになるときの目的と、その形についての説明、ならびに、前章にふれた疑問に対する解答。/第18章 霊的指導者のうちには、前にも述べたような示現(ヴィジョン)について、人々を正しく導かないものがあるため、それによって生ずる弊害について──また、さらに、それが神からのものであっても、そうしたものにおいて、自らを欺くこともあり得ること。/第19章 示現(ヴィジョン)や、神からの言葉が真実のものであるとしても、それについて、われわれが、どんなに錯覚に陥りやすいものであるかということの説明と論証。──聖書の言葉によって確かめる。/第20章 神の言われた事柄や、言葉は、それ自体、いつも真実なものであるとはいえ、それが生みだされる原因においては、いつも確かなものとは限っていないということを、聖書に基づいて証しする。/第21章 時には、神が、願ったことに答えてくださるとしても、このようなことを神がおよろこびにはならないということの説明。たとえ答えてくださったとしても、憤りを覚えられるということ。/第22章 恩寵の掟を与えられている今においては、旧約時代のように、超自然の道によって神に問いかけることは、なぜ許されていないかという疑問に対する解答。──聖パウロの書簡に基づく証し。/第23章 ただ霊的な道によってのみ得られる知性の知覚について論じ始める。──それはどのようなことかについて。/第24章 超自然の道による霊的示現の二つの形について。/第25章 啓示について。それは何であるか、また、その区別について。/第26章 知性による、真理のあるがままの認識について。その二つの形があることと、それに対して、われわれの態度はいかにあるべきかということ。/第27章 啓示、すなわち隠された秘義が外に示される第二の形について。それが神との一致に役立つ場合と、妨げになる場合。悪魔はいかにここで多くの偽りをなすかということ。/第28章 超自然的に心のうちに起こり得る言葉について。──それがどんな形のものであるかということ。/第29章 潜心している霊魂のうちに、時につくりだされる言葉の第一の形について。──その原因および、そうした言葉のうちにあり得る利益と弊害とについて。/第30章 自然の枠を超えた道によって、霊魂に明瞭に(形相的に)語られる言葉について。──これらのものが与える弊害、および、そうしたものによって欺かれないための必要な警告。/第31章 霊のうちに生ずる実質的な言葉について。──明示的言葉との相違、それらのうちにある益、および、そうしたものに対してもつべき思慮と、こだわらない態度について。/第32章 超自然的に生ずる内的な感動から、知性が受け取る知覚について。──それらの原因、ならびに、そうしたものが神との一致への道の妨げをしないようにするためにとるべき態度について。/第III部 精神の能動的暗夜──記憶と意志/第1章 概要/第2章 記憶による通常の知覚について。──この機能によって神と一致するためには、その知覚に全くこだわらないようにしなくてはならない。/第3章 記憶から生ずる知解や、推理を暗くしないために受ける三つの弊害について。──その第一。/第4章 記憶の本来の働きを通じて、悪魔が霊魂に及ぼす第二の弊害について。/第5章 本来記憶に伴う、はっきりした知解のために霊魂に生ずる第三の弊害について。/第6章 記憶をめぐって、通常もつことのできる思いや考えのすべてを忘れ、むなしくすることによって、霊魂が受ける益について。/第7章 第二の記憶の形として、超自然的な想像と知解。/第8章 超自然的な事柄について、繰り返し考えることが霊魂に及ぼす弊害について。──それが、いかほどであるかということ。/第9章 自負心や虚栄心に陥る第二の弊害について。/第10章 想像による思い出のために悪魔が引き起こす第三の弊害について。/第11章 超自然的に、はっきり記憶にとらえることが、神との一致の妨げとなる第四の弊害について。/第12章 超自然的想像によってとらえられる形に従う、神についての判断は、それが低く、かつ不完全なものであるために生ずる第五の弊害について。/第13章 想像によってとらえられるものを遠ざけることによって得られる益について。および、ある反論に対する答え、ならびに、想像によってとらえられるもので、自然的なものと超自然的なものとの間にある差異の説明。/第14章 記憶にとらえられる限りの霊的知解について。/第15章 こうした感覚に対して、霊的な道をゆく人々が対処すべき一般的な方法について。/第16章 意志の暗夜について論じ始める。意志の執着のさまざま。/第17章 意志の第一の愛着について。よろこびとは何か、および意志がよろこぶことのできる対象について。/第18章 この世の宝に関するよろこびについて。──これらのものについてのよろこびを、どのようにして神に向かわせるかについて。/第19章 この世のものをたのしむことによって生ずる害について。/第20章 現世的な事柄についてのよろこびを遠ざけることによって、霊魂に生ずる益について。/第21章 自然の宝に心奪われることがどんなにむなしいことであるか、したがってそうしたものを通して、どのようにわれわれを神に向けていくべきかについて。/第22章 自然の宝に心を奪われることによって霊魂に生ずる弊害について。/第23章 自然の宝をたのしまないことによってそこから引き出す益について。/第24章 人が心を奪われる宝の第三の形、すなわち感覚的なものについて。それはどういうもので、どのような種類であるか、どのようにして、このようなたのしみから心を洗い清め、神に向かうべきかについて。/第25章 感覚的なたのしみのために、霊魂が受ける害について。/第26章 感覚的なものについてのたのしみを退けることによって受け取る霊的および、この世での益について。/第27章 倫理的な宝の第四の形のものについて述べる。それはどんなものか、またどんな形で、それをよろこぶことができるかについて。/第28章 倫理的な宝に心を奪われるために生ずる七つの害について。/第29章 倫理的な宝についてのたのしみから離れることによって、霊魂に生ずる益。/第30章 心をたのしませることのできる第五の形である超自然的宝について。──それはどういうものであるか、および、それは一般の霊的宝とどのように区別されるか、またどのようにして、それを神のほうに向けなくてはならないかについて。/第31章 この種の宝をよろこぶために霊魂に生じる害について。/第32章 超自然の恵みからのよろこびを捨てることにより、引き出される益について。/第33章 意志のたのしみをつくる第六のもの。それはどんなものか、および、その第一の分類。/第34章 知性と記憶の中にはっきりとらえることのできる霊的宝について。これらの宝のたのしみがあるとき、意志はいかに対処すべきであるかについて。/第35章 意志にはっきりととらえられる快い霊的な宝について。──それがどのような形のものであるかということ。/第36章 画像について(続き)、および、これらについてのある人々の無知。/第37章 想像に浮かぶものによって、誤ることなく意志のよろこびを神に向けてゆくことについて。/第38章 よい動機となるものについて(続き)──聖堂および祈りの場所について。/第39章 心を神に向けるため、聖堂や教会をどのように用うべきかについて。/第40章 上に述べた内的潜心に精神を向かわせることについて。/第41章 以上のような具合に信心の場所や、事物の感覚的なたのしみに至るものの陥る弊害について。/第42章 三種類の敬虔な場所と、それに対する心構えについて。/第43章 多くの人々が種々さまざまな典礼によって祈るその他の理由について。/第44章 このような信心により、どのようにして意志のよろこびと力とを神に向けていくかについて。/第45章 意志のむなしいよろこびを誘う目に見えてはっきり現れる第二の宝について。/訳者あとがき/訳語解説/解説(鶴岡賀雄)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ナディル
-

- 和書
- 皆勤賞 文春文庫