内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
日本人に把握された豊饒な色の原点はどこにあるのか。万葉集・懐風藻・古事記・日本書紀・続日本紀・風土記はもとより、正倉院文書をはじめ、金石文・木簡等の記録的資料を取りあげることで、わが国の色彩の源流を辿る。上代日本社会の色彩のあり方を探る書。
目次
万葉の染色
万葉の紫とその背景
上代の黄-とくに万葉の「黄〓(しつ)」について
上代の赤-顔料を主に
万葉の「知らに」と、「白土」「胡粉」「白粉」について
「佛造る眞朱足らずは」攷
「白珠は人に知らえず」攷
万葉の緑児-当時の戸籍から考える
上代の馬-とくに黒馬と、その意義
色の霊力-「化」という事象を一例として
陰陽五行説の影響-万葉を主に
万葉のしるしの背景-上代の祥瑞について
万葉の人びとの色彩観
天武天皇のある一面
大伴家持の心情の一端
増補版論文(色と『万葉集』のかかわり
古代歌謡の方法-色彩について
万葉から古今へ-色彩の変遷
万葉の色
譬喩歌と寄物陳思歌-衣服の色彩をとおしてみた
紅乃深染
あかねさす
やまとたけるのみこと垣間見)
-

- 電子書籍
- 現代ユウモア全集 5巻 『東京初上り』…
-
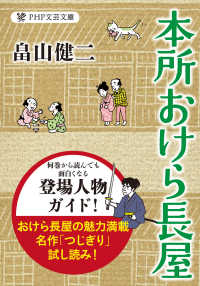
- 電子書籍
- 本所おけら長屋【お試し読み版・つじぎり】
-

- 電子書籍
- アイカギ(11) モバMAN
-
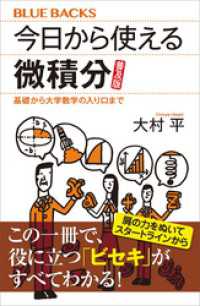
- 電子書籍
- 今日から使える微積分 普及版 基礎から…
-

- 電子書籍
- 闇の皇太子19 光と闇のロマンス ビー…



