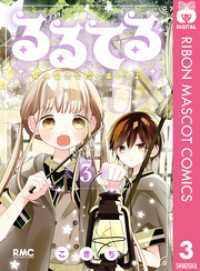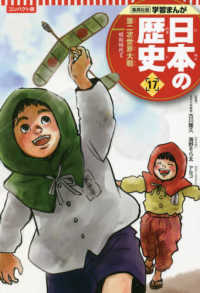内容説明
ボランティア先進国とされるドイツには,国家による支援制度が存在し,毎年数万人が参加している.ナチス時代の勤労奉仕という負の歴史と戦いながら,社会に貢献したいという個人の自発性を尊重し,国家に回収されない活動を支えてきたドイツの挑戦の軌跡をたどることからことで,ボランティアと社会とのあるべき関係を見つめ直す.
目次
はじめに――ボランティア支援政策が問いかけるもの
第1章 なぜボランティアを支援するのか――日独の事例から
1 日本のボランティア支援政策
JICA海外協力隊
一年間ボランティア計画
2 ドイツのボランティア支援政策
「ボランティア制度」の種類
歴史的展開
参加者の待遇
運営にかかわる団体
資金構造
3 訳語をめぐる検討
第2章 負の過去と向き合う――ボランティア支援の歴史的展開
1 なぜボランティアの制度化が実現したのか
自発性から義務へ――ナチ政権下の展開
一九六四年の法制化プロセス――戦後ドイツにおけるボランティア制度の成立
2 象徴的政策としての環境保護――一九九三年の法制化プロセス
州レベルにおける導入の試み
連邦レベルにおける議論
3 徴兵制停止後を見据えて――二〇〇二年法改正にみる集権化
州における民間役務法一四c条の影響
4 二〇一一年の歴史的転換――変わる政策的期待
徴兵制停止に向けた議論の展開
連邦ボランティア制度の導入プロセス
5 支援と干渉の隘路で――「自発性」をめぐる議論の変容
第3章 物言うボランティア――政治教育との接続
1 デモ行進するボランティア
2 ボランティアの政治性とその社会的受容
3 学校外政治教育としてのボランティア
4 ボランティア制度における政治教育の実践
環境保護団体による理論的基盤の提供
政治教育の担い手としてのボランティア
5 「物言うボランティア」を目指す教育の課題
第4章「承認の文化」に向けて――社会的包摂か,格差の再生産か
1 「誰一人取り残されない」政策の理想と現実
2 ボランティア制度をめぐる議論の展開
先行事例としての連邦ボランティア制度
「不利な状況にある若者」をめぐる議論
「承認の文化」を目指すロビー活動
奉仕義務への対抗
3 二〇一九年法改正における「社会的包摂」
就労・職業訓練との関係
若者の教育政策としての意義
「承認の文化」との乖離
右翼ポピュリズム政党と奉仕義務
4 法改正後の課題――ボランティア支援は社会的包摂に寄与するか
第5章 なぜ義務化が支持されるのか――揺れるボランティア制度
1 繰り返される「義務化」の議論
2 ボランティアは誰のものか――リベラルな価値と制度設計
3 コロナ禍における議論――奉仕義務をめぐって
徴兵制再開
奉仕義務をめぐる議論
連邦軍の「ボランティア制度」?
4 「義務化」支持者の論理――政治的合意の継続と変容
おわりに――政策から「ボランティア」を考える
あとがき
注
関連年表
用語リスト
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Go Extreme
takao