内容説明
日本の教育現実に怒り、それを変えるべく本を書き戦い続けた学者が、作文教育を、定番の教材を斬る。
教育学界最長老の一人にして衰えることなく吠え続ける著者が、今作では国語教育に絞り、その現状を斬る。読書百遍義自ら見る――「読み書きの能力は、読み書きをすることによって育つ。」として、①とにかく読む。それも、古典を読み、模範とする。②体を使って(手書きで)書く。それなくして読み書きの能力が伸びることはないと言い切る。さらに、発問は教師の論理で作られていて、学習者の読み手としての独立した世界の可能性は無視されていると指摘。発問による授業を誤った有害な方法と断じる。(年齢等は刊行当時。)
【著者】
宇佐美寛
1934年神奈川県横須賀市生まれ。東京教育大学教育学部卒業、同大学大学院教育学研究科博士課程修了、教育学博士。千葉大学名誉教授。東京教育大学助手、千葉大学講師、同助教授、教授(1993-97年教育学部長、1998-2000年東京学芸大学教授併任)。1961~62年米国、州立ミネソタ大学大学院留学(教育史・教育哲学専攻)。九州大学、山梨大学、岩手大学、山形大学、秋田大学、茨城大学、上智大学、立教大学、早稲田大学等の非常勤講師(客員教授)を務めた。2023年没。
目次
第1章 原稿用紙で思考するのだ
第2章 彼(彼女)は東大出だろうな
第3章 読めばいいのだ、書けばいいのだ
第4章 〈お礼〉の記号論
第5章 教室方言
第6章 前おきをやめよう
第7章 概念
第8章 教材文からの遊離・分裂
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しんえい
2
読み書きの能力を鍛えるには、読み書きをするしかない。その通りである。だが、授業に発問は不要なのか。いや、必要である。宇佐美寛氏自身も「子どもは未熟・未発達である。だから、子どものための教育内容は、価値が定まった重要な内容を、適切な順で少しずつ与えるべきものである」と述べている(26ページ)。その「与える」方法が発問である。 ……しかし、力量の低い教師がこねくり回した発問をするくらいなら、良文をたくさん読ませ、たくさん作文させた方が良いのであろう。反省した。まずは教師としての力量不足を認めなければならない。2025/05/01
まさきち
1
圧倒的な正論が持ち味の著者に初めて論戦をしてみたいと思った.思考のためには,キーボードではなく,手書きでないといけない(これもきちんと引用してないから怒られるやつだけれどもw)という論は,あくまで野中氏の不手際をパソコンに転嫁しているに過ぎない.精緻な論理をキーボードで綴る森博嗣の文章を宇佐美氏はどう考えるのか.でも,この論戦は,絶対に自分が負ける.この論を支える実践がないからだ.悔しいが,手書き教育はおこなわないぞ.ただ,考え続けることは絶対に怠らない.2019/02/08
今更読書
1
良書。ただ、「お世話になっております。」の件は、今の職場等で自分が言ったら、”メンドクサイ奴”で終わるだろうな・・・w この著者の他の本も是非読んでみたい。2018/10/14
良さん
1
自分のやっている指導法や授業を疑って、じっくり見直していきたいと思った。何よりもまず、自分がしっかり読み書きしないとダメだ、と思った。今まで教えよう教えようとする方向にばかり考えが行っていた。 【心に残った言葉】読み書きを教える当然の方法は読み書きである。発問ではない。多量に、くり返し、しかも入念・緻密に読み書きさせる。これしか無いではないか。(120頁)2018/09/22
にくきゅー
0
どれだけ僕は正確に読み書きできているのだろうか、そんなことを考えさせられた本。久しぶりの宇佐美体験。これをどう超えるか。2018/07/27
-
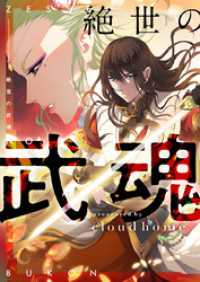
- 電子書籍
- 絶世の武魂【タテヨミ】第296話 pi…
-

- 電子書籍
- 【重大発表】これから動画配信者に復讐し…
-

- 電子書籍
- 村の不幸を背負った嫁ですが【フルカラー…
-
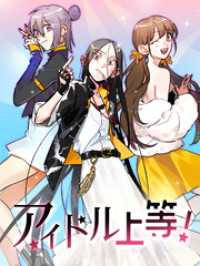
- 電子書籍
- アイドル上等! 第31話 炎上【タテヨ…
-
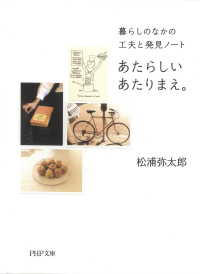
- 電子書籍
- あたらしいあたりまえ。 - 暮らしのな…




