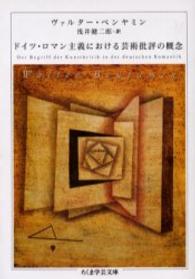- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
2040年の食生活、食産業はどうなっているのだろうか。AIがサポートしてくれるため、経験の浅い人でも失敗しない都市農園が普及し、食料自給率対策の一つになっている(すでに現状、ロンドンには3000箇所以上の都市農園があるという)。さらに家庭内にも、野菜や穀物を育てる栽培庫ができ、採れた食材は3Dフードプリント機能付き家庭用調理ロボットが調理してくれる(現在、植物工場スタートアップのプランテックスは生育状況をかなり精緻に制御する技術を持ち、スーパーマーケット用などに巨大な植物工場コンテナを手がけている)。日本の食産業における変化としては、各地方ごとに循環型経済を実装する「マイクロフードシステム」が構築されている。また「シン輸出拠点」も設置され、冷凍装置や粉体化装置など、世界中に輸出できる設備が配備されている(冷凍技術の進歩は目覚ましいものがあり、将来は生ケーキやお弁当を輸出できるかもしれない)。著者は本書の第3章で、このような未来シナリオを7つ提示している。本書の「未来シナリオ」は、現在すでにある技術の延長線上にある未来をシミュレートする「未来予測」とは異なるものである。未来のある時点において、社会や生活者がどのようなニーズを持ちうるのかの洞察、技術や社会環境の変化の予測と根拠、社会として人類として大事にしたい価値や哲学という観点から考察を進めた上で、解像度高く絵や言葉に落とし込み、ストーリーとして編集したものだ。本書では、食に関するプレーヤーの間での「共創」を生み出すための事業を展開している企業「UnlocX」の二人が、第1章で過去5年間に変貌を遂げたフードテックの最前線、第2章で「サステナブルからリジェネラティブへ」という未来を考えるための大前提について解説したあと、上述の「7つの未来シナリオ」を提示する。その後第4章で、この未来シナリオを社会実装するための「新経済モデル」について語り、第5章では、食品メーカー、銀行、大学、メディアのキーパーソンを招いて、7つの未来シナリオについて徹底議論する。最後の第6章では、本書の総括として、日本発で日本の強みを活かした食の未来をどのように共創していくのか、今、どのような取組みが動いているのかについて考察する。巻末には、本書で登場する注目すべきスタートアップやプロダクトなどを解説した。食の未来を構想する視野が圧倒的に広くなってワクワクするとともに、明日から始められる具体的なビジネスのヒントが満載の一冊である。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よっち
はるき
とも
きゅー
Go Extreme
-

- 電子書籍
- 異世界でもふもふなでなでするためにがん…
-

- 電子書籍
- 女友達は頼めば意外とヤらせてくれる【分…
-

- 電子書籍
- レベル9の閲覧要員96【タテヨミ】 R…
-

- 電子書籍
- 美活時代【タテヨミ】第5話 HykeC…