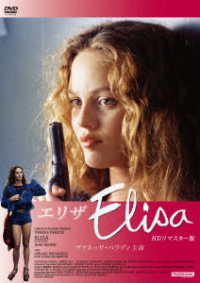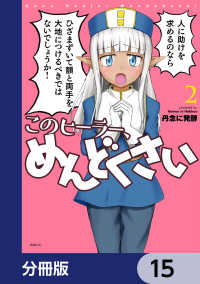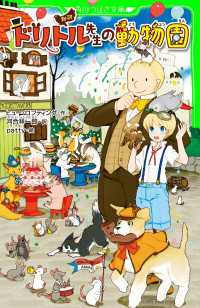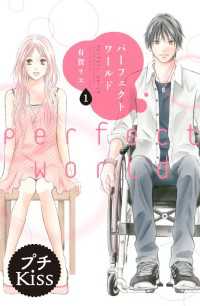内容説明
ブッダの教えはどんな「幸せ」を創造できるか?
2008年、ミャンマーで著者は戒律の厳しい「森の寺院」で出家する。布施のみで生きる出家者のあり方に仏教の可能性を確信し、帰国後京都で新寺院を立ち上げて現代日本に即した仏教のあり方を追求しはじめたが……。宗教の本質と現代的可能性に迫る、一気読み必至の学術ノンフィクション
【内容】
はじめに
第一章 「律」厳守の挑戦 ――タータナ・ウンサウン寺院
第二章 「善行」の共同体 ――ダバワ瞑想センター
第三章 「即身成仏」という理想 ――実験寺院・寳幢寺
おわりに
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
お抹茶
4
ミャンマーの寺院でのフィールドワークと日本の寶幢寺での経営経験を記す。行政による福祉サービスが不十分なミャンマーでは社会福祉活動を行う寺院があり,世俗教育を行う寺院もあり,在家者と極力交流を避ける寺院もある。社会福祉活動を行う寺院は世俗的な幸せへの貢献が超俗的な幸せに繋がると考えるが,出家者が自らの修業に専念することを優先する寺院もある。律遵守の挑戦は,社会との関係および寺院組織内部における在家者との関係の調整という問題として現れる。寺院は社会と仏教を繋ぐ装置と考える。2025/04/02
tetsuwo
2
皆に役立つと信じる思想を持っているだけでは飯を食えない。非営利で組織を経営することのジレンマを体験できる。必要最小限の顧客(スポンサー)を確保するために大衆に迎合するも、思想の本質の普及からはどんどん遠ざかる。本書ではマスメディアの目に止まったことで首の皮がつながったが、本質の普及はここからどうするかにかかっているだろう。そもそも、思想の普及と飯の糧を同じ活動内で完結させようとしてはいけないのかもしれない。2025/05/11
呑司 ゛クリケット“苅岡
1
仏教を知りたくて手に取った本だが、期待した内容ではなく、ミャンマーでの経験と日本では福祉寺院の寳幢寺の実践を解説している。出家か軍隊かを選ばなくてはならないミャンマーの現状日本での布教活動の中に見える仏教や寺院の役割の違いなどは面白く読めた。仏教の前に宗教は幸せを求めて存在すると勝手に想像していたが、その幸せが幾通りもあることにあらためて気づいた。2025/04/19
Go Extreme
1
出家生活と戒律:出家生活 超俗的幸せ 律遵守 金銭忌避 食事制限 涅槃追求 教学寺院 試験競争 在家者との関係:布施相互依存 在家支援 出家者模範 精神的修行 信徒支持 サンガ関係 教えの伝達 寺院の社会的機能:社会福祉 教育機関 福祉支援 地域連携 啓発活動 貧困者受け入れ 社会貢献 善行と共同体:善行実践 相互扶助 共同体形成 精神的成長 布施行為 経営と課題:寺院経営 赤字継続 設計主義克服 財政支援 資金不足 経営方針改革 現代仏教:即身成仏 実験寺院 現代仏教 日本的適応 社会実装 文化的橋渡し2025/03/22
kiri
0
ミャンマー寺院の経営事例の紹介と、国内で寺院の設立、運営に携わった体験記です。人々が「ハッピーに暮らせる」ように助力することを目的にした、檀家を持たない、葬式をしない、布教活動をしない寺院の運営は想像以上に厳しいものでした。日本人は「宗教」に対して警戒心が強いように思いますが、法律や条例だけでは手の届かない領域を守ってくれるツールとして宗教や哲学には可能性を感じます。お寺に限らず、心の拠り所となる場所が増えていけば良いなぁ、と思いました。2025/06/27