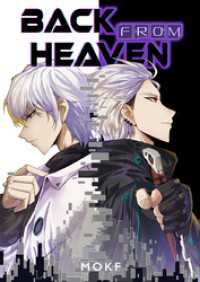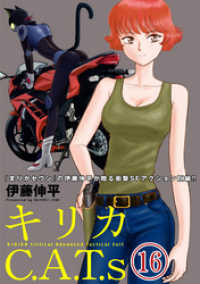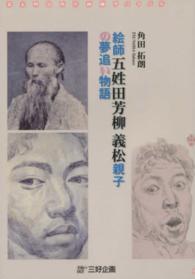内容説明
2010年に、食文化としてはじめてユネスコの世界無形文化遺産に登録された「フランス人の美食術」。食材や調理方法を絶え間なく変化させ続けてきたフランス人たちの食事に対する飽くなき関心は、どのように生まれ、表現されてきたのか。
テーブルセッティングと庭園の共通点とは。
ゾラが「ブランデーは身の破滅」と記したのはなぜか。
ミレーとファン・ゴッホは、なぜジャガイモの描き方がちがうのか。
食の歴史を筆者独自の視点でたどりつつ、文学・美術作品からフランスの食文化を逆照射し、料理が、他の文化の作品と相互に影響を与えながら発達した文化であることを浮かび上がらせる。
目次
まえがき
1章 フランス料理からフランス美食学へ
2章 アントルメとパティスリー
3章 パンの歴史とフランス人
4章 ジャガイモとフランス
5章 ワインとアイデンティティー
コラム
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Go Extreme
2
「料理は自然と文化の媒介」レヴィ=ストロースの料理三角形を通した文化的食物への変容 「美味しくしようとする意志-栄養摂取を超えた文化的行為としての料理 「食卓は舞台」17世紀以降のサービス構成と視覚的美意識の確立 「ガストロノミー=文化そのもの」 食を核とした総合的文化概念 「飢饉を救う貧者のパン」ジャガイモが担った歴史的役割 「地のリンゴ」ジャガイモの文化的受容を象徴する言語戦略 「テロワール=土地の魂」ワインが体現する地域アイデンティティ 「ガストロノミーの総合史」美術・文学・社会史が交差する食の全景2025/04/02