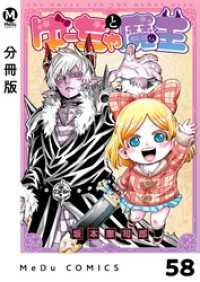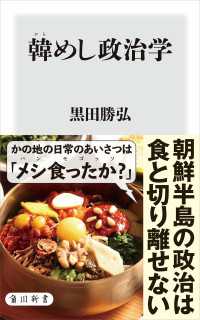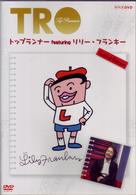内容説明
作家・研究者としてロボットを追う瀬名秀明氏を迎え、瀬名氏が「ロボティクス界のホープ」と呼ぶ稲邑哲也准教授の研究紹介を通じて、ロボット研究がどこへ向かっているのかを解き明かす。キーワードは「おへそ」。ロボットは将来どこまで人間とツーカーの仲になれるのか──脳科学から進化論まで、知の領域を横断しながら最先端に迫る。
目次
第一章 ロボットの「おへそ」をつくる 瀬名秀明氏を迎えて1
第二章 脳科学とロボティクス
第三章 イヌはどんなところが賢いか
第四章 「まねる」と「まなぶ」のダイナミクス
第五章 あいまいさを乗り切れ!
第六章 ひととロボットが暮らす未来 瀬名秀明氏を迎えて2
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
コユキ キミ
2
ロボットを作るためには、人間のあやふやさを研究しなければならず。。。 いわゆる「ロボット」というものを作るためには人間そのものをとことん追求しないとできないのね。。。 ということがよーっくわかりました。カーナビでもいいんですというあたりがもはや。。です。原始シンボル空間を使って動作を単純化して組み合わせるという仕組みが面白かった。2014/05/04
azur
2
わかりやすい語り口で先端のロボット研究が説明されています。ロボット系を専攻したい人には良い教材になるのでは。2010/02/06
takizawa
2
ロボットのおへそとは、現段階でのロボットに欠けているものの比喩。工学の研究をしている人と社会学者がなぜ議論するのかがよく分かったw あらゆる状況に対応できる完全なプログラムを作るのではなく、その場その場で学習していってもらうロボットを作る。このことは、あらゆる状況に対応できる法を作ることを断念した歴史にちょっと似ている。日本人は小さいころからドラえもんや鉄腕アトムと暮らす未来を自然と描いているから動機付けはばっちり。これに対して欧米人は、ロボットはなるべく「見えないように」しておくのが一般的だったりする。2009/03/03
motoso
1
「ある条件のときはどのように動作する」とすべての場合に対してプログラムするのではなく,確率・統計を用いてロボットを制御する.自分の認識が違っていれば「あっちにそれっぽいものがあったっけ」と考えてくれる.「それっぽいもの」という曖昧な条件をロボットにどう認識させるのかという大きな課題に対してアプローチしていく.外的環境の変動が頻繁な家庭用ロボット全てに将来的に使われると言われても不思議がない.人間がストレスなく付き合っていける知的なロボットの条件は何かを論考.学習し,使用者に最適化するのが一つの解か.2012/10/22
三木
1
書いている側にワクワクするような感情が満ち溢れているから、感心しつつもこちらも楽しんで読むことができる。この本に書かれていることが不思議になるぐらいロボットが進化していく日がくれば楽しいだろうなあ。2011/02/20