- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
■「米国の圧力で思うがまま?」「日銀の金融政策で決まる?」「通貨マフィアの腕しだい?」「為替は実体経済を映す鏡?」――円相場をめぐる「都市伝説」はなぜ生まれたか。ベテラン記者が謎をひもとく。
■日本は円高になっても円安になっても、なぜ大騒ぎするのか。為替レートに一喜一憂するのも、日銀や通貨マフィアに過剰な期待や責任が押し付けられるのもいまや日本だけ。1987年のブラックマンデーから、2024年の「令和のブラックマンデー」まで現場で取材してきた記者が、為替に翻弄される歴史とその真因、日本経済のいびつな構造を明らかにする。
目次
第1章「令和のブラックマンデー」をどう読むか――為替に翻弄され続ける日本
第2章 都市伝説(1)「円相場は米国が決める」――日米交渉化した為替相場
第3章 都市伝説(2)「円相場は日銀の金融政策で決まる」――為替との距離に悩む中央銀行
第4章 都市伝説(3)「円相場は通貨マフィアの腕しだい」――進化する介入大国
第5章 都市伝説(4)「円相場は実体経済を反映する」――だが市場は常にいきすぎる
第6章 円相場の「脱ガラパゴス」への道はあるか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
kk
17
図書館本。戦後日本経済の足取りを振り返りながら、円ドル相場の変動が我々の経済生活に如何に大きなインパクトを与えて来たかを提示。そうした背景の下、関係プレイヤーたちの時々の思惑に光を当て、為替相場による国民経済の調整という大時代的アプローチが、我が国では依然として罷り通っている有様を炙り出す。著者の基本的なスタンスは、このご時世、経済再生の鍵は、為替や通貨の操作といった小手先の技にではなく、価格メカニズムの改善や産業構造の変更など、痛みとリスクを伴う構造改革にこそ求められるという考え方。激しく同意。2025/05/01
takao
1
ふむ2025/08/20
Kb54081271Kb
1
日本ほど為替に敏感な政府そして国民はいない?右往左往させられてきた日本の為替と市場介入の歴史を紐解く、為替ノンフィクション。昨今の円安で生活は苦しくなっているけど、ちょっと昔は円高で苦しんでいたんだよね。思うに任せない為替の操作に苦闘する裏歴史が面白い 2025/03/01
ゼロ投資大学
1
2011年には円相場は1ドル75円を付けていたが、24年には161円を超す円安となった。エネルギー価格の高騰と円安による輸入物価の高騰で、日本にもインフレの波が押し寄せている。日本が短期間のうちに為替相場に振り回される要因となった原因は、「ガラパゴス現象」にある。日本の商品やサービスが国内で独自の発展を遂げたことにより、世界市場での優位性を持たなくなり競争力を失うようになった。2025/03/01
Go Extreme
1
円相場の変動と影響: 円安(2022-2024) 為替市場介入 インフレ対策 米国との金利差 円売り・ドル買い 日本銀行の金融政策: 長期金融緩和 市場介入 金融政策の限界 インフレ抑制策 物価上昇への影響 歴史的背景と政策: 1985年プラザ合意 円高不況 民主党政権の円高政策 1990年代の通貨政策 輸出企業の影響 政治的要因と対応: 岸田政権の円安対策 歴代政権の為替政策 政府補助金政策 選挙と為替政策 今後の課題: 経済構造改革 日本の国際競争力 貿易収支悪化 物価と賃金のバランス グローバル市場2025/02/22
-
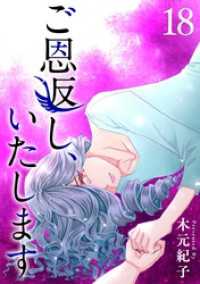
- 電子書籍
- ご恩返し、いたします 18巻 ティアード
-

- 電子書籍
- 口語全訳華厳経 12 逝多林会の一
-
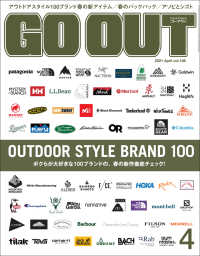
- 電子書籍
- GO OUT 2021年4月号 Vol…
-
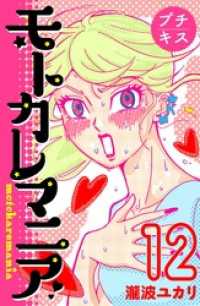
- 電子書籍
- モトカレマニア プチキス(12)
-

- 電子書籍
- 司馬遼太郎短篇全集 第四巻 文春e-b…




