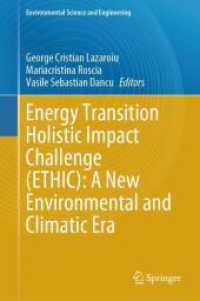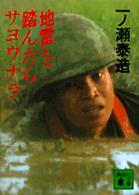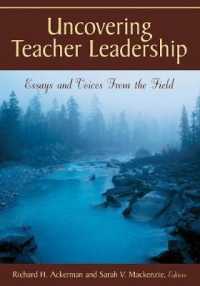内容説明
戦後日本の民主主義は「与えられた/押しつけられた」ものなのだろうか.アジア太平洋戦争を草の根から支えた日本の民衆が,過酷な戦争体験と伝統的な価値観をもとに,民主主義を自ら作りあげ,獲得したことを,彼らが残した日記や雑誌投稿,聞き取りなどを通して明らかにする.『草の根のファシズム』の続編,待望の文庫化.
目次
第6章 自由と民主主義の再創造Ⅱ
1 ある高校教員の戦後体験
2 ある小学校教員の体験
第7章 女性の自立と解放をめざして
1 女性解放の息吹
2 あるダンサーの自立への願い
3 ある共働き家庭の妻の苦闘
4 中島飛行機元職員の結婚・離婚と自立
5 ある女学校・中学校教員の体験
第8章 中国・ソ連へのまなざし
1 日中戦争の反省と中国観
2 シベリア抑留問題と戦後
第9章 見えない他者
1 在日男性にとっての平和と民主主義
2 在日女性にとっての平和と民主主義
第10章 変わらざる意識――あるエリート社員のインドネシア体験
おわりに――草の根の占領期体験の意味
註
あとがき
岩波現代文庫版あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nagoyan
10
優。戦中、戦後の様々な階層、立場の日本人が、未曽有の戦争、敗戦、敗戦後の社会変革をどのように受け止めたのを記録した。その体験自体が戦後民主主義の可能性と限界とつよく結びついていると。生々しい手触り感、息づかいをも感じられ、著者の立場からくる「評価」をそれとして注意すれば、むしろ、読者の私には、民衆のリアルな民主主義体験が愛おしく、まっすぐに肯定すべきものとしてよみがえってくるように感じられた。ただ、その開放感をもたらした自由主義的価値観が戦前、戦中でいかに沈潜していたかは、本書でも明らかにならない。2024/12/08
Go Extreme
2
占領期の社会的背景:戦後混乱 食料不足 インフラ破壊 生活様式変化 地域コミュニティ形成 共同体の取り組み 草の根運動の具体例:労働組合活動 市民団体運動 労働条件改善 平和促進 教育の重要性 新教育理念 平和意識の芽生え:反戦意識 戦争の記憶 核戦争認識 非戦の重要性 社会再構築 弱者の文明 意義と教訓:草の根経験 戦争の記憶保存 平和構築 民主主義維持 社会の安定 未来への展望 現代への示唆:地域社会再生 平和促進 持続可能な未来 過去の教訓実践 民主的価値継承2025/03/19
Go Extreme
2
自由と民主主義の再創造Ⅱ: ある高校教員 ある小学校教員 女性の自立と解放をめざして: 女性解放の息吹 あるダンサーの自立への願い ある共働き家庭の妻の苦闘 中島飛行機元職員の結婚・離婚と自立 ある女学校・中学校教員の体験 中国・ソ連へのまなざし: 日中戦争の反省と中国観 シベリア抑留問題と戦後 見えない他者: 在日男性・在日女性にとっての平和と民主主義 あるエリート社員のインドネシア体験 草の根の占領期体験の意味 自分の少年期の思い出 憲法・農村村の自分のような子供も守ってくれる→次々と掘り崩される事態2024/12/24
数之助
0
激動の時代を生き抜いた人びとの群像。2025/07/11
qbmnk
0
前作「草の根のファシズム」より読みにくいので、腰を据えて上巻に引き続き一気読みをした。日本民衆の占領下当時の意識を偏らずなるべく広く扱いたいという意欲を感じるが、各章のまとめが少なく散漫な印象。前作では世論調査の大きな傾向と日記など個々の記述が対比されて分かりやすかったが、本作は日記中心で全体傾向の分析は少なく感じた。聞き取りを混ぜたのも振り返りで時代意識から離れることになり散漫さに繋がっていると思う。ソ連に対する見方が抑留者帰国により急激に悪化しているところはある意味ソフトパワーの現れで興味深い。2025/06/15