- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
いまも続く「失われた30年」の直接的な原因とされるバブル経済の崩壊。当時、金融業界では何が起こり、関係者は何を見誤ったのだろうか。段階的に導入された一時国有化、新銀行設立、資本注入、不良債権の分離などの「破綻処理スキーム」は、何を目指したものだったのか。激動の現場で実務に当たった著者がその舞台裏を振り返り、金融不安と隣り合わせの現代に、その教訓と危機対応の考え方を伝える一冊。
目次
はじめに/第一章 金融危機が生んだ経済の断層──97年~98年の日本の経験/「銀行の潰し方を研究せよ」/金融危機が実体経済に与えた悪影響/「魔の97年11月」/第1次流動性危機──山一證券、徳陽シティ銀の連続破綻/初めて目撃した「取付け」の行列/第2次流動性危機──長銀、日債銀の破綻/日銀貸出と公的出資/第二章 公的資金、預金保険の資金援助始まる/低利融資方式の公的資金/護送船団方式と預金保険/預金保険の初適用/BCCIの破綻とヘルシュタット・リスク/東洋信金の巨額詐欺事件/「奉加帳方式」とは何か/事業譲渡か合併かの対立──釜石信用金庫/不良債権の分離から分割譲渡まで/資産稼働効果を導入/悪質な破綻理由──イトマン事件と大阪府民信用組合/大阪府民信組の破綻処理/幻の合併構想/韓国系金融機関初の破綻──信用組合岐阜商銀/太平洋銀行の逆さ合併/太平洋銀行の来歴/大蔵省との擦り合わせ/落とし穴は別にあった/第三章 バブル経済の崩壊/東京協和、安全の二信組破綻/受皿専門の銀行、東京共同銀行の設立/二信組の破綻処理不信の深淵/国民との対話が重要/コスモ信用組合の破綻/木津信用組合の破綻/兵庫銀行の破綻処理──大蔵省と日銀の意見対立/大震災直後の神戸出張/みどり銀行の設立/兵庫銀行破綻物語の終幕/住専の不動産融資で不良債権の山/住専問題、3つの論点/公的資金投入への反感/公的資金投入はなぜ唐突な印象になったか/住専国会の紛糾/第四章 金融危機/三洋証券のデフォルト/寄託証券補償基金から投資者保護基金へ/コール市場でのデフォルト/拓銀の転落/大規模銀行初の破綻/拓銀破綻で北海道経済はガタガタ/交付国債方式で公的資金/望ましい拓銀処理は日銀のつなぎ出資/山一證券の自主廃業/「飛ばし」とは何か/日銀内でもめた特融発動/釈然としない山一證券破綻/山一證券処理の最善策は何だったのか/リーマン・ブラザーズは米国版・山一證券/リーマン・ショックがドル危機へ/リーマン破綻と米国政治の混乱/第五章 ようやく完成した金融システム安定化策/特別公的管理──長銀の一時国有化から外資への売却/金融国会──野党案を丸 みした小渕内閣/ハードランディング/金融債の保護問題/日債銀の連鎖破綻/奉加帳方式の日債銀再建策/長銀・日債銀の刑事責任追及と時効の壁/長銀、日債銀裁判の争点/スケープゴート/貸付信託に膿がたまる/脱・貸付信託を進め、最後は廃止に/幻の日本信託銀行の破綻処理/第六章 遅すぎた特効薬「公的資金」/タブーへの再挑戦/第1次公的出資が極端に少額だった理由/早期健全化法──大規模な注入に成功した第2次公的出資/金融危機局面の変化/「不良債権問題解決を通じた経済再生」/竹中プランの手法/不良債権の大幅減少/金融危機対応措置の確立/竹中改革による金融危機対応措置──りそな銀行の公的資本注入/竹中改革による金融危機対応措置──足利銀行の一時国有化/第七章 公的出資はなぜ遅れたか/日銀がまとめた基本4原則と大蔵省との折衝/住専処理で大蔵省に申し入れ/公的資本注入と受皿金融機関の設立/変遷したメディアの主張/りそな問題に対するメディアの反応/金融危機発生の原因/政府の日銀特融依存/西村銀行局長が公的資金に否定的だったわけ/公的資金はなぜ必要だったか/あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
とりもり
ぎぃ~
バーニング
KS20
-
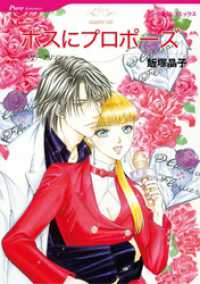
- 電子書籍
- ボスにプロポーズ【分冊】 12巻 ハー…
-
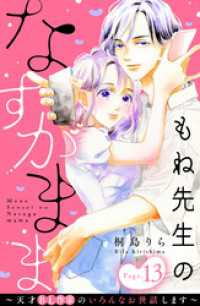
- 電子書籍
- もね先生のなすがまま~天才BL作家のい…
-
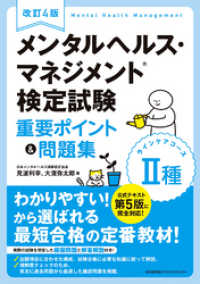
- 電子書籍
- 改訂4版 メンタルヘルス・マネジメント…
-
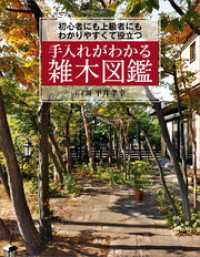
- 電子書籍
- 手入れがわかる雑木図鑑 初心者にも上級…
-

- 電子書籍
- ホワイト企業 創造的学習をする「個人」…




