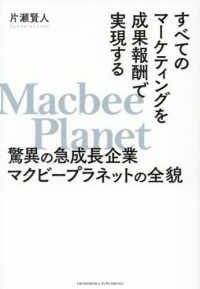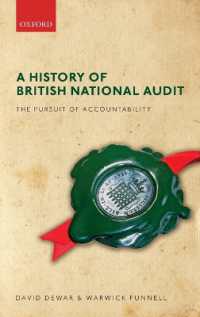内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
公共図書館の多くは1970年代後半から90年代にかけて建設され、書籍・雑誌を中心とした資料の収集・保存・提供を目的とした空間設計がなされていた。2000年代以降は社会状況、技術環境の急激な変化・進展にともない、リノベーション、コンバージョン(用途変更)が数多くなされてきたが、未だ多くの図書館が暗中模索の段階にある。 そこで本書は、安城市中心拠点施設、野々市市文化交流拠点施設、玉野市立図書館、武蔵野市立吉祥寺図書館、砺波市立図書館といった5つの先進的な事例をもとに、ICTをうまく取り入れながら図書館機能の複合化を図り、自治体が抱える課題に応える実践的な方策を多数の図版を通して紹介。
目次
1.図書館建築の実践(安城市中心拠点施設、野々市市文化交流拠点施設、玉野市立図書館、武蔵野市立吉祥寺図書館、砺波市立図書館)
2.現代の図書館の空間構成(ICTを積極的に活用した図書館空間の構成、図書館と多機能の複合)
3.図書館建築の未来
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きゅー
8
著者が代表を務める建築事務所が設計を行った3事例の紹介と、ICTを活用した図書館空間計画について記されている。うち1事例では大型物販店の一部を改築し、図書館を中心とする公共施設に転用するというプロジェクトであり、構造的な制約の中で最大限の効果を得ようとする試みに興味を惹かれた。ところで、現在の公共図書館の常識としては、図書館のみを独立させるのではなく、子育て支援センターなどと共に包括的な市民サポートの一環として位置づけられていることがよくわかった。施設を集中した方が運営者、利用者ともに都合が良いのだろう。2018/10/15
-
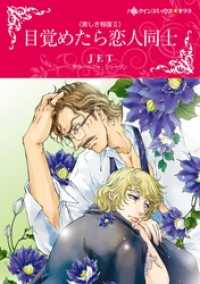
- 電子書籍
- 目覚めたら恋人同士本編