内容説明
昭和初期に鮮やかに出現し、いまなお文学に関心を抱く者がどこかで出会う、小林秀雄、梶井基次郎、中原中也――
彼らの文芸評論、小説、詩はどこが新しく、どこが古かったのか?
著者は通念にとらわれず、すべてをゼロから読み解くことで、この三人の文学者の表現を徹底的に検討し、思いの外自らに近いところに三人の存在があるという理解に至る。
「早稲田文学」1981年11月号に発表されたものを徹底的に加筆訂正し、1987年7月に刊行された二番目の評論集『批評へ』に収録された長篇文芸評論が37年を経て再刊される。
文芸評論家としての加藤典洋の出発点に再び光が当てられる。
目次
はじめに
1 小林秀雄の世代の「新しさ」――「社会化した私」と「社会化されえない私」
1 「故郷を失つた文学」
2 「私小説論」
2 小林秀雄――ランボーと志賀直哉の共存
1 再び「私小説論」
2 「私小説」という制度
3 梶井基次郎――玩物喪志の道
1 「白樺派流」の意味
2 モノへの自由
3 トルソーについて
4 「檸檬」の記号学
5 キッチュ
4 中原中也――言葉にならないもの
1 「うた」の古さ
2 モノの否定
3 「古さ」の選択
4 「下手」さへ
5 小林と中原――社会化と社会性
6 「惑い」の場所――終りに
註記
魂の露天掘り――小林秀雄の死に寄せて
参考資料 単行本『批評へ』あとがき
年譜
著書目録
-

- 電子書籍
- 消えた母は見知らぬ遺体になってここにい…
-
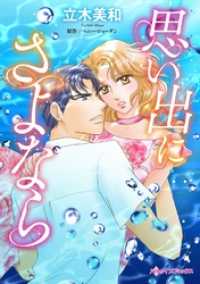
- 電子書籍
- 思い出にさよなら【分冊】 9巻 ハーレ…



