内容説明
江戸後期の日本が、ヨーロッパを、世界を支配する中心的存在と認識した契機は、ロシアの脅威であった。急速に深化した世界研究の動向と、これに併行して、ヨーロッパに対峙する「鎖国」外交が成立する経緯をたどる。世界理解の深まりが、進んだヨーロッパの科学や技術を受け入れる動きを生み、日本の近代化を支える土台が形づくられた様を描く。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
117
鎖国完成時の日本では、外国とは大陸や朝鮮を含め南にあるものと認識されていた。しかし北方からロシアが南下してきたと知り、さらには文化露寇事件の敗退もあって幕府も外交の前提を大転換しなければならないと悟ったため、新しい語学や科学技術の導入が図られた。そんな「変わった」部分が旧態依然の思考に囚われた「変われない」勢力と対立し、さらに長い泰平期に成立したナショナリズムと称すべき国学や攘夷意識とも衝突して幕末維新の動乱に至る。18世紀末から日本人の意識には北の脅威が固定され、近代の戦争や外交に繋がったと理解できる。2025/02/05
まーくん
90
江戸時代後期の日本人は一体世界をどう理解していたのか?自分個人としては漠然としていたが、本書を読み腑に落ちたような気がする。少なくとも幕府の要路者及び知識層はぺリー来航によって泰平の世の眠りから目覚めたわけではなかった。日本の北方に漸次現れた「ロシア」により、欧州諸国の世界進出への理解が進んだ。1792年、大黒屋光太夫ら漂流者を連れ蝦夷地に来航したロシア使節ラックスマンの一件処理にあたった老中松平定信のロシア問題への理解・研究はかなりのものだった。又、『加模西葛杜加(カムサスカ)国風説考』を著した⇒2024/12/25
さとうしん
18
ラクスマン来航以来のロシアとの接触が江戸日本の地理認識や文明観を変えたという議論。西洋世界に対する認知がそれまでは暦のための天文学程度にしか利用されていなかった科学・技術の重要性に対する認識を生じさせ、それらを生み出せなかった中国に対する蔑視や文明国が未開の地域を支配するという植民地主義的な見方を内面化させることとなった。また武士たちの蘭学の興味は外国への脅威への対応の模索と表裏一体であった。江戸幕府の意外な外交・危機対処能力とともに日本の近代化が持つ危うさや歪みを考えさせられる内容となっている。2024/12/10
MUNEKAZ
16
北方に現れたナゾの国「ルス国」。この衝撃から始まる江戸幕府の対ヨーロッパ認識の変遷を紹介する一冊。多くの史料を読み解きながら、幕府のヨーロッパ像が「夷狄」からむしろ進んだ技術を持つ強国へと変化していく様は面白い。それは中国を先進国とする伝統的な見方を相対化し、明治維新への助走となる。ペリー到来でいきなり泰平の眠りから覚めたわけではなく、少なくとも幕府と知識人層は新たな世界の潮流を感じ取っていた。また蘭学者の情熱は、純粋な学問的興味ではなく、対外危機を前にした「国益」の意識があったというのも興味深い。2024/12/25
アメヲトコ
11
2024年12月刊。明和8年(1771)、日本の北方に「ルス国」という国が南方を窺っているという真偽不明の情報がもたらされて以降、日本人が徐々にロシアの脅威に気づき、世界認識を変えていく過程を辿った一冊です。工藤平助の先駆性や高橋景保・間宮林蔵・伊能忠敬ら、江戸時代知識人の知的忍耐力には頭が下がるばかりですが、一方で西洋の科学と技術を獲得する過程は、それまで敬意の対象であったアジアを軽侮するようになる過程でもあり、複雑な思いもします。理系大学生の我が子にも読めるようにと専門用語を排した文章は読みやすい。2024/12/06
-
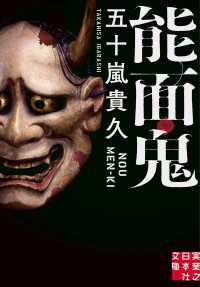
- 電子書籍
- 能面鬼 実業之日本社文庫
-
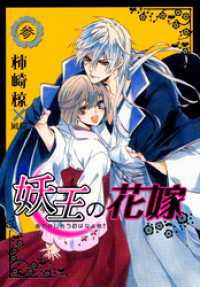
- 電子書籍
- 妖王の花嫁 3巻 冬水社・いち*ラキコ…
-

- 電子書籍
- モトチャンプ 2022年6月号
-
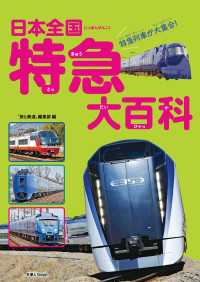
- 電子書籍
- 日本全国 特急大百科 天夢人
-
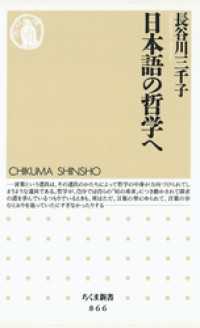
- 電子書籍
- 日本語の哲学へ ちくま新書




