内容説明
なぜ細胞の集合体である脳から自我が生まれ、感情が湧くのか。
どうして相手の心がわかるのか。脳はいかに言語を操るのか。
そもそもなぜ生命を維持できるのか。鍵は、脳がする「予測」と予測誤差の修正だ。
本書では、知覚、感情、運動から、言語、記憶、モチベーションと意思決定まで、脳が発達する原理をひもとく。
子どもの学習や障害、意識の構造も一望。
人類に残された謎である、高度な知性を獲得するしくみを解き明かす。
まえがき
第1章 脳の本質に向けて
脳科学の祖ヘルムホルツ 世界が止まって見える理由 幸運な出会いから科学の爆発へ サイバネティクス 悪魔的天才と呼ばれたフォン・ノイマン シャノンの情報理論 人間の能動性と心の発達 予測と模倣 シュレーディンガーの仮説
第2章 五感で世界を捉え、世界に働きかける
知覚・運動機能に関する脳研究の夜明け ホムンクルスの発見 知覚とは何か 脳内の階層的処理によって生まれる知覚 脳はどのように推論するのか 推論の基本――ベイズ推論 脳の推論メカニズムを探る フリストンの自由エネルギー原理 予測誤差最小化を実証する 運動制御 知覚と運動の循環 注意機能とニューロン反応の同期 視覚と運動を統合するミラーニューロン まとめ
コラム1 感覚統合――異種感覚を統合する
第3章 感情と認知
感情に関する脳研究の夜明け 感情はどのように決定されるのか外環境と内環境 内臓状態の知覚と運動 ホメオスタシスとアロスタシス アロスタシスの仕組み 内受容予測符号化 内臓感覚皮質の構造と感情 内受容感覚と自閉症 感情の発達 まとめ
第4章 発達する脳
発達・学習研究の夜明け 人間の視覚野の臨界期 ヘブ則からBCM理論へ 赤ちゃんの手腕運動 じーっと見る赤ちゃん 発達の原理 動機づけのメカニズム 滑らかな運動を司る小脳知識を書き換える赤ちゃん GABAの役割と神経発達症(発達障害)との関係 まとめ
コラム2 ヘブの洞察力
第5章 記憶と認知
記憶研究の夜明け 海馬損傷の患者 過去の記憶は海馬にはないのか エピソード記憶は多感覚である 海馬の役割 二つの発見――エピソードの予測と時系列化 記憶を再構成する 睡眠は記憶の強化と要約を行う 概念細胞の発見 場所細胞の発見 運動予測――ボールを見てバットを振る 身体化による
認知 メンタルシミュレーションの仕組み まとめ
コラム3 海馬の機能――出来事の順序を記憶し、再生する
第6章 高次脳機能――知識、言語、モチベーション
モノがわかるとは何か 二つの視覚系経路 動的概念の獲得から言語獲得へ 意図の理解 言語の基礎とブローカ失語 名詞と動詞の理解 目的語の理解 文の意味理解 チョムスキーの生成文法 予測しながら会話する モチベーション(動機づけ)とは何か 人間行動の基礎理論へ 再び注意と視線移動行動の決定とモチベーション 予測誤差とドーパミン 好奇心はどこから来るのか まとめ
第7章 意識とは何か
意識の科学 意識の神経相関 意識の芽生え ホメオスタシス感情と痛み 自己意識――自己主体感・自己所有感・自己存在感 錯覚 後付け的再構成(ポストディクション) 認知や意識の上書き メタ認知 人工知能と脳科学の接点――対照学習 まとめ
終 章 脳の本質
あとがき
参考文献
索 引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
武井 康則
bapaksejahtera
ざっく
春ドーナツ
-

- 電子書籍
- 西洋絵画入門! いわくつきの美女たち
-
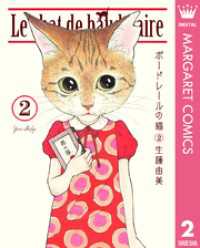
- 電子書籍
- ボードレールの猫 2 マーガレットコミ…
-
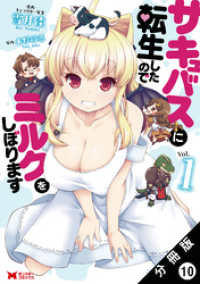
- 電子書籍
- サキュバスに転生したのでミルクをしぼり…
-
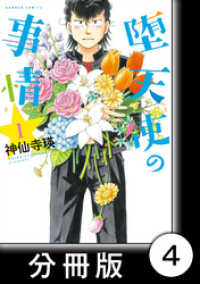
- 電子書籍
- 堕天使の事情【分冊版】 1巻 園芸部に…
-
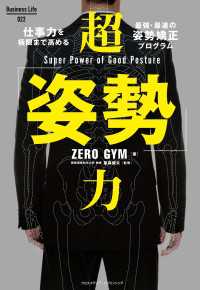
- 電子書籍
- 超「姿勢」力




