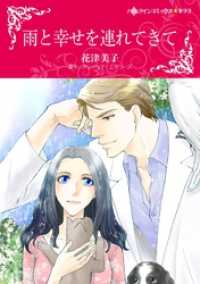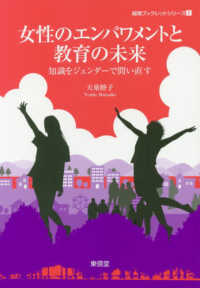内容説明
戦後日本の文学界を代表する詩人・評論家、吉本隆明。彼の詩作や思想のルーツはどこにあるのか。
文学・音楽・映画など多様な文化芸術を論じてきた筆者が、吉本隆明の文学的・思想的変遷をたどりつつ、
「マス・イメージの現在」をキーワードに、現代文化の諸相への批評を試みる。
第一部では、吉本隆明の誕生から、敗戦の経験という過酷な革命的経験を経て詠まれた詩の検討を通じて、
その裏に潜む時代性を論じるとともに、彼を取り巻くさまざまな人びととの互いに及ぼしあった影響を明らかにする。
現代短歌について論じる第二部では、近代市民社会から大衆社会へと移行するなかでの、率直な心情を綴った短歌
(俵万智・林あまり・吉村実紀恵・加藤千恵・柳澤真実など)を紹介し、その特徴を詳らかにした。
第三部は岡本かの子と太宰治の作品を検討したのち、現代の芥川賞作品を論じる。戦前から戦後直後にかけての
文学思想を概観したのち、現代の文学が持つ文化的・歴史的背景を示そうと試みる。
現代文化のさまざまな論点に踏み込んだ第四部は、映画(アンジェイ・ワイダ)や音楽(井上陽水)への、
そして写真やプロレスなど、さまざまな事物のマス・イメージを現在の文化的視点から考察した。
広範な文化芸術の諸相の変化を、現代の視点から鋭く切り込む一冊。
目次
第一部 初期・吉本隆明論
第一章 戦後詩と時代精神―吉本隆明の『固有時との対話』を読む
一 戦争から敗戦へ / 二 『固有時との対話』 / 三 『転位のための十篇』
第二章 戦後詩―吉本隆明と戦後詩
一 戦後詩とはなにか / 二 吉本隆明の戦後詩 / 三 『エリアンの手記と詩』
/ 四 戦争をくぐりぬけた思想
第三章 エリアンの手記と詩
一 『抒情の論理』 / 二 『アンドレ・ワルテルの手記と詩』 / 三 「海ははからぬ色で」
/ 四 「よるのひと時」
第四章 今氏乙治論
一 塾の先生 / 二 北村太郎「今氏先生のこと」 / 三 「海はかはらぬ色で」
第五章 色の重層
一 「色の象徴性」 / 二 「青い生と赤い死」 / 三 「青の世界」
第六章 吉本隆明と黒田喜夫
一 「灰とダイヤモンド」をめぐって / 二 黒田喜夫と吉本隆明
第七章 現代文化と『マス・イメージ論』とのかかわり
一 『マス・イメージ論』とのかかわり / 二 「変成論」について / 三 「停滞論」について
/ 四 「推進論」について / 五 「世界論」について / 六 「差異論」について
/ 七 「解体論」について / 八 「解体と縮合」―村上春樹をめぐって
/ 九 「縮合論」について
第八章 『吉本隆明代表詩選』を読む
一 三浦雅士の問題提起 / 二 「ぼくが罪を忘れないうちに」 / 三 三人の代表詩の選考
/ 四 「記号の森の伝説歌」
第二部 現代短歌論
第九章 俵万智論
はじめに
一 『サラダ記念日』 / 二 『かぜのてのひら』 / 三 『チョコレート革命』
/ 四 『プーさんの鼻』
おわりに
第一〇章 林あまり論
はじめに
一 林あまりの歌の世界 / 二 林あまりと比喩表現 / 三 歌に表現された同性愛の世界
おわりに
第一一章 吉村実紀恵論
はじめに
一 『カウントダウン』 / 二 『異邦人』
おわりに
第一二章 加藤千恵と柳澤真実
はじめに
一 加藤千恵 / 二 柳澤真実
おわりに
第三部 岡本かの子と太宰治
第一三章 岡本かの子『鶴は病みき』を読む
一 岡本かの子という文学者 / 二 岡本かの子の短歌 / 三 『鶴は病みき』という小説
/ 四 芥川龍之介と岡本かの子 / 五 五年後の芥川氏との再会
第一四章 太宰治『女の決闘』を読む
はじめに
一 オイレンベルグ『女の決闘』 / 二 太宰治『女の決闘』 / 三 太宰治『女の決闘』論
おわりに
第一五章 二つの芥川賞作品について
一 『首位の馬』高山羽根子 / 二 『彼岸花が咲く島』李琴峰
第四部 現代文化の諸相
第一六章 アンジェイ・ワイダの映画
一 「世代」(一九九四年) / 二 「地下水道」(一九五六年)
/ 三 「灰とダイヤモンド」(一九五八年) / 四 「鷲の指輪」(一九九二年)
/ 五 「カティンの森」(二〇〇七年) / 六 「大理石の男」(一九七七年)
/ 七 「鉄の男」(一九八一年) / 八 「悪霊」(一九八八年)
/ 九 「ナスターシャ」(一九九四年) / 一〇 「残像」(二〇一六年)
第一七章 井上陽水論
一 社会的評価や成功と反比例する音楽家としての自己愛
/ 二 二枚のアルバムの中にひそかに存在していた“バロック文化”
第一八章 マス・イメージの諸相
一 コンテキストと“ドラマ”の現在 / 二 議事環境と“写真”の現在
/ 三 物語と“プロレス”の現在 / 四 象徴交換と“広告”の現在