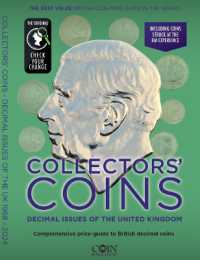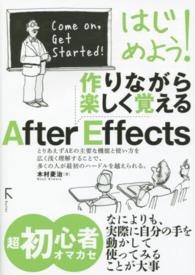内容説明
19世紀後半から20世紀初期のドイツにあって、
哲学および社会学上のさまざまな業績を残したゲオルク・ジンメル。
彼の業績や先行研究にも触れたうえで、
そのジンメルの社会学を、社会学の基礎理論として再検討・再評価する。
ジンメルの社会学、とりわけ形式社会学について、独自の検討をおこない、
その社会理論としての再評価をめぐる議論の進展に寄与する。
〈ジンメルの形式社会学は、人びとの相互作用から出発して、超個人的な存在としての
「社会」の存立機制を解明する、という理路を内包するものである。
その根底には、彼の生の哲学における「生の主観/客観への二元的分離」と、
その帰結としての諸個人の疎外という問題意識があった〉。
本書では、第1に、ジンメル形式社会学の記述の中から
超個人的な存在としての「社会」の生成に関わる論点を抽出する作業と、
第2に、そうして抽出された論点がジンメルの社会哲学的な問題意識と
いかに関連するかについて検討する作業をおこなう。
今日における、社会理論および社会分析のどのような文脈に、いかに位置づけられるのか。
得られた成果に基づき、現在の社会情況も交えて考察する。
「個人と社会の葛藤」の問題に取り組む、ジンメルの社会学をより理解するための1冊。
目次
序 章 本書の趣旨
1 ジンメル社会学に対する捉え方
2 本書の主題
(1)相互作用から「個人と社会の葛藤」へ
(2)社会の〈内部かつ外部〉の視点
(3)本書のアプローチ
3 本書の概要
第Ⅰ部 ジンメルと社会学
第1章 ジンメルの生涯と業績
1 ジンメルの生涯
2 ジンメルの時代
3 ジンメルの学問
(1)ジンメルの業績
(2)ジンメルの全体像―先行研究から―
(3)哲学と社会学
小 括
第2章 ジンメル研究の動向
1 初期の研究
2 ジンメル・ルネサンス
3 日本での受容
(1)初期の受容
(2)戦後の復活
小 括
第3章 ジンメル社会学の基本的視角
1 相互作用と生成
2 抽象とアナロジー
(1)「社会化の形式」の抽象
(2)アナロジカルな手法
3 対立物の融合
小 括
第Ⅱ部 二元論と両義性
第4章 「女性」と二元論の統一
1 ジンメルの男女論
2 ジェンダー論としての限界
3 ジンメル男女論の読み換え
(1)二元論の2つの統一
(2)2つの統一の統一
小 括
第5章 「よそ者」と第三者の視座
1 社会のアプリオリとよそ者
2 「排除された者」としてのよそ者・貧者
(1)よそ者の社会学的意義
(2)貧 者
(3)社会化の形式としての「排除」
3 内部と外部の二重性
(1)「排除」と三者関係
(2)社会の「内部」と「外部」
小 括
第6章 支配と多数決における個人と社会
1 「一人支配」からの出発
(1)「排除」と〈外在性〉
(2)「敵」あるいは「よそ者」としての支配者
(3)支配者の〈外在性〉と従属者の〈余剰性〉
2 多数決の社会学的意義
(1)「社会構成の本質」と票決の意味
(2)多数決以前としての満場一致
(3)多数決
3 支配における個人と社会
(1)3形式の検討
(2)「多数決」から「客観的な力への従属」へ
小 括
第Ⅲ部 相互作用から〈個人と社会〉へ
第7章 相互作用と「個人/社会」二元論
1 探究の方向―「抽象次元の相違」から「発生論的考察」へ―
(1)形式社会学と一般社会学
(2)多数決論における「新しい転換」
2 「超個人的な統一体」の発生
(1)三者関係論からの知見
(2)社会圏の拡大と機関の形成
(3)社会の内部と外部
3 「相互作用」から「個人/社会」へ
小 括
第8章 ジンメル社会学の「根本問題」と「超個人的な統一体」
1 個人と社会の葛藤
(1)2つの個人主義
(2)分業と「社会と個人の葛藤」
2 生の超越と超個人的な統一体
(1)形式社会学における個人
(2)生の自己疎外と理念への転換
(3)文化の悲劇
3 生の自己疎外と社会
(1)生から相互作用へ
(2)生の哲学と形式社会学における「転換」
小 括
終 章 本書の成果とその展望―「物象化論」としてのジンメル社会学―
1 本書の成果
2 ジンメルの「物象化論」
(1)物象化論への接近
(2)物象化論としての『貨幣の哲学』
3 「物象化」と「疎外」
(1)疎外論から物象化論へ
(2)問題としての「疎外」
(3)物象化のポジティブな側面
4 「個人と社会」の現在
(1)作田啓一の個人主義論
(2)現代社会の考察に向けて
付論1 三者関係論から差別の社会学へ
1 「三者関係としての差別」論
2 集団における被差別者の位置づけ
3 マジョリティの普遍化
小 括
付論2 近接性と距離―バウマン道徳論におけるジンメルの援用をめぐって―
1 バウマンの道徳論
(1)ポストモダンと道徳の再個人化
(2)近接性と距離
2 ジンメルの諸論点
(1)二者関係と三者関係
(2)他者の認識
(3)よそ者と貨幣
3 バウマンにおけるジンメルの影
(1)二人の道徳パーティ(moral party of two)
(2)第三者の出現
4 考 察
(1)二者関係/三者関係
(2)バウマン道徳論への批判と期待
あとがき
文献リスト