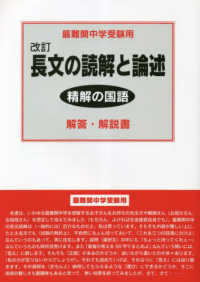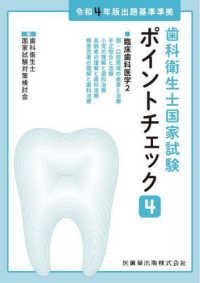内容説明
ベートーヴェン《第9》からケージ《4分33秒》へ──
〈聴くこと〉のもつ創造性をしなやかな感性でとらえた画期的音楽論!
「作曲者は、音を吐くのではなく、耳を世界にそばだてて、適切な音を探す。
作曲をするためには、人は、まず、聴く人(ホモ・アウディエンス)でなければならない」(本文より)
音楽はほんらい聴き手に多様な解釈をゆるすものであり、ひとは「耳をすます」ことによって創造者となる──
「聴くこと」のもつ創造性を高らかに謳い上げる、音楽への希望に満ちた一冊。
2012年、アメリカ芸術・文学アカデミーの終身名誉会員(日本人音楽家としては武満徹に次いで2人目)に選出され、名実ともに日本を代表する作曲家となった著者の最新音楽論。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
忽那惟次郎8世
7
この本はある理論を断定的に論じる本(理論書等の類)ではなく著書があとがきに書いているようにエッセイであり「思索の記録」というもので思索の迷宮と言ってもいい。 またウンベルト・エーコやガダマーといった美学者、哲学者の著書の理論にも沿って書かれているので それらの著書を読んでいないと理解しずらい点もある 構成はあとがきにもあるとおり 解釈二題とコーダは別として、2、3、4、5章がそれぞれ独立したテーマを展開している 荒っぽく言えば 2は「聴く人」3は作曲行為の目的 4は受容のあり方(音楽)評論行為について 2019/12/07
hr
4
近藤譲の管弦楽曲「林にて」や、フルートとピアノのための「歩く」を聴いてみて欲しいです。肩の力を抜くことを全身全霊でやっているような、不思議な感慨の残る作品で、初めて聴いた時には打ちのめされました。どんな人が、どんな精神状態でこんな音楽を書くのか知りたくて読み進めるも、人となりは分からない。創作の秘密が保持されて良かったのかも。それでも、これらの音楽は、何らかの主張と思考で書かれたようだ。それを感じ取った上で、また聴き直してみます。2016/02/07
植岡藍
1
ベートーヴェンの「第九」を第一主題、ケージの「四分三三秒」を第二主題とすると四楽章形式の交響曲のような本だった。この本で繰り返し思索が迫ろうとするのは音楽とは何かという事で、それ自体やはり音楽には何か音響以上のものがあると信じる作者の姿勢があるように思う。この本自体は静寂の中で読みたいが、読み終えた今、聴くことについて全く違う世界が広がるような気もしている。2025/03/22
勇03
0
図書館本。2014/03/29
-

- 電子書籍
- 転生妻は優しくない 第49話 真実【タ…