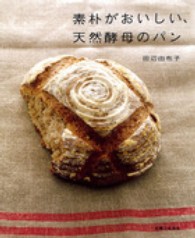内容説明
世界は味で動いていた。香辛料(スパイス)から砂糖、そしてうま味調味料へといたる「味」の移り変わりは、資本主義が誕生し、ヨーロッパが覇権を握るプロセスと軌を一にする。本書では、ウォーラーステインの「近代世界システム」を参照し、さらにポメランツが提唱した「大分岐」論以降のさまざまの研究成果も踏まえつつ、「諸島」に焦点を当てることで、世界史の興亡を新しく描き直す。
※カバー画像が異なる場合があります。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
136
欧州の大航海時代は香辛料や砂糖を求めて始まった。つまり旨いものを食べたいという欲求が歴史を動かし、世界的な交易ネットワークの形成と交易を握ることによる覇権国家誕生につながり、今日に至る歴史を築いたとする。嗜好品を輸入するためには輸出品が必要で、交易のための工業製品による利潤が資本主義の基礎となり、技術力の底上げにつながる連鎖反応を引き起こしていった。その意味で世界史は確かに味覚が生んだものであり、日常に食べるカレーや中華の由来を考えれば納得できる。つまり地産地消など歴史的には最初からあり得ないことなのか。2024/12/26
skunk_c
76
一応乳香や没薬などにも触れられているが、本線は「大航海時代」につながる香辛料と、それが砂糖に取って代わる、いわゆる世界システム論でいう世界経済の展開の原動力についてのざっくりした入門書。ただし砂糖に関しては川北稔の『砂糖の世界史』の方が圧倒的に面白いし有用と思った。著者は18世紀後半に始まるイギリスの第1次産業革命より19世紀終盤に始まる第2次産業革命を重視している。そのひとつの証しとして化学工業の発展と味の素などのうまみ調味料を取り上げるがかなり無理筋な展開を感じた。やはり新書版では論じきれないのでは。2025/01/31
1.3manen
58
O図書館。砂糖はウォーラーステインの世界システム形成期に最重要な商品(11頁)。香辛料は東南アジアが生産(15頁)。甘さと辛さが入り乱れた時代。アラビア半島の香料の道(36頁)の地図は初めて拝見した。世界史探究とかで出てくるのかも? 同様に、初めて拝見した中世の香料貿易ルート(50頁)は、コショウ、シナモン、ジンジャー、ナツメグ、クローヴの位置づけがなんとなくわかる。香辛料を薬剤師が扱っていたというから、香辛料は健康にいいんだろう。ヒポクラテスも認めていたくらいだから(56頁)。2025/12/28
よっち
31
食の多様性はいかにして生まれたのか。東南アジアとカリブ海を目指して拡大したヨーロッパ経済史の視点から、資本主義の起源と展開に迫る1冊。資本主義が誕生してヨーロッパが覇権を握るプロセスと、香辛料から砂糖、そしてうま味調味料へといたる「味」の移り変わり。古代・中世におけるインド・アフリカの香辛料貿易ネットワークの構築、大航海時代になってからの香辛料貿易の変化、香辛料から砂糖へと比重が移っていった経緯と資本主義経済、産業革命の果たした役割やそこから現代に至るまでにさらにどう変わっていったのか興味深かったですね。2024/12/08
ようはん
26
大まかにいえば大航海時代に至るまでの香辛料貿易の歴史とその後の植民地のプランテーションによる砂糖生産が近代以降の資本主義を生み出したという流れ。香辛料も砂糖も物流システムも自分を含めて今現在の多くの日本人が享受しているが、その流れでサトウキビ生産に駆り出された黒人奴隷等の多くの負の歴史があったのも忘れてはならない2025/02/08