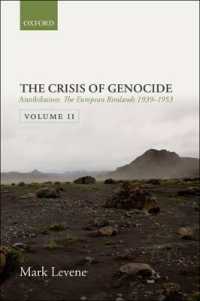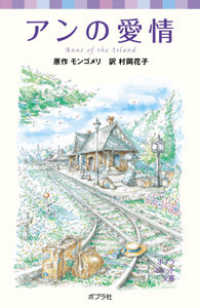内容説明
AIに街は管理できない!
IT化社会に一石を投じる渾身の都市論
都市はコンピュータではない。AIやIoT、データ分析による効率化からこぼれ落ちるものにこそ、人が交わる公共空間としての都市の本質があるのだ。アメリカの人類学者が示す、まちづくり、そして図書館などのコモンズ(共有空間)をめぐる新たなビジョン。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐倉
20
コンピューター、プラットフォーム、ダッシュボード。多くの情報が集まる都市はこうした情報媒体に例えられ、実際にテック企業が都市開発を担う例は数多い。だが都市はこれらのように特定の個人や企業が利益や目的を追求するために存在しているのではない。多様なコミュニティを内包するために単純化する情報処理では不可視化するものも多く出てくる。安易にテクノロジーに例えて企業に開発を任せるのではなく、切り捨てられる情報(人も含む)を拾い上げて公共性があり議論が出来る場=都市を作り上げるにはどうすればいいのか…という題材の1冊。2025/09/04
バーニング
8
タイトルでやや敬遠してたがいい評判を多く聞いたので読んだ本。原タイトルのほうが分かりやすくて好みかな。スマートシティが目指す都市データのアルゴリズム化がなぜうまくいかないのかを詳しく説明した上で、そうではない方向性での都市設計を構想する一冊。第三章で図書館の役割が何度も強調されていたのは映画『ニューヨーク公共図書館』を思い出すし、その後のケア論は近年のケアの倫理論とも接続出来そう。日本ではトヨタのウーブンシティが本格的に稼働を始めたが楽観しないほうがいいかな。そういうわけで何かと示唆が多い一冊だった。2025/03/27
Pustota
8
データを集約して一覧することで都市の問題解決を図っても、データ作成や分析のバイアスは多くのものを取りこぼす。都市はデータ化できない知恵で溢れている。原題はA City Is Not a Computer: Other Urban Intelligences. これが示すとおり、スマートシティが失敗する理由を掘り下げるより、別の視点で都市にまつわる知をとらえる方法を模索した内容。自分にもスマートな問題解決への憧れ(整然さと秩序への強烈な欲望)に共感してしまうところがあるので、戒めになる内容だった。2025/01/20
iwtn_
5
タイトルの通りの疑問に対する答えを求めて購入。しかし、原題はかなり違うし、中身も邦題のようなものではなく、従来、及び、昨今のテクノロジスト達に対する批判を都市という観点からまとめたもの、という感じ。正確には、まだ「スマート」な都市はできていないのかもしれない。情報は現実の影に過ぎず、理論によるトップダウンに構築できるものではない。が、特に目新しい話でもなく、西洋特有の頭でっかち批判ということで、そんなに読むべきものでもない、とも思った。生態学を参考にするのはいいけど、それはただ複雑だって言ってるだけでは?2024/11/24
chiro
3
今もあるのかもしれないけど過疎の市域でセントラルシティ構想というものがあり、行政サービスの効率化を目指して進めようとしたが住民の賛意を得られずに頓挫している。この著作でのスマートシティ構想はそれとは多少狙いは異なってはいるがAIなどのテクノロジーを盲信するが如く進められることへの警鐘を鳴らしている意味では血いじるところがあると思うが、我が国のそれは不動産大手の収益を優先させるもので行政の怠慢と構想力のなさはそれ以前の問題でなんとももどかしい。2025/02/01