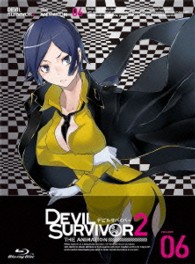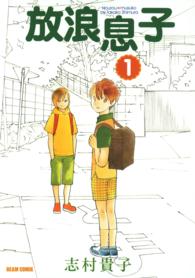- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
住宅ローンや消費者金融、銀行預金に個人向け国債。私たちの身の回りには「金利」があふれている。「低金利だから円安になる」「金利を上げると不景気になる」といったニュースも、毎日のように聞こえてくる。これらの「金利」はお互いにどんな関係があって、それぞれの金利はなぜ/どうやって決まるのか。金利が動くと私たちの生活に何が起きるのか。金融政策の第一人者が、身近な事例をもとに根本から解き明かす。お金と社会を見る目が変わる、実践的経済学の書。
目次
第一章 金利を上げ下げする力はどこから来るのか/1 プロローグ/2 「金利」とは何か・どう決まるのか/「もうけ」の対価としての金利/中央銀行は金利を「なぜ」・「どのように」動かすのか/中央銀行は「物価安定」のために金利を動かす/金利の上げ下げに人々が反応すれば経済活動が調節できる/中央銀行が金利を動かす伝統的出発点は「資金決済」/日本銀行は貸し倒れのないコール市場の超短期金利を動かす/〈コラム〉コール市場で安易に貸し倒れを起こさせてはいけない/金利を上げ下げする伝統的手段は国債などを売買する公開市場操作/量的緩和後は日本銀行が払う預金金利水準で金利を誘導/3 いろいろな金利はどう関連しているのか/満期の異なる金利の関係は投資家の期待(予想)に左右されるはず/〈コラム〉国債はどういう意味で「安全資産」なのか/中央銀行は市場参加者の期待(予想)に働きかけて満期の長い金利へ影響を与える/金利が変動することで生じるリスクの対価としてのリスク・プレミアムもある/イールドカーブは満期の異なる金利の関係を示している/異次元緩和のイールドカーブ・コントロールは例外的政策/中央銀行の金融政策は金利体系を上げ下げしたりイールドの傾きを変えたりする/完全雇用と物価安定をもたらす金利(自然利子率)と金融政策で決まる金利の関係/自然利子率から長期間・大幅に離れた金利誘導はできない/補論 金利政策の理論的支柱としての現代マクロ経済学/第二章 金利はなぜ「特殊な価格」なのか/1 ミクロ経済学からみた金利の特殊性/貸し倒れリスクの存在/缶ビールを購入する取引と消費者金融取引の違い/金利の価格機能に欠陥をもたらす「レモン問題」/「隠された情報」が欠陥品を跋扈させる(逆選択)/隠された行動で貸し手を欺く(モラルハザード)/ヒトに「明日の自分の行動」を見誤らせる「現在バイアス」/自分をコントロールできなくなるギャンブル依存症/〈コラム〉水原一平元通訳とギャンブル依存症/2 家計にとっての金利はどう決まっているか/貸し倒れリスクのある借り手の金利には信用リスク・プレミアムが上乗せされる/借入金利を左右する要素は消費者金融と住宅ローンで大きく異なる/金利が家計に影響を与える経路/金利政策がもたらす円安・円高は企業や家計に大きな影響を与える/補論 社会規範からみた金利の位置づけ/第三章 消費者金融の金利は高すぎるのか低すぎるのか/1 消費者金融の金利/政策金利と消費者金融の金利はほとんど関係がない/消費者金融の金利は貸し倒れリスクと金利上限規制に左右される/一昔前に比べ消費者金融は身近になった/「サラ金」への恐怖感が強かった時代、情報は限られていた/「ウマル氏」の体当たり調査/スマホやパソコンを使った21世紀の消費者金融契約手続きは簡単/信用判定モデルにより即時に審査され合格すればすぐ出金できる/2 苛酷な取り立てがもたらした社会規範の変化/ギリシア・ローマ時代の有力な借金取り立て手段は債務者を奴隷として売ること/サラ金が手っ取り早い借金回収手段として生命保険を利用した、という疑い/金融庁が団信利用実態を調査した結果、サラ金への疑念は強まった/金融庁の是正指導に対してサラ金は反発し団信を解約/社会的批判の強まりはグレーゾーン金利是正の追い風になった/グレーゾーン金利廃止を支持した世論と最高裁/3 グレーゾーン金利解消の副作用は大きかったか? /グレーゾーン金利解消で消費者金融会社は一部の借り手を締め出す? /ヤミ金を跋扈させるのではないか、との懸念/むしろ上限金利引き上げや金利自由化が必要という意見/政府は世論を背景にグレーゾーン金利解消を決断/グレーゾーン金利を解消した改正貸金業法成立後、多重債務問題は緩和した/懸念材料は特殊詐欺・闇バイトが増えていること/補論 高利だが安全な質屋金融はなぜ衰退したのか/第四章 住宅ローンの金利は上がるのか下がるのか/1 日本における住宅ローン金利の選択肢/日本の住宅ローン金利には基本的に三つの選択肢がある/住宅ローンの選択基準はメリットとリスクの比較/メリットもリスクも大きい変動金利型/変動金利型を選択する場合には経済的余力があることが望ましい/住宅ローンの選択状況は変動金利型に傾斜してきた/国際的にみると日本の家計は変動金利型に大きく偏っている/金利選択は自己責任、結果は借り手に跳ね返る/2 金利リスクが破滅的結果をもたらしたサブプライム・ローン問題/サブプライム・ローンとは/サブプライム・ローンの矛盾を先送りすることに成功した返済負担後倒し方式/固定金利・元利均等分割返済の返済額は大きい/変動金利元本後払いローンの当初返済額はきわめて小さい/元本の返済が始まる時期が来ると状況は一変する/問題の表面化を遅らせた住宅価格バブル/バブル崩壊により問題は一気に深刻化/「システミック・リスク」までもが表面化した2008年の国際金融危機/国際金融危機を深刻化させた疑心暗鬼/3 教訓──住宅ローンで家計の破綻を避けるために必要なこと/サブプライム・ローンの借り手はリスクを認識していなかった/日本の低所得家計は金利リスクを避け固定金利ローンを選ぶ割合が多いらしい/日本の家計の金利リスクへの理解は不十分かもしれない/補論 ねずみ講・レッドライニング・略奪的貸出/第五章 金利はなぜ円高・円安を起こすのか/1 固定相場の時代/変動相場制を知るには固定相場制時代を振り返るとよい/固定相場制の終焉は突然やってきた/固定相場制で資金が自由に移動できれば日本の金利も米国で決まる/金利裁定取引には金利差を破壊する威力がある/〈コラム〉国際金融のトリレンマ/2 変動相場制と価格裁定・金利裁定/変動相場制に移行したとき、為替レートがどう決まるかわかっていなかった/各国の物価が為替レートを決めると考えた購買力平価説/購買力平価説の根拠は価格裁定取引で説明できる/購買力平価説を応用しているビッグマック指数/〈コラム〉ビッグマック指数拡張の試み/購買力平価で決まるなら為替レートは安定化するはず、と期待されていた/〈コラム〉消費者物価指数は価格裁定の基礎と考えてよいのか? /大きく変動しはじめた実質為替レートと「PPPパズル」/ふたたび関心を集めた金利裁定/為替レートはオーバーシュートする? /一時大きな関心を集めた為替リスク・プレミアムの影響/グローバリゼーションで為替リスクの影響は低下したらしい/対外直接投資が大きく増えたことも為替レートに影響している/3 為替レートの予測はなぜ当たらないのか/理論モデルはランダム・ウォークに勝てない/〈コラム〉ランダム・ウォーク・モデルの使い道/為替レートの「アンカー」はなにか/「ニュース」こそが為替レートを動かす/「美人投票原理」も作用してしまう/「自己実現的予言」が起きる可能性/美人投票原理からみたソロス・チャートの説明力の変遷/金利と為替レートの関係の要約/4 為替レートと金利をめぐる不都合な真実/円安についての政府の懸念/「日本にとって円安はプラス」という議論の落とし穴/円安には輸出企業を潤し家計を圧迫する強い「再分配効果」がある/〈コラム〉円安の家計負担について細かく積み上げて計算した事例/「受益は輸出企業へ・損失は家計へ」という構造は固定化している/超低金利持続の不都合な真実は輸出企業へのサポートと家計の圧迫の持続/金利政策は分配問題にどうかかわるべきか/円安のもうひとつの不都合な真実は、競争力や成長に十分つながっていないこと/補論 円安・円高は将来の日本の人口構成を変える/エピローグ──金利引き上げと株価暴落/あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
KAZOO
特盛
Kooya
読人