内容説明
分断の時代に改めて問う 「比較」研究の叡智
19世紀フランスで生まれた学問「比較文学」は、130年を経て文化・芸術をも対象として発展してきた。その基本概念から最新の研究ジャンルまで幅広いテーマを解説した、比較研究の過去・現在・未来を「読む事典」であり、さまざまな書物への導きとなる一冊。
【主要目次】
本書の使い方
総 説
第Ⅰ部 比較研究の理論、重要概念
[歴史・概念]
比較/比較文学/世界文学/「文学理論」と比較文学/フランス派とアメリカ派/間テクスト性/近代・近代性(modernity)/比較史/ナショナリズムと国民文学/比較「文学史」/越境文学/普遍
[方法]
エクスプリカシオン・ド・テクスト (explication de texte)/影響・受容研究/対比研究/たとえ/物語論(ナラトロジー)/蔵書研究/比較文学と定期刊行物(新聞・雑誌)/カノン形成、脱カノン/創作と言語越境/再話研究
[翻訳]
翻訳/翻訳文学/翻案・改作/訳語/文化の翻訳/通訳/重訳/翻訳者の使命/映像翻訳/機械翻訳/自己翻訳
[ジャンル別比較文学]
比較詩学/比較演劇/小説の勃興/能と謡曲/近代詩/詩のモダニズム/幻想文学/探偵小説(ミステリ)/児童文学/ネイチャーライティング(自然文学)/文学と政治/神話・伝説・伝承・民話・説話/動物文学/自伝・自伝文学/文学賞・ノーベル文学賞
[比較芸術]
比較芸術/クロスジャンル/アダプテーション論/ジャポニスム/文学と絵画/文学と写真/文学と映画/挿絵・イラストレーション/文学と音楽/美術と建築/スポーツとアート/国際的な合作や共同制作/漫画・アニメ/舞踊の越境/楽器の越境
[比較文化]
比較文化/異文化理解/ポストコロニアル/ジェンダーとフェミニズム、クィア批評/階級/言語相対論と文化相対主義/文化交流と文化交渉/文明の衝突とグローバリゼーション/戦争と占領/留学(体験)/亡命、ディアスポラ/中東・西アジア/他者論、異人論/比較日本文化論/日本人論/外地(体験)/エスペラント
[東アジアにおける比較文学比較文化]
韓国/中国/台湾/東アジアのモダニズム/漢文学と日本(前近代)/植民地(満洲)の日本語文芸/在日文学/東アジア藝術における西欧
第Ⅱ部 比較研究の読書案内――比較文学・比較芸術・比較文化を深く知るために
比較文学への道/初めて学ぶ人の本棚/文庫・新書の本棚/もっと読みたい人の本棚/より深く研究したい人の本棚
第Ⅲ部 専門研究への道しるべ
1比較研究者になるために/2比較文学関連学会(国内)/3国際比較文学会(ICLA)/4フランスの学校教育とexplication de texte/5世界と日本の比較文学雑誌/6各国の比較文学研究史 フランス アメリカ カナダ ロシア 韓国 中国/7比較文学比較文化の教育現場と将来/8オーラルヒストリー:比較文学者に聞く
事項別参考文献
人名索引
著者一覧
【本書「総説」より】
例えば夏目漱石の作品は、近代日本とか日本語だけに縛られた存在ではない。 ――(中略)―― 漱石が近代日本の急速な近代化・西欧化について思索を深めていった軌跡をたどる一方で、日本が併合した植民地に対する漱石の立ち位置はどのようであったのかを考えてみる。そんなところから、比較文化的な視野が拓けてくる。漱石は日本語でのみ著述する作家であったが、例えば彼と同時代の、日本語と韓国語の双方を用いて書いた作家を、私たちはどのように読むことができるのだろうか。このように比較文学の方法は、文学のみならず、芸術や文化を対象とする時にも応用することができる。ひいては、人間や社会が孤立し自閉した存在ではなく、様々な要素が混淆して共存する存在でもあると気づく第一歩にもなる。
本書はこうした理念にもとづいて、比較文学・比較芸術・比較文化に関して日本で初めて編まれたハンドブックである。このハンドブックは研究と読書の海に乗り出すための航海の指針であり、随伴者(コンパニオン)でもある。今回、数十名に及ぶ専門家たちがここに集結し、一般読者や初学者に向けて、さらには研究者の参照にも耐えうるように、平易で深く、読んで面白い「読む事典」にもなることを心がけて執筆した。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
不見木 叫
小谷野敦
すいか
-
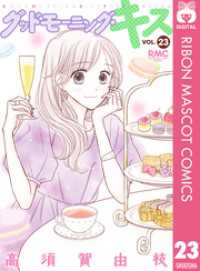
- 電子書籍
- グッドモーニング・キス 23 りぼんマ…
-
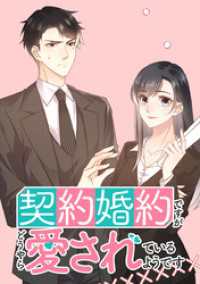
- 電子書籍
- 契約婚約ですがどうやら愛されているよう…
-

- 電子書籍
- このヤクザ 初恋を貪る獣(分冊版) 【…
-

- 電子書籍
- 私の押しカップルは絶対だ!【タテスク】…
-
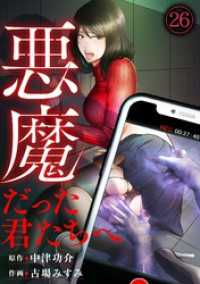
- 電子書籍
- 悪魔だった君たちへ(26) DEDEDE




