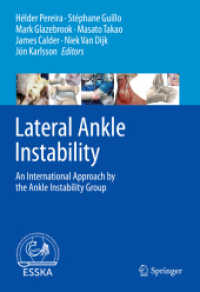内容説明
現在約1.3億人の日本の人口は,2040年代に1億人を割るとされる.そしてその時日本は65歳以上の高齢者が4割の超高齢国となる──.「少子化対策」が叫ばれながら,なぜ日本の出生率は下がり続けるのか? そのカギは景気後退と雇用の劣化に翻弄された団塊ジュニアの未婚化にあった.一貫して少子化,子育てを研究してきた著者による「少子化対策失敗の歴史」と渾身の対抗策.
目次
はじめに
どんどん減っていく現役人口/“溶けない氷河”世代を社会に組み戻す
第1章 少産多死ニッポン 人口が減ると何が起こる?
日本は少産多死の国/毎年五〇〇の学校が閉校している/合計特殊出生率一・四四で何が起こるか/問題は生産年齢人口 一・四人の現役で一人の高齢者を支える日/サービスもセーフティネットも成立しなくなる/もうミカンは食べられない?/水道事業は維持できるか/九〇歳はめでたくない? いまや約二一九万人/高齢者四割社会は未体験ゾーン/すでに地方では急速な人口減少が始まっている/生産年齢人口は激減していく/二〇四〇年,三人に一人が七五歳以上になる秋田県/出生数ゼロ地域の出現/無子高齢化は「今ここにある危機」
第2章 なぜこんなにも少子化が進むのか
なぜ少子化が進んでいるのか──直接的な三つの要因/分水嶺は団塊ジュニアの未婚化/一生結婚しない人たち 生涯未婚率の上昇/晩婚化・晩産化はどんどん進む/ワンオペ育児とダブルケア/夫婦の平均子ども数の低下/いずれは結婚したいけれど……/コミュニケーション能力と経済力が必要/結婚・出産はぜいたく品?/若者の非正規化が未婚化を招く/非正規雇用の結婚へのハンディは女性にも/結婚の形が自由になればいいのか?
第3章 少子化対策失敗の歴史――混迷の霧の中を進む日本
人口が増えては困る時代があった/一九七三年まで続いた移民送り出し事業/一九六〇年代からすでに若年人口は減少していた/一九六九年には生産年齢人口減が予測されていた/第二次ベビーブームの到来と「成長の限界」/一九七〇~九〇年代は人口ボーナスの時代/日本型福祉社会と「ジャパン・アズ・ナンバーワン」 成功体験の足かせ/「一・五七」はなぜショックだったのか/「産めよ殖やせよ」の呪縛で及び腰/少子化という「女子どもの問題」は後回し/広がらなかった危機感/なぜ効果を上げられなかったのか 小出しの施策/変わらない政治家の姿勢/担当職員ですら子育て支援には無理解/結婚・出産は「自己責任」か/次世代育成こそが高齢者福祉を支えるはずなのに/「子育てなんか他人事」のツケ/政治の混乱,リーマンショック/司令塔がいない少子化対策・子育て支援/世代再生産の最後のチャンスを逃す/霧の中を人口減少へと進み続ける日本
第4章 第三次ベビーブームは来なかった 「捨てられた世代」の不幸と日本の不運
保育園だけが子どもの問題ではない/そして,第三次ベビーブームは来なかった/破綻した「学校と職業の接続」/企業は生き残り,国は滅びる──少子化を招いた「合成の誤謬」/「パラサイト」「ひきこもり」が覆い隠した雇用の劣化/非正規にしかなれない現実/見えない「もう一つの社会」/間に合わなかった支援/日本の不運 失われた二〇年と団塊ジュニア,そしてポスト団塊ジュニア/学校卒業時の景気で人生が決まる/溶けない氷河 残り続ける世代効果/親と子の世代が仕事を奪い合う皮肉な構造/次世代と仕事を分かち合ったオランダ/片働き社会から脱却できなかった日本/高卒者の場合 世帯の経済力によるハンディ/進路ルートから漏れていく若者たち
第5章 若者への就労支援と貧困対策こそ少子化対策である――包括的な支援が日本の未来をつくる
人口減少は止められるのか/婚活支援より先にやるべきこと/結婚したいけれど…… ずれる理想と予定/男性の収入 女性の期待とその現実/男性の賃金は低下し続けてきた/子育て世代の家計も厳しい/奨学金が少子化を招く?/いま必要なのは人生前半への支援/就労支援と貧困対策こそ少子化対策/緩少子化と超少子化の国は何が違う?/家事・育児を一緒に担う共働きの方が総労働時間が増える/人材をムダにするな 放置される未婚無業女性/深刻化する八〇五〇問題/必死で働いて貧乏になった「安くておいしい日本」の限界/「日本は何もかもが安い」/競争原理と地方創生のどちらを取るのか?/もう新しいタワマンもダムも道路もいらない/社会のOSを変えよう 総合的な社会保障の再設計を/外国人労働者はモノではなく人間である/受け入れ体制をつくっていく覚悟と努力/体制整備のコストは行政に転嫁される/移民は人口問題を解決するか?
〈対談〉それでも未来をつくっていくために 常見陽平×前田正子
「処置」しかなかった日本/構造的な変化であることを理解できなかった/「就職氷河期」という言葉の初出は一九九二年/ほんとうに凍り付いたのは二〇〇〇年代前半,ポスト団塊ジュニアを直撃/フリーターはほんとうに「究極の仕事人」か/みんなでこの国を貧しくした/日本は世界の中堅中小企業/国民に目を向けていない政治/誰もが付加価値を生み出せる産業で働けるわけではない/「若者を耐えろ」/「日本人再生プラン」を/希望格差,文化格差が広がる若年層/少子化対策・若年支援庁をつくれ/行政は仕事の再配分を/「労働とは何か」が問い直されなければならない/子どもにどのような未来を手渡すのか
おわりに
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おさむ
katoyann
謙信公
うさうさ
ふじ
-

- 電子書籍
- 不貞の教室 6話「笑顔の裏で牙をむく」…