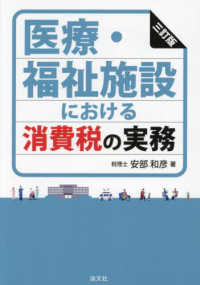内容説明
矢継ぎ早に「流星群」のように降り続く「教育改革」に負けない学校になるためには、どうしたらいいのか。
文部科学省と広島県教育委員会で20年、教育改革をし続けた著者が問う、学校をもっともっと、「自由な場」にするための書。
巻末対談 岩瀬直樹(軽井沢風越学園校長)氏との対談を収録!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Hachi_bee
2
岩瀬直樹さんとの対談部分に全てが集約されていると思う。 p.124辺りから出てくる「評価」は「evaluate」寄りか?指導と評価の一体化の文脈では「assess」の意味だと思うが、ミシガン大学的には違うのか?p.150で紹介されているティーチングマシンの様な「個別最適」は、筆者も否定している様に読み取ったが合っているか?p.187の盾の話は学校組織や教員自身に「盾」となることを求めているように読めた。2024/02/18
BECCHI
2
トップダウンでなく、ボトムアップ。現場で授業を変えていくことで、上を変えていく。今までは、上のシステムが変わらない限り本当の意味で子どもたち主体の学びということは不可能と思っていた。もちろん、お金の面、人事の面などなど上がやらなければならないことはある。でも、現場でもできることはあるし、むしろ現場が変わるように自分ができることをすれば良いのだと思った。そこにはやはり教師の学びだ。教師がどれだけ学びに夢中になり、お互いの個性を尊重し合い、子どもたちの成長に寄り添うことができるかだ。やれることをやろう!2024/01/05
そうむ
1
現状認識や各論に同意しづらい部分はあるものの、大きな方向性としては共感できました。同意しづらいと感じるのも自分の狭さと受け止め、視野を広げていきたいとは思いました。2024/01/19
松村 英治
1
うーん。タイトルと比べて何か期待外れというか、何を言いたいのかよく分からなかった。2024/01/13
ラモンキー
0
評論家然とせず教育を語るために持っておきたいマインドの種を蒔いてくれる本だった。 教員に限らず、まず自身がアクティブラーナーとなり、アートとサイエンスの両要素を備えながら実践・改善し続ける人が増えていくと、社会全体が教育の担い手として機能していくのだろうなと感じた。 また、巻末対談の「一旦乗っかる」姿勢は、ビジネス現場でも人間関係でも大事にしたい。2024/02/12