内容説明
髪切虫(かみきりむし)、雪女、姥(うば)が火(ひ)…。人知を超えたさまざまな怪異を引き起こす妖怪。中世まではごく限られた種類にとどまっていた妖怪が、江戸時代に急激に増加したのはなぜか。その背景には「怪異」の変容と、新たな文芸である俳諧の興隆があった。諸国で怪談・奇談を集め、妖怪を創造した俳人たちの情報ネットワークから、江戸の〝妖怪爆発〟の謎に迫る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
118
水木しげるの妖怪図鑑を読んだ世代としては、様々な妖怪がイラスト入りで名前と特徴が紹介されるのを疑ったことはない。しかし妖怪に名前が付けられたのは江戸時代以降で、幕府の政策と俳諧ネットワークにより爆発的に広まったとは想像もしなかった。家康の合理主義が怪異と災厄の結びつきを遮断した後に、俳諧の題材として妖怪が取り上げられて各地で増えたものが、当時のSNSというべき俳人たちのつながりで集成され一般化したのだ。ネット社会でのフェイクニュース拡散と同じ理屈とすれば、日本人は3世紀前に現代と同じ状況を体験したわけか。2024/11/19
さとうしん
18
江戸時代の妖怪の(認知と命名の)急増は、江戸幕府がそれまでの政府と違って危機管理としての怪異には関知しないという方針を採ったことや怪異が知的好奇心の対象となったことが影響し、とりわけ俳人が大きな役割を担ったことを指摘する。松尾芭蕉や西鶴、蕪村ら著名な俳人も妖怪の命名に関わり、芭蕉をモデルとしたと見られる妖怪も存在するという。怪異論として意外背生のある議論になっているが、俳諧論としても意外であることだろう。江戸時代の俳諧を研究している人の評価も聞きたいところ。2024/08/24
そうたそ
11
★★★☆☆ 妖怪好きとしては興味を惹かれてしまうタイトル。妖怪が広まった原因として、江戸時代の俳諧ネットワークがあったという考えが面白い。俳諧ネットワークは今でいうならSNS的存在でもあったのだと。タイトルにある"名づける"というには、やや違う内容だとも思ったが、存在自体は中世からあった妖怪がなぜ江戸時代から爆発的に広まり、個々の妖怪がその名を得ていったのか、著者の説も交えながら丁寧に検証されており読み応えある一冊だった。昨今の妖怪ブームも当時の俳諧があってこそか。2024/09/29
しゅー
10
★★妖怪は日本古来の伝承と錯覚しがちだが、今のようなバラエティを獲得したのは江戸時代なのである。それまでは朝廷を中心とした「怪異にもとづく危機管理システム」とでも言うべきものが存在した。多種多様な怪異の裏には鬼、天狗など数の限られた本体が存在し、それを突き止めて対策を打つと言う仕組みである。しかし徳川幕府は凶事の先触れとしての怪異を否定した。その結果、怪異は無害なものとして庶民の博物学的な興味の対象へとなり下がる。そこに当時のSNSである俳諧のネットワークが組み合わさり、妖怪のカンブリア爆発が起きたのだ。2024/12/21
蒼田 友
9
まさか俳諧と妖怪が結びつくとは。俳諧には興味がないという著者に、苦労しながらも執筆をしてくれて感謝する。自分の全く知らぬところからのアプローチが新鮮で面白かった。そしてアマビエにも言及されており、2020年の話なのだがそういえば「すでにどこから広まったのか」曖昧である。2024/12/14
-
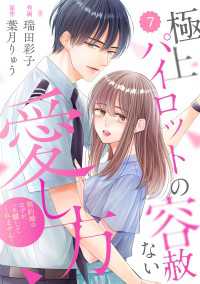
- 電子書籍
- comic Berry's 極上パイロ…
-

- 電子書籍
- ハンコを押してください【タテヨミ】第4…
-
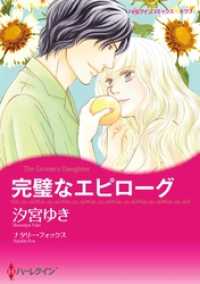
- 電子書籍
- 完璧なエピローグ【分冊】 5巻 ハーレ…
-
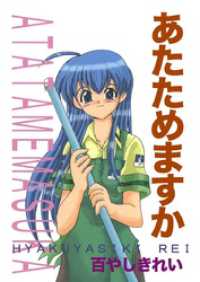
- 電子書籍
- あたためますか
-
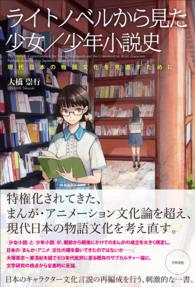
- 電子書籍
- ライトノベルから見た少女/少年小説史 …




