内容説明
〈少女小説〉と〈少年小説〉が、
戦前から戦後にかけてのまんがの成立を大きく規定し、
日本の「まんが・アニメ」文化の礎を築いてきたのではないか―。
ライトノベルを起点に〈少女小説〉〈少年小説〉に戻り、日本の物語文化を見直す。
特権化されてきた、まんが・アニメーション文化論を超え、現代日本の物語文化を見直すとき、そこにはどんな問題が立ち上がってくるのだろうか。
これまであまり行われてこなかった、まんが・アニメと小説とがどのようにつながるのかという問題を、〈物語文化〉という問題意識から考える文芸批評。
大塚英志~東浩紀を経てゼロ年代批評に至る既存のサブカルチャー論に、文学研究の視点から全面的に反論。日本のキャラクター文化言説の再編成を行う、刺激的な書。
【......これからの私たちがまんがやアニメーション、ライトノベルについて語るときに求められるのは、それぞれのメディアを「特殊」な文化として囲いこみ、それぞれのメディアにおいて作り出されただけを限定的に論じるというあり方ではないはずである。むしろ、日本のまんが文化、アニメーション文化、そしてそこに加わったライトノベルという媒体、その他日本語によって作られている〈物語〉を伴ったさまざまな文化全体の中で、それぞれがどのように位置づけられるかということを考えていく視点が必要である。
このような視点のあり方を、筆者は〈現代日本の物語文化〉についての考察と称している。......】......本書第三章より
目次
はじめに
一般文芸のライトノベル化という現象を前にして
「まんが・アニメ」文化は、「おたく」文化として特権化されてきた
そもそも「おたく」文化とそれ以外とのあいだに、本当に距離はあったのか?
「まんが・アニメ」文化の礎を築いたのは、〈少女小説〉〈少年小説〉ではないか
ライトノベルを起点に日本の物語文化を見渡す
第1章●ライトノベルとキャラクター
ライトノベルの現在
一般文芸のライトノベル化
「ライトノベル」は定義可能か
一般的すぎた東浩紀の「データベース理論」
〈文学史〉としての「リアリズム」
リアリズムという幻想
本書の目的―〈物語文化〉を見直す
「ライトノベル」とは
「ジャンル小説」としてのライトノベル
「ジャンル外」作品群としての少女向けレーベル
「ライトノベル」一九九〇年「誕生」説について
(1) ネット上に見られる情報共有のあり方
(2) 「ライトノベル」という用語の「誕生」
(3) 普及しなかった「ライトノベル」
(4) 「ひとくくり」にすることの是非
a 性別隔離文化
b ファンタジーブームとTRPG
ほか
- 評価
Piichanの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひめありす@灯れ松明の火
よっち
ゆかーん
ヤギ郎
サイバーパンツ
-
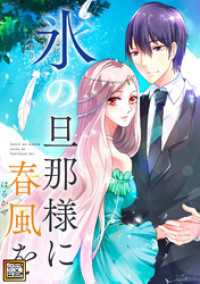
- 電子書籍
- 氷の旦那様に春風を【タテヨミ】(23)…
-

- 電子書籍
- 辻占売(分冊版) 【第40話】
-

- 電子書籍
- オリンピックと鉄道 - 新幹線だけじゃ…
-

- 電子書籍
- 「こちら秘書室」公認 接待の手土産 2…
-

- 電子書籍
- サモナーさんが行く I 〈上〉 オーバ…




