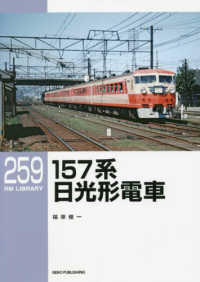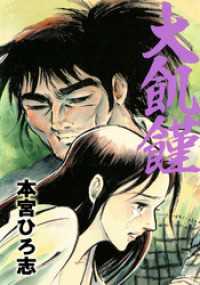- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
落合陽一氏 佐渡島庸平氏 推薦!
AIが「答え」を出す時代に
思考の主導権を取り戻す
アルゴリズムが誘導する世界を
「問う力」で切りひらく
編集工学に基づく知的創造のプロセス
私は私でなく、私でなくもない、
そんな言葉が響く編集の洞穴の入り口である.
――落合陽一氏
“「問う」ということはつまり、「いつもの私」の中にはないものに出会うこと、
その未知との遭遇の驚きを自分に向けて表明することだと言っていい”
本文中にあったこの一文。ここに、編集の真髄を感じた。
――佐渡島庸平氏
本書は、編集工学を手すりに「問い」の発生現場の謎を探る一冊。
学校教育では探究学習が浸透し、
ビジネスの現場でも自立型人材や、課題解決力よりも課題発見力の重要性が盛んに言われるようになった。
一方で、これまで「答え方」は練習してきたが、「問い方」は学んでこなかった。
「問う力」が必要であることは多くの人が共有し始めているのに、肝心な「問い方」がわからない。
なぜ「問う」ことは難しいのか?
小さい頃は「なんで?」「どうして?」の問いにあふれていたのに、
大人になって問えなくなるとしたら、何が邪魔をしているのか?
「問い」はどこからどうやって生まれてくるのか?
誰もが備え持つ「編集力」をもとに、
問いが生まれ出るプロセスを4つのフェーズで考えていく。
「問い」の土壌をほぐす:Loosening(第1章)
「問い」のタネを集める:Remixing(第2章)
「問い」を発芽させる:Emerging(第3章)
「問い」が結像する:Discovering(第4章)
本書を通して、本質を見抜き、世界を動かしていく
「内発する問い」を生み出す力を身につけよう。
【目次】
第1章 「問い」の土壌をほぐす:Loosening
第2章 「問い」のタネを集める:Remixing
第3章 「問い」を発芽させる:Emerging
第4章 「問い」が結像する:Discovering
第5章 「内発する問い」が世界を動かす
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Tenouji
おさむ
エジー@中小企業診断士
ほよじー
naohumi