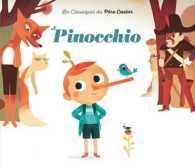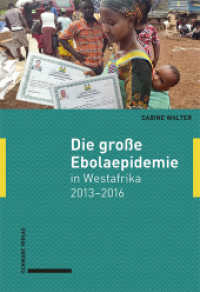- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
多くの動物にあって、ヒトにはないしっぽ。遠い祖先はしっぽが生えていたというが、いつの時点でヒトはしっぽを失ったのだろうか。はたまた長い歴史の中で、人は八岐大蛇や九尾狐など多くのしっぽを描いてきたが、そのしっぽの向こうに何を見ていたのだろうか。しっぽを知れば、ひとが分かる――。文理の壁を越えて研究を続けるしっぽ博士が魅惑のしっぽワールドにご案内!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
120
「ヒトはなぜしっぽを失くしたか」に興味を持った女性研究者の熱い思いが伝わってくる。文学部出身の著者が、理学部の大学院で博士号を取得するも、動物形態学では、しっぽの謎は解明できないと悟り、生物発生学を一から学んで、今も研究を続けている。明確な知的好奇心に基づき、狭い分野の蛸壷に陥ることなく、領域の壁を越えて研究活動の幅を広げる姿がとても頼もしい。郡司芽久さんの「キリン解剖記」もそうだったが、若い女性研究者のこういう一途で前向きな姿勢に心からのエールを送りたい。京大の白眉センターは、いいことをしていると思う。2024/10/05
姉勤
32
比較分類的な代物を期待していたが、これはこれで面白い。研究者たる著者の学者としての来し方、尻尾に興味を持った発端と転機、研究対象としてのヒトのシッポ。対象が化石、現世生物、胎児標本、発生のトリガーたる遺伝子、そして日本神話の研究と、疑問を解決するためにセクショナリズムに陥りがちな確固たる学術の世界に果敢に踏み込んでいく。古代ギリシャでは数学、工学、歴史、政治、文学の総合を、哲学と呼んだと聞いたことがあるが、学究とはそういうものだろう、著者を蔑んだ口舌の徒よ。2024/10/10
コピスス
13
文理を越えてしっぽについて研究をした本。胎児は発生過程でしっぽがあるのに、それが消えてしまう。確かに考えてみれば不思議。こちらはまだ研究途中ということで、解明される日が待たれる。ちなみにしっぽを持つヒトはいないらしい。(悟空は人間じゃないのね)日本書紀やミケランジェロの絵などに出てくるしっぽを調べたりするのも興味深い。2024/12/16
於千代
6
専門を「しっぽ」と語る著者が、自身の研究史とともに「しっぽ」のあれこれを語る一冊。生態学や解剖学といった学問分野にこだわらず、古典にまで分野を横断してアプローチする姿勢がとても興味深く、好奇心に突き動かされる研究とはこういうものかと感じさせられた。 特に印象に残ったのは、サルの分類において「しっぽの有無」が重要な基準になるという話。我々人間はゴリラなどと同じapeであってmonkeyではないとのこと。 今度「イエローモンキー」と罵られたら、「バカめ、人間はmonkeyではなく、apeだ」と返してやろう。2025/05/21
乱読家 護る会支持!
6
体感的に想像出来ない他の生き物たちの特徴。背中に羽が生えた昆虫、六本足の昆虫、そしてしっぽの生えた動物たち。 今自分にしっぽが生えていたら、どんなふうに使うんだろうか? 背中が痒い時にかく、トイレの後でトイレットペーパーを掴んで拭く? 11本目の指としてキーボードを叩く? ズボンの後ろにはしっぽを通すための穴が有る? 寒い冬には、手袋ならぬ、しっぽ袋をつける? 顔色をうかがうよりも、しっぽをうかがう? そして椅子には、しっぽを避けるための空間が常に必要になる? などと空想が膨らみました。 2024/11/10
-
- 洋書
- Pinocchio
-
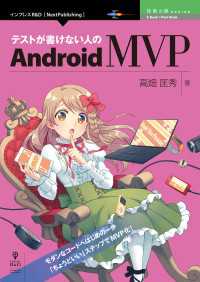
- 電子書籍
- テストが書けない人のAndroid M…