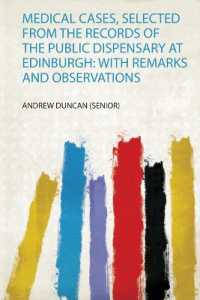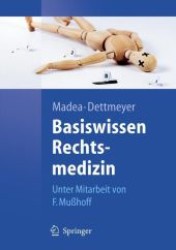- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
日本の漁業の生産量・生産額はこの30年減り続けている。魚の消費量もこの20年右肩下がりだ。漁業の未来への活路はあるのか。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Go Extreme
2
https://claude.ai/public/artifacts/be94b552-a099-4a91-9c44-958149294ea72025/06/10
takao
2
ふむ2024/06/10
0ku
1
水産業のアポリアという題材を扱う以上、やむを得ないのかもしれないが、投げっぱなしのような印象を受けた。 また経済学者の性なのか、短い文章で説明できる内容も、数式やグラフを用いて説明しており、なかなか苦しい一冊だった。2025/06/06
お抹茶
1
経済学の考え方を使ってさまざまなトピックを解説。経済学が生き生きしている。和食ブームで日本産の魚の輸出が伸び漁価が高くなると国内供給量は減少する。農林水産省は国民への水産物の供給と輸出振興という矛盾した政策を推進。安価な外国人労働力があると労働生産性を向上させるための資本投資の意欲が削がれる。豊洲市場での活車海老のように財が転売不可能で売り手に市場支配力がある場合,卸売業者が消費者余剰を獲得する。太平洋小島嶼国ではEEZ内で獲る権利を漁業国に与え,入漁料収入を得る。消費者の魚離れの経済学的検討も興味深い。2024/09/17
いちごチョコレート
0
人間が生態系に手をつけるとこれだけ問題が山積しますよ、という例を多分にみせてくれる1冊。回遊魚は世界中で奪い合う資源で人が管理すべきというとんでも論も含まれています。アポリアうんぬんよりも自分の身の回りに何が起きているかを業態を超えて考えさせられました2025/04/07
-
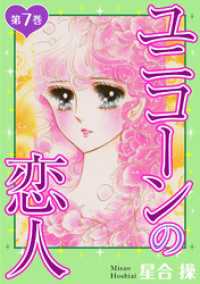
- 電子書籍
- ユニコーンの恋人 第7巻 少女宣言