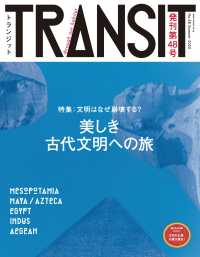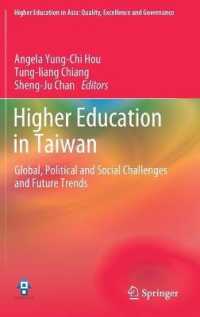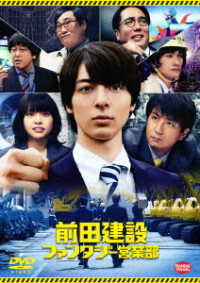- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
人文学の論文執筆には、基礎となる習得必須の知識と技術がある。しかし、それを現在の大学教育はうまくカリキュラム化できていない。どんな条件を満たせば論文は成立したことになるのか、どの段階でどの程度の達成が要求されるのか、そしてそのためにはどのようなトレーニングが必要なのか。そもそも、なんのために人文学の論文は書かれるのか。期末レポートからトップジャーナルまで、「独学で書く」ためのすべてを網羅する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
53
図書館除籍本。もったいない。重要箇所は明朝太字。読後としては、すらすら読める文体ってのがすごいね。論文:アーギュメントを論証する文章(27頁)。アンパンマンは、男性中心主義的な物語が女性キャラを排除している(24頁)。このような文章をたくさん作る練習を(26頁)とのこと。確か、アーギュメントといえば、植田一三先生もおっしゃってたね。アカデミックな価値は、反論可能な主張提示で会話を進めたときに発生する(41頁)。2025/12/26
エジー@中小企業診断士
31
論文の書き方を「徹底的に要素分解し、極限までプラクティカルに解説する」何が新しいのか。まず「問い」はあってもなくても良いとする。また、日本の人文学における論文観にアメリカンスタイルを輸入して刷新する。論文とは、アーギュメントを論証する文章である。アーギュメントとは論文の核となる主張内容を一文で表したテーゼである。テーゼとは論証が必要な主張である。アカデミックな価値をつくる。それには引用と否定が必要である。最重要なパラグラフはイントロダクションであり、アーギュメント・アカデミックな価値・シノプシスを含むこと2025/05/05
Carlyuke
30
Audible で。本を購入前に内容を聞くことができるのが利点。この本については紙の本もしくは電子書籍で読んで実際に何か書くときに是非参考にしたいです。2025/05/18
ife
29
論文だけでなく、目的を持った読み物を書く際に読むべき一冊。大言壮語する若き新鋭だが、それだけの実力と実感が伴った骨太の概説書。論文を書くということ、読むということのエッセンスが凝縮されており、私自身が修論を書きながら感じた学びが言語化されていて快かった。書く前に読み返すであろう。 また、論文に終始するだけでなく、一人の人間が、目的を持ってものを書くとはどういうことか、に対して考えているのがよかった。人文学というのはそういうことに資するべきであり、そういうことによって資されるべきなのだ。2024/11/19
ユーユーテイン
24
海外の研究論文の書き方をベースにしたアカデミック・ライティングの本は読んだことがあるが、形式を知っただけで、隔靴掻痒の感を拭うことができなかった。しかし、本書は海外の流儀を咀嚼して日本語話者や日本の文化に適合する書き方で示してくれている。本書が新しいのは、論文に「問い」が必須ではない、という主張だ。論文には鍛え上げたアーギュメント(主張)が必須だと訴える。論証する部分に書く内容についても詳細に示されているので、再読して理解したい。日米の学術界に挑み続ける筆者が掴んだ人文学研究の目的には、胸が熱くなった。2024/09/17