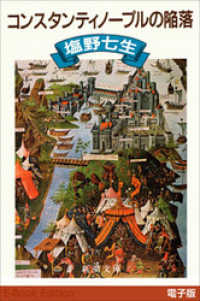内容説明
ドイツ生まれのユダヤ人少年の幸せな日々は、突然終わりを告げた。ゲットーへの「再定住」と父の死。強制収容所への移送と母の死。死があまりに身近な場所で、人間が失うことのできるほとんどすべてのものを失いながらも、運と知恵を頼りに少年は生き抜いた。移送された2011人の最後の生き残りとして、なお寛容を語った魂の記録。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
106
これはある意味ドキュメンタリーノヴェルなのでしょう。ヘンリー・オースターというナチのユダヤ人虐殺を逃れてアメリカに永住に地を求めた人物からその詳細を聞いたデクスター・フォードという人がまとめたもののようです。ナチについては様々な文献などがあったりするのであまり珍しくはないのですが、写真などを多用してしかも少年時代のユダヤ人収容所の悲惨な日常が記されています。一気に読まされました。2026/01/12
とよぽん
62
ナチスの狂気に翻弄されたユダヤ人の少年オースターが語った残虐の全て。ドイツ国民として父母と3人、何不自由なく暮らしていた子ども時代だったが、小学校に入学した頃からユダヤ人に対する差別が・・・。強制収容所での絶望的な日々を彼は生き延びて、ドイツ敗戦により解放された孤児たちはフランスに引き取られる。その後アメリカに渡り、叔父と叔母の養子となる。彼が生き延びることができたのは、厩番の仕事を与えられたことが大きく影響している。それゆえのタイトルなのだろう。彼が語る「寛容」という言葉の重みに圧倒された。2024/10/11
つちのこ
50
ホロコーストを生き延びたドイツ系ユダヤ人の少年の手記。10年間の囚われの生活は、ゲットーからアウシュヴィッツ、死の行進を経てブーヘンヴァルトで餓死寸前になって解放されるまで。厩番での労働期間はわずかだが、悲惨を極める収容所生活の中では、仕事にやりがいを見出し精神的に安定していた時期だったことが伺える。本書の肝はタイトルよりも、解放されてからの第二の人生に比重があるといってもいい。ナチスによってケルン市から連れ去られた2011人のユダヤ人のうち、終戦を迎えたのは23人。著者の「寛容」という言葉が重く響いた。2024/10/08
kawa
40
ナチスドイツによるホロ・コーストに巻き込まれたユダヤ人青年の手記。1941年、ケルンに住む12歳のヘンリー・オースターは、父母と一緒にポーランド・ウーチに強制移送、その後終戦まで何度もの生死の危機を乗り越え生き残る。初期のユダヤ人排斥からアウシュビッツ等の収容、戦後のアメリカでの成功まで、淡々と全貌が記されていることに却って迫力を感ずる。ナチスの差別思想に当時のアメリカの優生学運動の影響があったこと、「死の天使」として怖れられたヨーゼフ・メレンゲがロック・フェラー財団から研究助成を受けていたことも初知り。2024/12/18
tosca
38
アウシュヴィッツでの実話はプリーモ・レーヴィも読んだが、この本の語り手は当時は少年だった。ドイツ国民だったユダヤ人の子供が生き残った例は数少ないのだそうだ。裕福な両親と笑っている5歳の写真。その後ナチの弾圧が始まり11歳でゲットーへ強制移住させられ、その後は強制収容所へ移送される。両親も失い収容所の殆どのユダヤ人が東欧系でドイツ語を理解しなかったので彼の孤独と絶望は計り知れない。後にアメリカ国民となった彼の行動や言葉が素晴らしい。日常が脆くも崩れ去るという事態が身近で起こり得る今だからこそ読むべき本と思う2025/01/16