内容説明
500年以上続いた未曾有の国家事業ーー勅撰和歌集
天皇の命を受けて編纂された歌集ーー勅撰和歌集は、乱世のなか500年以上にわたって生み出されてきた。古今和歌集をはじめ、初期の勅撰集に注目が集まりがちだが、勅撰和歌集が権威を持つようになったのは鎌倉時代以降のことである。しかし、それぞれの勅撰集がいかに編纂されたかは意外なほど知られていない。本書では鎌倉時代の勅撰集がいかに編纂されたかを、新史料も交えてつぶさに描き出す。それによって見えてくるのは、単なる文学史を超えた、和歌と政治の相互補完関係という中世という時代の特質である。
【内容】
はじめに
序章 和歌所とその源流
第一章 開闔・源家長と歌人たち―新古今和歌集
第二章 撰者の日常―新勅撰和歌集
第三章 創られる伝統―続後撰和歌集
第四章 東西の交渉と新しい試み―続古今和歌集
第五章 和歌所を支える門弟―続拾遺和歌集
第六章 打聞と二条家和歌所―永仁勅撰企画・新後撰和歌集
第七章 おそろしの集―玉葉和歌集
第八章 法皇の長歌―続千載和歌集
第九章 倒幕前夜の歌壇―続後拾遺和歌集
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
106
勅撰和歌集は八代集まで有名だが、残り十三代集は知られておらず後世の評価も低い。しかし十三代集期こそ勅撰集に権威が備わり、その成立事情も複雑になっていく。鎌倉幕府の誕生で権力を握った武士が、今度は文化的地位を求めて勅撰集への入集を望んだ。しかも皇統分裂に伴って歌道家も双方に味方する家に分かれ、勅撰集を権勢の証とするようになった結果、1世紀で8回も編纂されたのだ。武士の入集を増やして幕府に色目を使ったり、自らの属する党派を賞賛するために歌壇が栄えた。美しい文化と生臭い政治の表裏一体ぶりは、何ともグロテスクだ。2024/08/25
MUNEKAZ
14
鎌倉時代の勅撰和歌集を扱った一冊。文学的な側面よりも、その政治的な部分に注目する。後鳥羽院という天才から始まった中世の勅撰和歌集は、藤原定家の活躍を経て御子左家が、その撰者を家職とするに至る。しかし世は分裂の時代。御子左家が二条家と京極派、冷泉派に分かれ、さらに天皇家も大覚寺統と持明院統に分裂する。この2つの分裂が絡み合い、撰者を巡って訴訟合戦が続くあたりが面白い。また混乱の中でも、和歌集の権威はしっかりと確立されており、南北朝期まで衰えなかった。文学的評価は芳しくないが、中世和歌の盛期でもあるのだ。2024/08/05
chisarunn
9
適当な解説書が見つからなくて謎だった新古今以降の勅撰集の様子がよくわかった。藤原定家の子孫が、幾つもの系統に別れながら、あるいは皇統が二つに分裂しながらも「勅撰集」という国家的事業が続いてきた経緯がわかりやすく書かれている。続編もぜひ読みたい。2025/07/25
つきもと
8
勅撰集の成立や時代背景、当時の文化との関連をまとめた本。時代を経て編纂がシステマティックになっていくのがおもしろいです。一首の和歌が他の和歌との並びでどう読み方が変わるかなどの解説もあり、なるほどと思わされました。和歌、ではなく、和歌集として見た時に意味や価値が変わるということですね。続編も予定されているようなので楽しみです。2024/09/03
紅林 健志
6
新古今集から続後拾遺集までの鎌倉時代の勅撰集を取り上げて和歌史の展開を描いてみせる。これは同時に御子左家の歌道師範家としての歴史にもなっている。おもしろい。定家を文句の多い気むずかしい人間としてとらえているところなど新鮮だった。鎌倉後期に「一ふし」「曲折」など後の俳論でよく出ることばが登場するとはじめて知った。室町時代は続編で扱う予定らしい。楽しみ。2024/08/15
-

- 電子書籍
- まめとむぎ 分冊版 12 ジュールコミ…
-
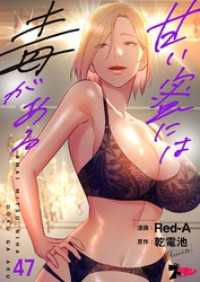
- 電子書籍
- 甘い蜜には毒がある【タテヨミ】 47
-
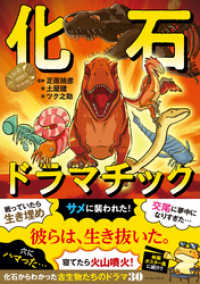
- 電子書籍
- 化石ドラマチック
-
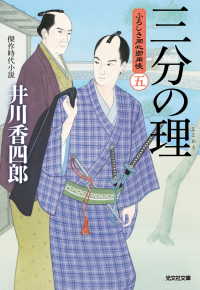
- 電子書籍
- 三分の理(ことわり)~ふろしき同心御用…
-
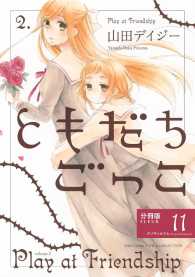
- 電子書籍
- ともだちごっこ 【分冊版】 - FLE…




