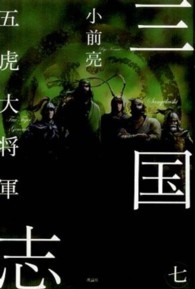- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
日経BPクラシックス 第11弾
第三分冊は、第4篇「相対的増殖価値の生産」の最後となる第13章「機械類と大工業」と、第5篇「絶対的増殖価値と相対的増殖価値の生産」の第14章から第16章まで、第6篇「労働賃金」の第17章から第20章までを収録。
全体で470ページほどのうち、250ページを超えるのが第13章。産業革命に伴う機械システム、工場制度の分析を通して、資本制生産が労働者を非人格化していく様子を描く。
「マニュファクチュアと手工業の時代には、労働者は道具を自分に奉仕させたが、マニュファクチュアと手工業の時代には、労働者は機械に奉仕する」
「機械で働く労働者は、仕事の内容を奪われているために、もはや細部における手腕などは、取るに足らぬ些事として姿を消す。その代わりに登場したのが機械システムのうちに体現された科学、巨大な自然力、
社会的な集団労働であり、これらが今や機械システムとともに『主人』の権力を構築する」
第17章「労働力の価値または価格の労働賃金への変容」以降は、増殖価値の源泉である労働力商品の価値が、労働賃金に変容していくからくりを詳細に解説する。
もっと少なく読む
目次
第4篇 相対的増殖価値の生産(承前)(機械類と大工業)
第5篇 絶対的増殖価値と相対的増殖価値の生産(絶対的増殖価値と相対的増殖価値;労働力価格と増殖価値の量的な変動;増殖価値率のさまざまな定式)
第6篇 労働賃金(労働力の価値または価格の労働賃金への変容;時間給の賃金;出来高賃金;国による労働賃金の格差)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かわうそ
タカオ
mass34
Ikkoku-Kan Is Forever..!!
上り下り澱